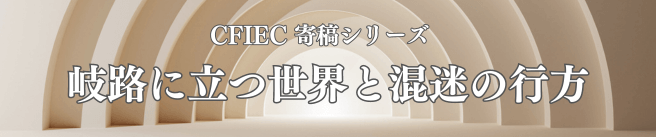
「インド太平洋」の理想と現実 ― 豪州の視点

掲載日:2024年3月28日
青山学院大学 准教授
佐竹 知彦
はじめに
2010年代から米国や豪州が中心となって提唱してきた「インド太平洋」という地域概念は、今や国際社会においてほぼ市民権を得たように思える。2016年8月に日本が「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)構想を、2019年6月に東南アジア諸国連合(ASEAN)が「インド太平洋に関するASEAN アウトルック」(AOIP)を、そして同年11月にはインドが「インド太平洋海洋イニシアティブ」を発表した。最近では、この概念の使用に慎重であった韓国の新政権が「自由、平和、繁栄のインド太平洋戦略」を発表したことも記憶に新しい。また欧州連合(EU)や英国、フランス、ドイツといった国々もそれぞれ独自のインド太平洋戦略(ないし政策ガイドライン)を発表しており、今やインド太平洋という地域概念は当該地域を越えて、世界的な広がりを見せつつある。
なぜ、2010年代以降この概念が急速に広がりを見せたのだろうか。本稿では、「インド太平洋」概念の発祥の地の一つである豪州の議論を追うことで、この問題について考えてみたい。
豪州とインド太平洋
インド太平洋という概念は、2010年代初頭から豪州の政策コミュニティで盛んに提唱されるようになった。2012年の労働党政権時代に発表された外交白書や、その翌年に発表された国防白書でも、インド太平洋という地域概念の台頭に言及があった。さらに自由党率いる保守連合政権に変わってから発表された2016年版の国防白書では、「安定し、繁栄したインド太平洋とルールに基づくグローバルな秩序」が、豪州の国益の一つとして掲げられた。翌年発表された新たな外交白書では、インド太平洋という言葉が実に70回以上も登場するなど、豪州の中でこの地域概念が完全に定着したことが伺える。安倍政権がFOIPを発表する数年前から、豪州ではインド太平洋という地域概念に注目が集まっていたのである。
それでは、なぜこの地域概念が豪州で注目を浴びるようになったのだろうか。そのことを考える上では、当時の豪州が置かれていた戦略状況を知る必要がある。冷戦後の豪州は、一方で緊密な米国との同盟関係を維持しつつ、他方で主要な資源の輸出先である中国との経済関係を急速に強化させていた。2000年代の後半に中国は日本を抜いて豪州にとっての最大の貿易パートナーとなり、さらに2010年代半ばにはその豪州の輸出に占める割合が35%にまで上昇した。この時期、しばしば「中国がくしゃみをすれば風邪をひく」と揶揄されたように、豪州の対中経済依存は他のアジア諸国と比較しても群を抜いていたのである。
その一方で、2000年代後半より中国の海洋進出や対外姿勢の強硬化が目立つようになると、豪州の中でも中国に対する警戒感が徐々に強まっていた。2009年に発表された豪州の国防白書は中国の軍事力の強化と近代化のスピードに異例とも言える警鐘を鳴らし、海軍力を中心とした豪州軍の大幅な増強を提唱した。またその前年には、労働党の首相が豪州のブロードバンド・ネットワークへの参入企業から、中国の「華為」を事実上外す決断を行った。同じ頃、豪州は安全保障面における日本との協力を強化していたが、それも多くの面においてこうした豪州の中で高まる対中警戒論を背景としたものであった。
仮に中国がこのまま軍事的拡張を続け、地域で覇権を握る米国と衝突するようなことがあれば、安全保障面では米国、そして経済面では中国に対する「二重の依存」によって安全と繁栄を享受してきたこれまでの豪州の路線は、成り立たなくなってしまう。むしろ、米中間の緊張が高まるにつれ、豪州は米中どちらかを「選択」する必要に迫られるかもしれない。2010年に「パワー・シフト」と題する論考を発表したヒュー・ホワイト豪国立大学(ANU)教授は、以上の観点から豪州が米国とともに中国と対決するのではなく、むしろ両者の融和を図ることで、アジアにおける大国間の均衡(コンサート・オブ・アジア)の確立を目指すべきと説いた。ホワイトの議論は豪国内外で大きな反響を呼び、「ヒュー・ホワイト論争」と呼ばれる議論を巻き起こした。
もっとも筆者の知る限り、豪州の政策決定者や、政府に近い一部の専門家は、ホワイトの議論をまともには受け止めていなかった。彼ら/彼女らの多くは、ホワイトの主張する米中の「パワー・シフト」が誇張された考えだと捉え、それゆえに豪州が米中間で「選択」を迫られるとするホワイトの議論を「ナンセンス」として退けていた。実際に2016年の国防白書は、中国やインドといった新興国の台頭を認めつつ、米国の一極体制が少なくとも今後10年間は続くであろうとの見通しを立てていた。豪州の政府もまた、豪州が米中いずれか一方を「選択」する必要はないとの立場の下、中国企業によるダーウィン港湾の99年リースを認めたり、中国の主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加を表明するなど、日米とは異なる独自の対中政策を展開していた。
ところが、現実はむしろホワイトの予測により近い形で推移することになる。2010年以降も中国の経済は加速度的に成長し、それにあわせて軍事費も毎年2桁以上の伸び率を維持した。さらに中国は、弾道ミサイルや核戦力の増強を図るとともに、東シナ海や南シナ海における自らの権益の既成事実化を着々と進め、米国に対する「接近阻止・領域拒否」戦略の地歩を固めた。中国はまた、2010年代の半ばより南太平洋における軍事プレゼンスの伸長を図ったことで、豪州にとってもその影響力が目に見えて強まることとなった。同じ頃、豪州国内では中国による豪州政治やメディアへの影響力工作や浸透工作が次々と明らかとなり、国民の間でも「中国恐怖症」が急速に広まっていた。
一方、頼みの綱である米国では、世論の分断や議会の停滞、予算のデフォルト等により、先の見えない混乱が続いていた。おそらく豪州は、2016年11月の米大統領選におけるドナルド・トランプ候補の勝利にもっとも衝撃を受けた国の一つであろう。トランプ政権の掲げる「米国第一主義」や反リベラリズムは、ミドルパワーとしてリベラル国際秩序への貢献を自負してきた豪州の価値観と、あらゆる意味で相容れないものであった。トランプ政権の誕生後、豪州の中で米国の保護を想定しない独自の路線を意味する「プランB」が盛んに議論されたのは、必ずしも安全保障の理由だけではなかろう。米国で国際主義や自由主義的価値観を否定する大統領が初めて誕生したことにより、「価値同盟」としての米豪同盟の基盤が失われることへの恐れが、豪州における「トランプ・ショック」の根底にあったのである。
活路としてのインド太平洋
インド太平洋という地域概念は、上記で述べた豪州が抱える戦略的なジレンマを解消する手段としての側面を持っていた。そこでの一つのキーワードは、「多極化」である。トランプ政権の誕生後に発表された豪州の外交白書は、2030年までに中国が米国を抜いて世界第一位の経済大国になるという見通しを示しつつ、同時にインドやインドネシア等の新興国の台頭により、2030年代に向けて世界が多極化していくとの見通しを示した。さらに米国やEU、そして日本もそうした多極化された世界の重要なプレイヤーであり、それらの国々との「インド太平洋パートナーシップ」を強化していくという方針が示されていたのである。
そうしたパートナーシップの強化が、中国の台頭を念頭に置いたものであることは論を俟たない。しかしながら、それは必ずしも対中「封じ込め」を意味するものではない。外交白書が作成された時期に外務次官を務め、引退後も活発な言論活動を続けているピーター・バギースによれば、それは対中「封じ込め」というよりも、中国の台頭を「管理」する手段である。豪州が米国やインド、そして日本といった国々と共に中国に対する「戦略的均衡(strategic equilibrium)」を形成することで、中国の覇権主義的な野心や冒険主義的な行動を抑制し、「ルールに基づく秩序」へと導くことが可能となる。そうした地域における安定的な均衡体制があって初めて、豪州は中国とも貿易を含めた良好な関係を維持することが可能となると考えられているのである。
日米豪印(QUAD)や豪英米の安全保障協力(AUKUS)は、そうしたインド太平洋秩序を実現する上で鍵を握る枠組みとして捉えられている。よく知られている通り、2007年に日本の安倍政権がQUADを提唱した際、豪州はそれに参加しないという決断を下した。ところがその後、南シナ海や南太平洋等で中国の拡張主義的な行動が強まったことにより、豪州ではQUADに対する超党派的な支持が形成されるに至った。さらに2020年初頭から広まったコロナ感染症をきっかけに豪中間で対立が深まると、翌年9月に豪州は米英とAUKUSを結成し、両国との協力のもと原子力潜水艦を取得するとの発表を行い、世界を驚かせた。
QUADは目下のところ軍事的な協力ではないが、経済安保や環境政策といった非軍事的な分野での協力より、中国に対する戦略的な優位性の確保を目指したものである。QUADはまた、「戦略的自律性」を掲げるインドを西側諸国に引き付けるという意味でも、重要な使命を持っている。これに対しAUKUSは豪州に対する原子力潜水艦の供与に加え、新興技術開発における協力という役割を持つ。特に豪英米が防衛産業基盤の強化や一体化を通じて武器・装備品のより効率的な開発や技術革新を目指すことにより、この分野においても優位に立とうとしている中国に対するカウンター・バランスとなることが期待されている。だからこそ豪州は、AUKUSを「国家的事業」として捉え、その実現に向けた国を挙げた取り組みを強化しているのである。
ミドルパワー外交からの決別
このように、豪州にとってのインド太平洋とはある種の多極的な秩序であり、そこにおける「戦略的均衡」を維持することが、地域の安定化に不可欠な要素として捉えられている。だからこそ豪州は、QUADやAUKUSといった協力を推進するとともに、戦後類を見ないペースで国防力の強化を進めているのである。原子力潜水艦の取得という「ハイリスク・ハイリターン」の決断を下し、そのために国を挙げた体制を敷いているのは、そうした豪州の並々ならぬ決意の表れであった。
2023年4月に発表された豪州の「戦略防衛見直し」は、米国の「一極体制」が終焉したとの見通しのもと、豪州の国防路線をそれまでの低強度紛争への対応に焦点を置いた「豪州の防衛」路線から、より強度の高い紛争への対処を目的とした「国家防衛」路線に転換することを提言した。そこでは、これまでの陸海空の均衡の取れた国防力から、海空領域における長距離打撃能力や新領域といった非対称能力の強化に資源を集中することで、中国の脅威に対抗するという構想が描かれていた。
これは、言ってみれば豪州が戦後初めて、中国の軍事力と(非対称ではあるが)直接対峙できるだけの能力を構築する決断を下したということでもある。米国の圧倒的な優位(プライマシー)が続く限りにおいて、中国の戦略的な影響力が豪州にまで及ぶことなど考えられなかった。そこにおいて豪州がすべきこととは、グローバルなテロとの戦いや地域の平和維持活動といった相対的に非論争的な分野で同盟に貢献することで、米国の覇権秩序を側面から支え、同時に中国との良好な関係を維持することであった。そうした状況において、豪州が他国との本格的な紛争事態に関与する可能性は、限りなく低く見積もられていたのである。ところが、中国の軍事的な能力が米国のプライマシーを破る可能性が生まれたことで、豪州は米国との緊密な同盟を維持しながらも、同時により自主的な国防力の強化を急ピッチで図っているのである。
それはまた、戦後の豪州の外交安全保障路線の重大な転換を意味していた。特に70年代以降の豪州は、いわゆる「中級国家(ミドルパワー)」として平和維持活動や多国間外交、そして核軍縮・不拡散といった大国があまり関与しない「ニッチ」な分野における活動に力を入れてきた。豪州はまた、大国間の権力政治からは一定の距離を置き、自由貿易や民主主義、人権といった価値規範に重きをおく「良き国際市民」としてのアイデンティティを強調してきた。それは、「ダウン・アンダー」と呼ばれる南半球の最果てに位置し、自国の力だけではその広大な国土を守ることすら困難な豪州が、自国のプレゼンスを国際社会において最大限発揮するための一つの知恵であり、「生き様」でもあった。
豪州は今、そうした戦後の「生き様」と決別し、地域の「戦略的均衡」に影響を与えうる主要なプレイヤーとしての立ち位置を確立しようとしている。豪州がいわば「国是」として追求してきた核軍縮や核不拡散の流れに逆行するとの批判を受ける恐れがありながら、それでも原潜の導入を決めたのは、そうした豪州の方針転換を象徴する出来事であった。またかつて一旦は不参加を表明したQUADの枠組みに超党派のコミットメントを示しているのも、そうした豪州のインド太平洋にかける並々ならぬ決意の表れとして受け止めることができよう。
インド太平洋の理想と現実
問題は、地域の戦略的均衡の維持に寄与するという豪州の目標が、果たしてどこまで現実的なのかということだ。確かに豪州は、移民の増加や資源輸出を中心とした輸出指向型の経済により、近年まで先進国としては稀に見る好調な経済成長を維持してきた。また日本や韓国といった高齢化に苦しむ地域の先進民主主義国家と比べれば、豪州の財政状況は健全である。加えて、ウクライナ戦争の影響によって世界的なエネルギー価格の高騰が進む中で、資源大国である豪州のプレゼンスは一層高まっている。原潜の導入をはじめとした急速な国防力の強化や国防費の増額を進める背景には、こうした豪州の経済に対する一定の自信が垣間見える。
その一方で、不動産価格をはじめとしたインフレや豪ドル安の進行等により、豪州経済の先行きの見通しは必ずしも明るいとは言えない。また日本や韓国ほどではないにせよ、高齢化の進行は一定程度豪州の経済にも影を及ぼしている。2023年に政府が発表した豪州経済の長期的な見通しに関する報告書は、少子高齢化や生産年齢人口の減少により、今後40年間の経済成長率は過去40年間のそれと比べ0.9%低下するとの見通しを示した。これに対し豪州の国防費は膨らむ一方であり、他の支出に対する影響が及ぶことは避けられない状況になっている。
だが、問題は財政面だけではない。長らく本格的な紛争事態を想定しない装備体系を維持してきた豪州軍は、中国の脅威に対峙するにはあまりにも心細い戦力となっている。現行の「コリンズ」級潜水艦はすでに老朽化が進み、故障や修繕等で満足に稼働できないこともある。また水上艦の主力となる「アンザック」級フリゲート艦も、艦船の乗組員不足等によって稼働率が低下している。さらにその後継として期待されていた英BAE社の「ハンター」級フリゲート艦は様々な問題から調達が遅れ、2024年2月に国防省が発表した新たな水上艦見直しの報告書では、その調達数を9隻から6隻に減らすことが提言されていた。その一方で、報告書は11隻の新たなフリゲート艦の導入により、2040年代までに豪州の戦闘艦を倍増することを提言しているが、艦船の建造や維持に携わる労働力が不足している状況で、その計画の実現性を危ぶむ声も多い。
加えて、AUKUSを通じた原潜の取得についても、多くの課題が指摘されている。例えば、豪州では原潜の建造や維持等に必要となる民間の労働力の数が、現状では圧倒的に不足している。また民間の労働力の供給不足は、豪州軍の人員不足という問題にも波及しており、特に上で挙げた艦船や潜水艦の乗組員不足という問題が既に表面化している。さらに、原潜の維持費や運用コストを含めると総額2680億〜3680億豪ドル(日本円で約26兆〜36兆)にも上るとも言われる巨額のコストとその費用対効果については、疑問の声も少なくない。2023年5月にはAUKUSに批判的な議員や元議員、元軍人、専門家等による公開レターが豪州の主要紙に掲載され、AUKUS決定の背景や予算コスト、計画期間等について政府側の回答を求めた。
原潜の調達に向けたリスクは、2024年11月に予定されている米国大統領選で共和党のトランプ候補が勝利した場合、さらに高まることになるであろう。そもそも共和党は自国の原潜製造ラインの維持という観点から、豪州への原潜の供与を渋っていた。2023年12月に可決された国防授権法は、豪州へのヴァージニア級原潜3隻の供与を原則として認めたものの、あくまで原潜の供与が米国の能力を損なわず、またその外交政策や国益とも合致するものであることを大統領が証明するという条件が付けられている。「米国第一主義」を掲げるトランプ候補が、こうした条件を呑んでまで豪州に原潜を供与するという決断を下すためには、豪州政府による相当な働きかけが必要となるであろう。
それでは、もう一つの頼みの綱であるインドはどうであろうか。豪州は2010年代半ばからインドとの安全保障関係を強化し、軍の後方支援協定や防衛科学技術協定も結んでいる。また経済的にも、中国に代わる市場としてのインドを高く評価し、暫定的な自由貿易協定となる経済協力貿易協定(ECTA)の締結を含めて幅広い関係を強化している。2023年5月にモディ首相がインドの首相としてはおよそ9年ぶりに豪州を訪問した際、豪州が国を挙げてこれを歓迎し、大きな盛り上がりを見せたことは記憶に新しい。同年8月には、米印の演習として始まり、その後日本、そして豪州が加わり4カ国の演習となった軍事演習「マラバール」が初めて豪州で開催された。
その一方で、インドは同年末に開催された米豪の合同演習への招待を拒否し、またマラバールをQUADの協力とは切り離すことを求めるなど、日米豪との軍事的な協力の進展には慎重な姿勢を崩してはいない。またインドとロシアの伝統的な関係は、特に新興技術面における他のQUAD諸国との軍事関係の強化を困難なものとしている。経済的にも、ECTAの締結後インドから豪州への輸出は上昇したものの、豪州からの輸出は必ずしも伸びていない。特に豪州が力を入れるインドへの石炭輸出は、中国による制裁の影響もあって2022年に増加したものの、中国の制裁が緩和された2023年には再び元のレベルに戻った。インドと豪州の間にはまた、ウクライナ戦争やミャンマー軍事政権への対応、そして人権や民主主義、自由なデータの移動に対する考え方という点でも、隔たりがある。2023年11月に発覚したインド政府の関与が疑われる米国在住のシーク教徒の殺害計画は、米印関係やQUADの協力にも暗い影を及ぼしている。
おわりに
以上をまとめると、豪州にとってのインド太平洋とは、米中のみならずインドや日本、そして豪州を含む地域諸国を含む多極的な秩序を構築し、またそれぞれの国が中国に対して「戦略的均衡」を維持することによって、包摂的でルールに基づく秩序の維持と強化を図るという構想である。その意味で豪州にとってインド太平洋は単なる地域概念を超えた、「秩序構想」としての意味を持っていると筆者は考える。それはまた、安全保障は米国、経済は中国という大国にそれぞれ依存してきた豪州の戦略的ジレンマを解消する手段としての側面を持つものであり、それが故に近年豪州は、伝統的な「ミドルパワー外交」から決別し、国防力の増強や同盟国・友好国との関係強化、そしてQUADやAUKUSの強化を通じて、インド太平洋秩序の実現に向けた軍事的な取り組みを強化している。
もっとも現実は、必ずしも豪州の思うように進んでいない。豪州の国防力の強化は、予算不足や労働力不足、そしてスピード不足といった様々な課題に直面している。特に原潜の取得については、上記問題に加え米国の国内政治の動向により、懐疑論が強まりつつある。仮に豪州の国防力強化が成功し、豪州が「戦略的均衡」を形成するための意味あるプレイヤーになれたとしても、それは早くても2040年代以降の話であり、それまでの間に地域で紛争が起こる可能性は否定できない。こうした可能性は、特に中国に対して好戦的な姿勢を示すトランプ候補が大統領になった場合、より高まるであろう。さらにもう一つのキープレイヤーであり、「グローバル・サウス」の盟主を自負するインドが、米豪や日本と共に中国に対する「戦略的均衡」に全面的にコミットする保証もない。
果たして豪州は、中国に対する「戦略的均衡」の形成が挫折した場合の「プランB」を持っているのだろうか。かつてホワイトが唱えたアジアにおける大国間の協調は、豪州を含む中小国の利益を軽視しているという点で、豪州にとっても許容できるものではない。また2020年以降対中関係が極度に悪化し、さらに対中警戒感がかつてなく高まっている中において、中国に対して「宥和」を図るという選択肢も考えにくい。結局のところ豪州は、貿易やサプライチェーンの多角化を通じて徐々に中国への経済的な依存を減らしつつ、安全保障面においては米英という伝統的なパートナーへの依存を深めていく以外に道はない。これに対し中国は、ロシアや北朝鮮といった権威主義国家との連携を一層強化させることで、既存秩序への挑戦を強めていくことになろう。豪州の描くインド太平洋の理想と現実の間には、依然として大きな隔たりがある。そしてそうした隔たりは、時と共に大きなものとなっているようにも見えるのである。
執筆者プロフィール
佐竹 知彦(さたけ ともひこ)
青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 准教授
慶應義塾大学法学部、同大学大学院法学研究科修士課程、オーストラリア国立大学博士課程修了。Ph.D. (国際関係論)。2010年防衛研究所入所、2015年4月より同主任研究官、2023年4月より現職。2013年~2014年にかけて防衛省防衛政策局国際政策課部員として多国間の安全保障協力を担当。また2020年には外務省の第9回太平洋・島サミットに向けた有識者会合委員を務める。専門はアジア太平洋の国際関係、豪州の外交・安全保障政策。著書:『冷戦後の日豪安全保障協力―「距離の専制」を越えて』(単著、勁草書房、2022年)、『「防衛外交」とは何か』(共著、勁草書房、2021年)、『UP plusアフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』(共著、東京大学出版会、2020年)、『冷戦後の東アジア秩序』(共著、勁草書房、2020年)等。
青山学院大学 准教授
佐竹 知彦
はじめに
2010年代から米国や豪州が中心となって提唱してきた「インド太平洋」という地域概念は、今や国際社会においてほぼ市民権を得たように思える。2016年8月に日本が「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)構想を、2019年6月に東南アジア諸国連合(ASEAN)が「インド太平洋に関するASEAN アウトルック」(AOIP)を、そして同年11月にはインドが「インド太平洋海洋イニシアティブ」を発表した。最近では、この概念の使用に慎重であった韓国の新政権が「自由、平和、繁栄のインド太平洋戦略」を発表したことも記憶に新しい。また欧州連合(EU)や英国、フランス、ドイツといった国々もそれぞれ独自のインド太平洋戦略(ないし政策ガイドライン)を発表しており、今やインド太平洋という地域概念は当該地域を越えて、世界的な広がりを見せつつある。
なぜ、2010年代以降この概念が急速に広がりを見せたのだろうか。本稿では、「インド太平洋」概念の発祥の地の一つである豪州の議論を追うことで、この問題について考えてみたい。
豪州とインド太平洋
インド太平洋という概念は、2010年代初頭から豪州の政策コミュニティで盛んに提唱されるようになった。2012年の労働党政権時代に発表された外交白書や、その翌年に発表された国防白書でも、インド太平洋という地域概念の台頭に言及があった。さらに自由党率いる保守連合政権に変わってから発表された2016年版の国防白書では、「安定し、繁栄したインド太平洋とルールに基づくグローバルな秩序」が、豪州の国益の一つとして掲げられた。翌年発表された新たな外交白書では、インド太平洋という言葉が実に70回以上も登場するなど、豪州の中でこの地域概念が完全に定着したことが伺える。安倍政権がFOIPを発表する数年前から、豪州ではインド太平洋という地域概念に注目が集まっていたのである。
それでは、なぜこの地域概念が豪州で注目を浴びるようになったのだろうか。そのことを考える上では、当時の豪州が置かれていた戦略状況を知る必要がある。冷戦後の豪州は、一方で緊密な米国との同盟関係を維持しつつ、他方で主要な資源の輸出先である中国との経済関係を急速に強化させていた。2000年代の後半に中国は日本を抜いて豪州にとっての最大の貿易パートナーとなり、さらに2010年代半ばにはその豪州の輸出に占める割合が35%にまで上昇した。この時期、しばしば「中国がくしゃみをすれば風邪をひく」と揶揄されたように、豪州の対中経済依存は他のアジア諸国と比較しても群を抜いていたのである。
その一方で、2000年代後半より中国の海洋進出や対外姿勢の強硬化が目立つようになると、豪州の中でも中国に対する警戒感が徐々に強まっていた。2009年に発表された豪州の国防白書は中国の軍事力の強化と近代化のスピードに異例とも言える警鐘を鳴らし、海軍力を中心とした豪州軍の大幅な増強を提唱した。またその前年には、労働党の首相が豪州のブロードバンド・ネットワークへの参入企業から、中国の「華為」を事実上外す決断を行った。同じ頃、豪州は安全保障面における日本との協力を強化していたが、それも多くの面においてこうした豪州の中で高まる対中警戒論を背景としたものであった。
仮に中国がこのまま軍事的拡張を続け、地域で覇権を握る米国と衝突するようなことがあれば、安全保障面では米国、そして経済面では中国に対する「二重の依存」によって安全と繁栄を享受してきたこれまでの豪州の路線は、成り立たなくなってしまう。むしろ、米中間の緊張が高まるにつれ、豪州は米中どちらかを「選択」する必要に迫られるかもしれない。2010年に「パワー・シフト」と題する論考を発表したヒュー・ホワイト豪国立大学(ANU)教授は、以上の観点から豪州が米国とともに中国と対決するのではなく、むしろ両者の融和を図ることで、アジアにおける大国間の均衡(コンサート・オブ・アジア)の確立を目指すべきと説いた。ホワイトの議論は豪国内外で大きな反響を呼び、「ヒュー・ホワイト論争」と呼ばれる議論を巻き起こした。
もっとも筆者の知る限り、豪州の政策決定者や、政府に近い一部の専門家は、ホワイトの議論をまともには受け止めていなかった。彼ら/彼女らの多くは、ホワイトの主張する米中の「パワー・シフト」が誇張された考えだと捉え、それゆえに豪州が米中間で「選択」を迫られるとするホワイトの議論を「ナンセンス」として退けていた。実際に2016年の国防白書は、中国やインドといった新興国の台頭を認めつつ、米国の一極体制が少なくとも今後10年間は続くであろうとの見通しを立てていた。豪州の政府もまた、豪州が米中いずれか一方を「選択」する必要はないとの立場の下、中国企業によるダーウィン港湾の99年リースを認めたり、中国の主導するアジアインフラ投資銀行(AIIB)への参加を表明するなど、日米とは異なる独自の対中政策を展開していた。
ところが、現実はむしろホワイトの予測により近い形で推移することになる。2010年以降も中国の経済は加速度的に成長し、それにあわせて軍事費も毎年2桁以上の伸び率を維持した。さらに中国は、弾道ミサイルや核戦力の増強を図るとともに、東シナ海や南シナ海における自らの権益の既成事実化を着々と進め、米国に対する「接近阻止・領域拒否」戦略の地歩を固めた。中国はまた、2010年代の半ばより南太平洋における軍事プレゼンスの伸長を図ったことで、豪州にとってもその影響力が目に見えて強まることとなった。同じ頃、豪州国内では中国による豪州政治やメディアへの影響力工作や浸透工作が次々と明らかとなり、国民の間でも「中国恐怖症」が急速に広まっていた。
一方、頼みの綱である米国では、世論の分断や議会の停滞、予算のデフォルト等により、先の見えない混乱が続いていた。おそらく豪州は、2016年11月の米大統領選におけるドナルド・トランプ候補の勝利にもっとも衝撃を受けた国の一つであろう。トランプ政権の掲げる「米国第一主義」や反リベラリズムは、ミドルパワーとしてリベラル国際秩序への貢献を自負してきた豪州の価値観と、あらゆる意味で相容れないものであった。トランプ政権の誕生後、豪州の中で米国の保護を想定しない独自の路線を意味する「プランB」が盛んに議論されたのは、必ずしも安全保障の理由だけではなかろう。米国で国際主義や自由主義的価値観を否定する大統領が初めて誕生したことにより、「価値同盟」としての米豪同盟の基盤が失われることへの恐れが、豪州における「トランプ・ショック」の根底にあったのである。
活路としてのインド太平洋
インド太平洋という地域概念は、上記で述べた豪州が抱える戦略的なジレンマを解消する手段としての側面を持っていた。そこでの一つのキーワードは、「多極化」である。トランプ政権の誕生後に発表された豪州の外交白書は、2030年までに中国が米国を抜いて世界第一位の経済大国になるという見通しを示しつつ、同時にインドやインドネシア等の新興国の台頭により、2030年代に向けて世界が多極化していくとの見通しを示した。さらに米国やEU、そして日本もそうした多極化された世界の重要なプレイヤーであり、それらの国々との「インド太平洋パートナーシップ」を強化していくという方針が示されていたのである。
そうしたパートナーシップの強化が、中国の台頭を念頭に置いたものであることは論を俟たない。しかしながら、それは必ずしも対中「封じ込め」を意味するものではない。外交白書が作成された時期に外務次官を務め、引退後も活発な言論活動を続けているピーター・バギースによれば、それは対中「封じ込め」というよりも、中国の台頭を「管理」する手段である。豪州が米国やインド、そして日本といった国々と共に中国に対する「戦略的均衡(strategic equilibrium)」を形成することで、中国の覇権主義的な野心や冒険主義的な行動を抑制し、「ルールに基づく秩序」へと導くことが可能となる。そうした地域における安定的な均衡体制があって初めて、豪州は中国とも貿易を含めた良好な関係を維持することが可能となると考えられているのである。
日米豪印(QUAD)や豪英米の安全保障協力(AUKUS)は、そうしたインド太平洋秩序を実現する上で鍵を握る枠組みとして捉えられている。よく知られている通り、2007年に日本の安倍政権がQUADを提唱した際、豪州はそれに参加しないという決断を下した。ところがその後、南シナ海や南太平洋等で中国の拡張主義的な行動が強まったことにより、豪州ではQUADに対する超党派的な支持が形成されるに至った。さらに2020年初頭から広まったコロナ感染症をきっかけに豪中間で対立が深まると、翌年9月に豪州は米英とAUKUSを結成し、両国との協力のもと原子力潜水艦を取得するとの発表を行い、世界を驚かせた。
QUADは目下のところ軍事的な協力ではないが、経済安保や環境政策といった非軍事的な分野での協力より、中国に対する戦略的な優位性の確保を目指したものである。QUADはまた、「戦略的自律性」を掲げるインドを西側諸国に引き付けるという意味でも、重要な使命を持っている。これに対しAUKUSは豪州に対する原子力潜水艦の供与に加え、新興技術開発における協力という役割を持つ。特に豪英米が防衛産業基盤の強化や一体化を通じて武器・装備品のより効率的な開発や技術革新を目指すことにより、この分野においても優位に立とうとしている中国に対するカウンター・バランスとなることが期待されている。だからこそ豪州は、AUKUSを「国家的事業」として捉え、その実現に向けた国を挙げた取り組みを強化しているのである。
ミドルパワー外交からの決別
このように、豪州にとってのインド太平洋とはある種の多極的な秩序であり、そこにおける「戦略的均衡」を維持することが、地域の安定化に不可欠な要素として捉えられている。だからこそ豪州は、QUADやAUKUSといった協力を推進するとともに、戦後類を見ないペースで国防力の強化を進めているのである。原子力潜水艦の取得という「ハイリスク・ハイリターン」の決断を下し、そのために国を挙げた体制を敷いているのは、そうした豪州の並々ならぬ決意の表れであった。
2023年4月に発表された豪州の「戦略防衛見直し」は、米国の「一極体制」が終焉したとの見通しのもと、豪州の国防路線をそれまでの低強度紛争への対応に焦点を置いた「豪州の防衛」路線から、より強度の高い紛争への対処を目的とした「国家防衛」路線に転換することを提言した。そこでは、これまでの陸海空の均衡の取れた国防力から、海空領域における長距離打撃能力や新領域といった非対称能力の強化に資源を集中することで、中国の脅威に対抗するという構想が描かれていた。
これは、言ってみれば豪州が戦後初めて、中国の軍事力と(非対称ではあるが)直接対峙できるだけの能力を構築する決断を下したということでもある。米国の圧倒的な優位(プライマシー)が続く限りにおいて、中国の戦略的な影響力が豪州にまで及ぶことなど考えられなかった。そこにおいて豪州がすべきこととは、グローバルなテロとの戦いや地域の平和維持活動といった相対的に非論争的な分野で同盟に貢献することで、米国の覇権秩序を側面から支え、同時に中国との良好な関係を維持することであった。そうした状況において、豪州が他国との本格的な紛争事態に関与する可能性は、限りなく低く見積もられていたのである。ところが、中国の軍事的な能力が米国のプライマシーを破る可能性が生まれたことで、豪州は米国との緊密な同盟を維持しながらも、同時により自主的な国防力の強化を急ピッチで図っているのである。
それはまた、戦後の豪州の外交安全保障路線の重大な転換を意味していた。特に70年代以降の豪州は、いわゆる「中級国家(ミドルパワー)」として平和維持活動や多国間外交、そして核軍縮・不拡散といった大国があまり関与しない「ニッチ」な分野における活動に力を入れてきた。豪州はまた、大国間の権力政治からは一定の距離を置き、自由貿易や民主主義、人権といった価値規範に重きをおく「良き国際市民」としてのアイデンティティを強調してきた。それは、「ダウン・アンダー」と呼ばれる南半球の最果てに位置し、自国の力だけではその広大な国土を守ることすら困難な豪州が、自国のプレゼンスを国際社会において最大限発揮するための一つの知恵であり、「生き様」でもあった。
豪州は今、そうした戦後の「生き様」と決別し、地域の「戦略的均衡」に影響を与えうる主要なプレイヤーとしての立ち位置を確立しようとしている。豪州がいわば「国是」として追求してきた核軍縮や核不拡散の流れに逆行するとの批判を受ける恐れがありながら、それでも原潜の導入を決めたのは、そうした豪州の方針転換を象徴する出来事であった。またかつて一旦は不参加を表明したQUADの枠組みに超党派のコミットメントを示しているのも、そうした豪州のインド太平洋にかける並々ならぬ決意の表れとして受け止めることができよう。
インド太平洋の理想と現実
問題は、地域の戦略的均衡の維持に寄与するという豪州の目標が、果たしてどこまで現実的なのかということだ。確かに豪州は、移民の増加や資源輸出を中心とした輸出指向型の経済により、近年まで先進国としては稀に見る好調な経済成長を維持してきた。また日本や韓国といった高齢化に苦しむ地域の先進民主主義国家と比べれば、豪州の財政状況は健全である。加えて、ウクライナ戦争の影響によって世界的なエネルギー価格の高騰が進む中で、資源大国である豪州のプレゼンスは一層高まっている。原潜の導入をはじめとした急速な国防力の強化や国防費の増額を進める背景には、こうした豪州の経済に対する一定の自信が垣間見える。
その一方で、不動産価格をはじめとしたインフレや豪ドル安の進行等により、豪州経済の先行きの見通しは必ずしも明るいとは言えない。また日本や韓国ほどではないにせよ、高齢化の進行は一定程度豪州の経済にも影を及ぼしている。2023年に政府が発表した豪州経済の長期的な見通しに関する報告書は、少子高齢化や生産年齢人口の減少により、今後40年間の経済成長率は過去40年間のそれと比べ0.9%低下するとの見通しを示した。これに対し豪州の国防費は膨らむ一方であり、他の支出に対する影響が及ぶことは避けられない状況になっている。
だが、問題は財政面だけではない。長らく本格的な紛争事態を想定しない装備体系を維持してきた豪州軍は、中国の脅威に対峙するにはあまりにも心細い戦力となっている。現行の「コリンズ」級潜水艦はすでに老朽化が進み、故障や修繕等で満足に稼働できないこともある。また水上艦の主力となる「アンザック」級フリゲート艦も、艦船の乗組員不足等によって稼働率が低下している。さらにその後継として期待されていた英BAE社の「ハンター」級フリゲート艦は様々な問題から調達が遅れ、2024年2月に国防省が発表した新たな水上艦見直しの報告書では、その調達数を9隻から6隻に減らすことが提言されていた。その一方で、報告書は11隻の新たなフリゲート艦の導入により、2040年代までに豪州の戦闘艦を倍増することを提言しているが、艦船の建造や維持に携わる労働力が不足している状況で、その計画の実現性を危ぶむ声も多い。
加えて、AUKUSを通じた原潜の取得についても、多くの課題が指摘されている。例えば、豪州では原潜の建造や維持等に必要となる民間の労働力の数が、現状では圧倒的に不足している。また民間の労働力の供給不足は、豪州軍の人員不足という問題にも波及しており、特に上で挙げた艦船や潜水艦の乗組員不足という問題が既に表面化している。さらに、原潜の維持費や運用コストを含めると総額2680億〜3680億豪ドル(日本円で約26兆〜36兆)にも上るとも言われる巨額のコストとその費用対効果については、疑問の声も少なくない。2023年5月にはAUKUSに批判的な議員や元議員、元軍人、専門家等による公開レターが豪州の主要紙に掲載され、AUKUS決定の背景や予算コスト、計画期間等について政府側の回答を求めた。
原潜の調達に向けたリスクは、2024年11月に予定されている米国大統領選で共和党のトランプ候補が勝利した場合、さらに高まることになるであろう。そもそも共和党は自国の原潜製造ラインの維持という観点から、豪州への原潜の供与を渋っていた。2023年12月に可決された国防授権法は、豪州へのヴァージニア級原潜3隻の供与を原則として認めたものの、あくまで原潜の供与が米国の能力を損なわず、またその外交政策や国益とも合致するものであることを大統領が証明するという条件が付けられている。「米国第一主義」を掲げるトランプ候補が、こうした条件を呑んでまで豪州に原潜を供与するという決断を下すためには、豪州政府による相当な働きかけが必要となるであろう。
それでは、もう一つの頼みの綱であるインドはどうであろうか。豪州は2010年代半ばからインドとの安全保障関係を強化し、軍の後方支援協定や防衛科学技術協定も結んでいる。また経済的にも、中国に代わる市場としてのインドを高く評価し、暫定的な自由貿易協定となる経済協力貿易協定(ECTA)の締結を含めて幅広い関係を強化している。2023年5月にモディ首相がインドの首相としてはおよそ9年ぶりに豪州を訪問した際、豪州が国を挙げてこれを歓迎し、大きな盛り上がりを見せたことは記憶に新しい。同年8月には、米印の演習として始まり、その後日本、そして豪州が加わり4カ国の演習となった軍事演習「マラバール」が初めて豪州で開催された。
その一方で、インドは同年末に開催された米豪の合同演習への招待を拒否し、またマラバールをQUADの協力とは切り離すことを求めるなど、日米豪との軍事的な協力の進展には慎重な姿勢を崩してはいない。またインドとロシアの伝統的な関係は、特に新興技術面における他のQUAD諸国との軍事関係の強化を困難なものとしている。経済的にも、ECTAの締結後インドから豪州への輸出は上昇したものの、豪州からの輸出は必ずしも伸びていない。特に豪州が力を入れるインドへの石炭輸出は、中国による制裁の影響もあって2022年に増加したものの、中国の制裁が緩和された2023年には再び元のレベルに戻った。インドと豪州の間にはまた、ウクライナ戦争やミャンマー軍事政権への対応、そして人権や民主主義、自由なデータの移動に対する考え方という点でも、隔たりがある。2023年11月に発覚したインド政府の関与が疑われる米国在住のシーク教徒の殺害計画は、米印関係やQUADの協力にも暗い影を及ぼしている。
おわりに
以上をまとめると、豪州にとってのインド太平洋とは、米中のみならずインドや日本、そして豪州を含む地域諸国を含む多極的な秩序を構築し、またそれぞれの国が中国に対して「戦略的均衡」を維持することによって、包摂的でルールに基づく秩序の維持と強化を図るという構想である。その意味で豪州にとってインド太平洋は単なる地域概念を超えた、「秩序構想」としての意味を持っていると筆者は考える。それはまた、安全保障は米国、経済は中国という大国にそれぞれ依存してきた豪州の戦略的ジレンマを解消する手段としての側面を持つものであり、それが故に近年豪州は、伝統的な「ミドルパワー外交」から決別し、国防力の増強や同盟国・友好国との関係強化、そしてQUADやAUKUSの強化を通じて、インド太平洋秩序の実現に向けた軍事的な取り組みを強化している。
もっとも現実は、必ずしも豪州の思うように進んでいない。豪州の国防力の強化は、予算不足や労働力不足、そしてスピード不足といった様々な課題に直面している。特に原潜の取得については、上記問題に加え米国の国内政治の動向により、懐疑論が強まりつつある。仮に豪州の国防力強化が成功し、豪州が「戦略的均衡」を形成するための意味あるプレイヤーになれたとしても、それは早くても2040年代以降の話であり、それまでの間に地域で紛争が起こる可能性は否定できない。こうした可能性は、特に中国に対して好戦的な姿勢を示すトランプ候補が大統領になった場合、より高まるであろう。さらにもう一つのキープレイヤーであり、「グローバル・サウス」の盟主を自負するインドが、米豪や日本と共に中国に対する「戦略的均衡」に全面的にコミットする保証もない。
果たして豪州は、中国に対する「戦略的均衡」の形成が挫折した場合の「プランB」を持っているのだろうか。かつてホワイトが唱えたアジアにおける大国間の協調は、豪州を含む中小国の利益を軽視しているという点で、豪州にとっても許容できるものではない。また2020年以降対中関係が極度に悪化し、さらに対中警戒感がかつてなく高まっている中において、中国に対して「宥和」を図るという選択肢も考えにくい。結局のところ豪州は、貿易やサプライチェーンの多角化を通じて徐々に中国への経済的な依存を減らしつつ、安全保障面においては米英という伝統的なパートナーへの依存を深めていく以外に道はない。これに対し中国は、ロシアや北朝鮮といった権威主義国家との連携を一層強化させることで、既存秩序への挑戦を強めていくことになろう。豪州の描くインド太平洋の理想と現実の間には、依然として大きな隔たりがある。そしてそうした隔たりは、時と共に大きなものとなっているようにも見えるのである。
執筆者プロフィール
佐竹 知彦(さたけ ともひこ)
青山学院大学 国際政治経済学部 国際政治学科 准教授
慶應義塾大学法学部、同大学大学院法学研究科修士課程、オーストラリア国立大学博士課程修了。Ph.D. (国際関係論)。2010年防衛研究所入所、2015年4月より同主任研究官、2023年4月より現職。2013年~2014年にかけて防衛省防衛政策局国際政策課部員として多国間の安全保障協力を担当。また2020年には外務省の第9回太平洋・島サミットに向けた有識者会合委員を務める。専門はアジア太平洋の国際関係、豪州の外交・安全保障政策。著書:『冷戦後の日豪安全保障協力―「距離の専制」を越えて』(単著、勁草書房、2022年)、『「防衛外交」とは何か』(共著、勁草書房、2021年)、『UP plusアフターコロナ時代の米中関係と世界秩序』(共著、東京大学出版会、2020年)、『冷戦後の東アジア秩序』(共著、勁草書房、2020年)等。

