
(10) 日本はデカップリングを早まるな

掲載日:2022年8月4日
東京大学 社会科学研究所 教授
丸川 知雄
中国への失望
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからはや5か月。いまも戦争が終わる兆しは見えない。侵攻が始まって以来、私にとっては失望させられること、意外なことの連続であった。
最大の失望はいうまでもなくロシアによる侵略そのものである。
もう一つの失望は、中国のウクライナ侵攻に対する反応である。私は、内政不干渉と主権の尊重が中国の外交の大原則なのだと思っていた。香港、台湾、新疆、チベットなどに関して他国から人権侵害などの問題を指摘されても、中国は内政不干渉の原則を盾として頑として聞き入れようとしない。であるのならば、中国はロシアに対しても武力侵攻によって他国に干渉するのは間違いである、と表明してスジを通してほしかった。
ところが、中国は武力侵攻に表立って反対を表明していない。結局、中国の内政不干渉、主権尊重の原則はご都合主義的なものだったのではないかと私は疑っている。つまり、自らと対立する国に対しては内政不干渉を求める一方、自国および自国と近しい国は他国の内政に干渉してもいいと思っているのではないか。中国の外交には特定の原則に基づく一貫性はなく、今後中国がアメリカと対抗していくうえで重要なパートナーとなるロシアの弱体化を防ぎたい、欧米が強くなりすぎるのを防ぎたい、という力の論理に依拠しているだけではないだろうか、という疑念が生じるのである。
また、中国が停戦に向けた働きかけに積極的に動こうとしていないことにも失望させられた。欧米各国がロシアに対する経済制裁を断行し、ウクライナに兵器を供与するなど半ば参戦してしまっている状況のなか、とりあえず中立を保ち、大きな経済力も持つ中国は、和平を仲介できるポジションにあるはずである。今後、アメリカと中国の国力が拮抗し、世界情勢の不安定化が危惧されるなか、中国が平和の回復に動くのではなく、むしろ力の論理に基づく動きを見せていることは将来への不安をかきたてる。
多国籍企業は制裁の主体であるべきか?
私にとって意外だったことは、欧米による経済制裁がロシア中央銀行のドル建て資産の凍結やロシアの銀行の国際銀行間通信協会(SWIFT)からの排除、半導体や工作機械の輸出禁止など政府がらみのものにとどまらず、多数の民間企業も自発的に制裁に同調したことである。アップル、フォード、エクソンモービル、ナイキなど多数の多国籍企業がロシアから撤退した。特にコカ・コーラやマクドナルドまでロシアから撤退したのには驚かされた。
半導体は兵器の部品になりうるし、工作機械は兵器の生産に使われるので、これらの輸出を停止するというのは理解できる。だが、コーラやハンバーガーが戦争に関係あるはずがない。なぜ撤退する必要があったのだろうか。
東西冷戦の時代、工作機械や半導体を自由主義陣営の国からソ連など東側の国々に輸出することは厳しく制限されていた。東芝の子会社、東芝機械がソ連に高性能の工作機械を不正に輸出したとしてアメリカで激しいバッシングにさらされたのは1987年のことである。だが、そうした時代にもアメリカからソ連へ小麦が大量に輸出されていた。小麦は兵器の生産に関係ないという理屈による。小麦がいいのであれば、コーラやハンバーガーをロシア人に販売することだってかまわないはずである。
ロシアに対する制裁強化を主張する人の中には、ロシアに設立された現地法人は、ロシア政府に納税するのだから間接的にロシアの戦争をサポートしていることになる、だから撤退すべきなのだ、といった議論をする人もいる。たしかに現地法人がロシアで利益を上げれば、その一部は税金としてロシア政府に納めることになるが、税引き後利益は出資者である親会社への配当として本国に還元される。だから、現地法人が利益を上げることは親会社の本国の税収増にもつながっているのであり、ロシア政府ばかりに利益をもたらしているわけではない。
仮に現地法人が設置されている国とその親会社が設置されている国が国際紛争をめぐって対立した時、現地法人がどちらの国の立場に立つべきかは自明のことではない。現地法人が親会社の国の手先だと見なされることは、多国籍企業にとってむしろ事業の障害となる。かみ砕いていうと、ロシアにある日本企業の現地法人は日本の手先としてふるまうべきではないし、日本の手先だとみなされることはロシアでのビジネスの支障となる。
ロシアに設置された現地法人は、当然ながらロシアの法律に従わなければならないし、ロシアでの納税の義務も負うし、従業員の大半もロシア人であろうし、CSR(企業の社会的責任)活動もロシアで行うべきであろう。ところが、今般のウクライナ戦争では欧米の多くの企業が侵略に抗議するとしてロシアから撤退する決定をした。つまり、親会社が本国の政治的立場に同調したことによって現地法人も親会社の方針に従った。ロシアが「多国籍企業」だと思って投資を受け入れたら、実はアメリカ政府に忠実な「アメリカ企業」だったというわけである。
このことは、これまで自国の発展に役立つとして多国籍企業の直接投資を受け入れてきた他の発展途上国を不安に陥れるであろう。もし自国とアメリカが対立するようなことになった場合、米系多国籍企業の現地法人はアメリカの手先として動き、自国にダメージを与えるかもしれないのである。そうなると今までのように多国籍企業を手放しで歓迎することはできなくなる。
そう考えると、日本企業が欧米企業に比べてロシアからの撤退に及び腰なのはむしろ正解である。少なくとも日系多国籍企業の現地法人は日本の手先ではないことになるからである。帝国データバンクによれば、ロシアに進出している日本の上場企業は168社で、うち74社はロシア事業の停止または撤退を表明しているが、その多くは物流の混乱などを理由に生産や販売を停止しているだけで、撤退したのは5社にすぎない。イギリス企業の場合は46%、アメリカ企業は27%が撤退したのに対して日本企業の撤退率は5%にとどまるという(『時事ドットコム』2022年7月27日)。
「デカップリング」を早まるな
中国はこれまでのところロシアの侵略を止めようとしていないが、軍事的に加勢してもいない。だが、今後仮に戦局がウクライナ有利に展開し、ロシアが追いつめられるような場面が到来したら、中国が本格的なロシア支援に乗り出す可能性が高まる。そうなれば欧米や日本の経済制裁の対象に中国も加わることになり、日本企業の中国ビジネスも大きな影響を受けよう。「中国とのデカップリング」がいよいよ現実のものとなるかもしれない。
しかし、日本と中国の経済関係は、日本とロシアの経済関係に比べてはるかに広くて深い。日系企業の現地法人の数もロシアが129社であるのに対して中国本土は6303社と桁違いに多い(経済産業省『海外事業活動基本調査』2020年)。日本の中国との貿易の途絶や、日本企業の中国事業の停止は、中国にも一定のダメージを与えるが、それ以上に日本にダメージを与える。
2021年の中国のGDPは日本の3.4倍になった。中国の対外貿易額は日本の4倍である。この単純な事実からして日本と中国の経済関係が途絶した時にどちらがより大きなダメージを受けるかは自明であるが、中国の経済規模が日本の4分の1、5分の1でしかなかった前世紀の記憶をいまだ引きずっている人たちはどうもそのことが分かっていないようである。
2000年まで日本は中国の対外貿易の2-3割を常に占めており、中国は鉄鋼、化学肥料、機械などを日本からの輸入に頼っていた。だが、貿易における日中の依存関係は2005年あたりに逆転し、むしろ日本が中国に依存する関係になっている。
図1では中国の輸入額に占める日本とアメリカの割合を示しているが、2016年から2022年という短い期間にも日本の割合は9.2%から6.9%に低下している。意図的かはともかくとして、中国の「脱日本化」がますます進んでいるのである。
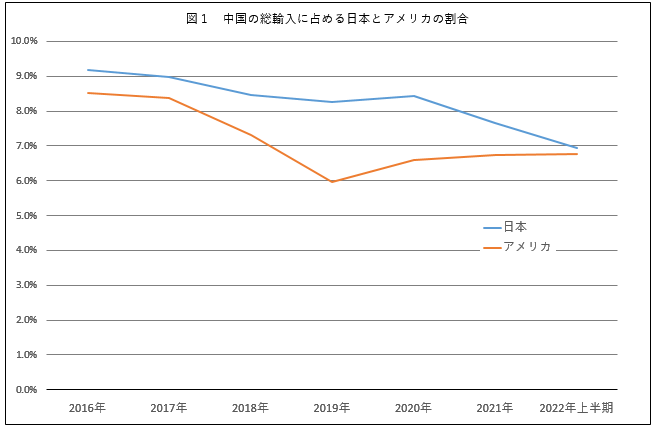
一方、アメリカの割合は、トランプ政権時代の2018年7月から米中が相互に関税を上乗せしあう米中貿易戦争が始まったことから2019年に大きく落ち込んだが、それ以降はむしろ上昇し、近く日本を抜きそうな勢いである。つまり、中国から見れば日本とは「デカップリング」、アメリカとは「リカップリング」していることになる。
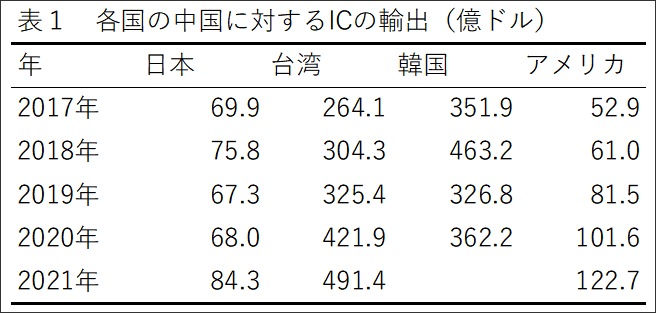
トランプ政権時代から中国とアメリカの「デカップリング」を代表する例としてしばしばマスコミで取り上げられてきたのがICである。中国は2015年の「中国製造2025」のなかでICを重点分野の一つに挙げ、ICの国産化に努めてきた。一方、アメリカは中国のICメーカー、SMICに対する設備輸出をブロックすることで中国のIC国産化の野望を妨害してきた。また、アメリカは中国の通信設備大手、ファーウェイを危険な企業だとみなし、アメリカからのICやソフトウェアをファーウェイに輸出する場合には商務省の許可が必要だとした。2020年からはその規制を、アメリカの技術やソフトを使う外国企業にまで広げ、日本の企業もファーウェイにICなどを輸出する場合にはアメリカ商務省に許可を願い出なければならないことになった。こうした規制強化により、日本やアメリカから中国へのIC輸出は減っていると思われるかもしれない。
ところが、表1にみるように、アメリカから中国へのIC輸出は2017年から21年の間に2.3倍に急増している。台湾から中国へのIC輸出も大幅に伸びている。一方、日本から中国へのIC輸出も伸びてはいるものの、わずか20%の増加にとどまり、アメリカに抜かれてしまった。この数字を見ると、ICにおける「デカップリング」は現実には起きておらず、むしろ日本が「デカップリングさせられている」のではないかという疑惑も生じてくる。「アメリカの裏切り」という言葉さえ浮かんでくる現実がここにある。
日本企業が「中国とのデカップリング近づく」という見方に恐れおののいて中国ビジネスの展開を躊躇しているうちにアメリカや台湾の企業にビジネスチャンスをさらわれているのではないだろうか。だが、幸か不幸かまだ中国は経済制裁の対象とはなっておらず、中国ビジネスを諦めざるを得ないような場面ではない。デカップリングせざるをえなくなる局面を想定しておく必要はあるだろうが、必要もないのにデカップリングして自らの首を絞めることは避けたいものだ。
執筆者プロフィール
丸川 知雄 (まるかわ ともお)
東京大学 社会科学研究所 教授
東京大学経済学部卒、アジア経済研究所を経て、2001年4月より東京大学社会科学研究所勤務。専門は中国経済・産業経済。
著書:『現代中国経済・新版』(有斐閣、2021年)、『タバコ産業の政治経済学』(共著、昭和堂、2021年)、『中国・新興国ネクサス』(共編著、東京大学出版会、2018年)、『チャイニーズ・ドリーム』(筑摩書房、2013年)、『携帯電話産業の進化プロセス』(共編著、有斐閣、2010年)、『現代中国の産業』(中央公論新社、2007年)他。
東京大学 社会科学研究所 教授
丸川 知雄
中国への失望
ロシアによるウクライナ侵攻が始まってからはや5か月。いまも戦争が終わる兆しは見えない。侵攻が始まって以来、私にとっては失望させられること、意外なことの連続であった。
最大の失望はいうまでもなくロシアによる侵略そのものである。
もう一つの失望は、中国のウクライナ侵攻に対する反応である。私は、内政不干渉と主権の尊重が中国の外交の大原則なのだと思っていた。香港、台湾、新疆、チベットなどに関して他国から人権侵害などの問題を指摘されても、中国は内政不干渉の原則を盾として頑として聞き入れようとしない。であるのならば、中国はロシアに対しても武力侵攻によって他国に干渉するのは間違いである、と表明してスジを通してほしかった。
ところが、中国は武力侵攻に表立って反対を表明していない。結局、中国の内政不干渉、主権尊重の原則はご都合主義的なものだったのではないかと私は疑っている。つまり、自らと対立する国に対しては内政不干渉を求める一方、自国および自国と近しい国は他国の内政に干渉してもいいと思っているのではないか。中国の外交には特定の原則に基づく一貫性はなく、今後中国がアメリカと対抗していくうえで重要なパートナーとなるロシアの弱体化を防ぎたい、欧米が強くなりすぎるのを防ぎたい、という力の論理に依拠しているだけではないだろうか、という疑念が生じるのである。
また、中国が停戦に向けた働きかけに積極的に動こうとしていないことにも失望させられた。欧米各国がロシアに対する経済制裁を断行し、ウクライナに兵器を供与するなど半ば参戦してしまっている状況のなか、とりあえず中立を保ち、大きな経済力も持つ中国は、和平を仲介できるポジションにあるはずである。今後、アメリカと中国の国力が拮抗し、世界情勢の不安定化が危惧されるなか、中国が平和の回復に動くのではなく、むしろ力の論理に基づく動きを見せていることは将来への不安をかきたてる。
多国籍企業は制裁の主体であるべきか?
私にとって意外だったことは、欧米による経済制裁がロシア中央銀行のドル建て資産の凍結やロシアの銀行の国際銀行間通信協会(SWIFT)からの排除、半導体や工作機械の輸出禁止など政府がらみのものにとどまらず、多数の民間企業も自発的に制裁に同調したことである。アップル、フォード、エクソンモービル、ナイキなど多数の多国籍企業がロシアから撤退した。特にコカ・コーラやマクドナルドまでロシアから撤退したのには驚かされた。
半導体は兵器の部品になりうるし、工作機械は兵器の生産に使われるので、これらの輸出を停止するというのは理解できる。だが、コーラやハンバーガーが戦争に関係あるはずがない。なぜ撤退する必要があったのだろうか。
東西冷戦の時代、工作機械や半導体を自由主義陣営の国からソ連など東側の国々に輸出することは厳しく制限されていた。東芝の子会社、東芝機械がソ連に高性能の工作機械を不正に輸出したとしてアメリカで激しいバッシングにさらされたのは1987年のことである。だが、そうした時代にもアメリカからソ連へ小麦が大量に輸出されていた。小麦は兵器の生産に関係ないという理屈による。小麦がいいのであれば、コーラやハンバーガーをロシア人に販売することだってかまわないはずである。
ロシアに対する制裁強化を主張する人の中には、ロシアに設立された現地法人は、ロシア政府に納税するのだから間接的にロシアの戦争をサポートしていることになる、だから撤退すべきなのだ、といった議論をする人もいる。たしかに現地法人がロシアで利益を上げれば、その一部は税金としてロシア政府に納めることになるが、税引き後利益は出資者である親会社への配当として本国に還元される。だから、現地法人が利益を上げることは親会社の本国の税収増にもつながっているのであり、ロシア政府ばかりに利益をもたらしているわけではない。
仮に現地法人が設置されている国とその親会社が設置されている国が国際紛争をめぐって対立した時、現地法人がどちらの国の立場に立つべきかは自明のことではない。現地法人が親会社の国の手先だと見なされることは、多国籍企業にとってむしろ事業の障害となる。かみ砕いていうと、ロシアにある日本企業の現地法人は日本の手先としてふるまうべきではないし、日本の手先だとみなされることはロシアでのビジネスの支障となる。
ロシアに設置された現地法人は、当然ながらロシアの法律に従わなければならないし、ロシアでの納税の義務も負うし、従業員の大半もロシア人であろうし、CSR(企業の社会的責任)活動もロシアで行うべきであろう。ところが、今般のウクライナ戦争では欧米の多くの企業が侵略に抗議するとしてロシアから撤退する決定をした。つまり、親会社が本国の政治的立場に同調したことによって現地法人も親会社の方針に従った。ロシアが「多国籍企業」だと思って投資を受け入れたら、実はアメリカ政府に忠実な「アメリカ企業」だったというわけである。
このことは、これまで自国の発展に役立つとして多国籍企業の直接投資を受け入れてきた他の発展途上国を不安に陥れるであろう。もし自国とアメリカが対立するようなことになった場合、米系多国籍企業の現地法人はアメリカの手先として動き、自国にダメージを与えるかもしれないのである。そうなると今までのように多国籍企業を手放しで歓迎することはできなくなる。
そう考えると、日本企業が欧米企業に比べてロシアからの撤退に及び腰なのはむしろ正解である。少なくとも日系多国籍企業の現地法人は日本の手先ではないことになるからである。帝国データバンクによれば、ロシアに進出している日本の上場企業は168社で、うち74社はロシア事業の停止または撤退を表明しているが、その多くは物流の混乱などを理由に生産や販売を停止しているだけで、撤退したのは5社にすぎない。イギリス企業の場合は46%、アメリカ企業は27%が撤退したのに対して日本企業の撤退率は5%にとどまるという(『時事ドットコム』2022年7月27日)。
「デカップリング」を早まるな
中国はこれまでのところロシアの侵略を止めようとしていないが、軍事的に加勢してもいない。だが、今後仮に戦局がウクライナ有利に展開し、ロシアが追いつめられるような場面が到来したら、中国が本格的なロシア支援に乗り出す可能性が高まる。そうなれば欧米や日本の経済制裁の対象に中国も加わることになり、日本企業の中国ビジネスも大きな影響を受けよう。「中国とのデカップリング」がいよいよ現実のものとなるかもしれない。
しかし、日本と中国の経済関係は、日本とロシアの経済関係に比べてはるかに広くて深い。日系企業の現地法人の数もロシアが129社であるのに対して中国本土は6303社と桁違いに多い(経済産業省『海外事業活動基本調査』2020年)。日本の中国との貿易の途絶や、日本企業の中国事業の停止は、中国にも一定のダメージを与えるが、それ以上に日本にダメージを与える。
2021年の中国のGDPは日本の3.4倍になった。中国の対外貿易額は日本の4倍である。この単純な事実からして日本と中国の経済関係が途絶した時にどちらがより大きなダメージを受けるかは自明であるが、中国の経済規模が日本の4分の1、5分の1でしかなかった前世紀の記憶をいまだ引きずっている人たちはどうもそのことが分かっていないようである。
2000年まで日本は中国の対外貿易の2-3割を常に占めており、中国は鉄鋼、化学肥料、機械などを日本からの輸入に頼っていた。だが、貿易における日中の依存関係は2005年あたりに逆転し、むしろ日本が中国に依存する関係になっている。
図1では中国の輸入額に占める日本とアメリカの割合を示しているが、2016年から2022年という短い期間にも日本の割合は9.2%から6.9%に低下している。意図的かはともかくとして、中国の「脱日本化」がますます進んでいるのである。
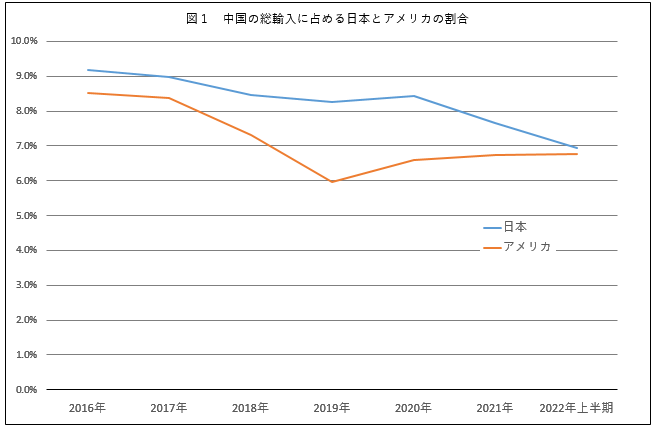
一方、アメリカの割合は、トランプ政権時代の2018年7月から米中が相互に関税を上乗せしあう米中貿易戦争が始まったことから2019年に大きく落ち込んだが、それ以降はむしろ上昇し、近く日本を抜きそうな勢いである。つまり、中国から見れば日本とは「デカップリング」、アメリカとは「リカップリング」していることになる。
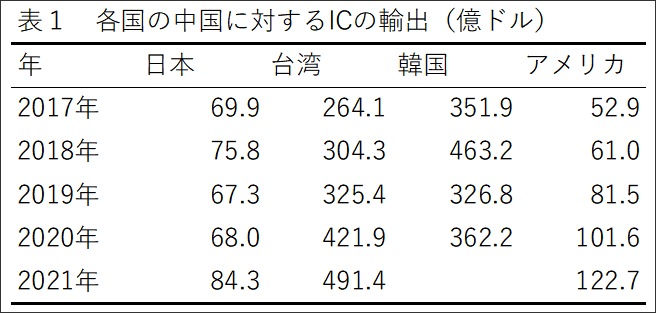
トランプ政権時代から中国とアメリカの「デカップリング」を代表する例としてしばしばマスコミで取り上げられてきたのがICである。中国は2015年の「中国製造2025」のなかでICを重点分野の一つに挙げ、ICの国産化に努めてきた。一方、アメリカは中国のICメーカー、SMICに対する設備輸出をブロックすることで中国のIC国産化の野望を妨害してきた。また、アメリカは中国の通信設備大手、ファーウェイを危険な企業だとみなし、アメリカからのICやソフトウェアをファーウェイに輸出する場合には商務省の許可が必要だとした。2020年からはその規制を、アメリカの技術やソフトを使う外国企業にまで広げ、日本の企業もファーウェイにICなどを輸出する場合にはアメリカ商務省に許可を願い出なければならないことになった。こうした規制強化により、日本やアメリカから中国へのIC輸出は減っていると思われるかもしれない。
ところが、表1にみるように、アメリカから中国へのIC輸出は2017年から21年の間に2.3倍に急増している。台湾から中国へのIC輸出も大幅に伸びている。一方、日本から中国へのIC輸出も伸びてはいるものの、わずか20%の増加にとどまり、アメリカに抜かれてしまった。この数字を見ると、ICにおける「デカップリング」は現実には起きておらず、むしろ日本が「デカップリングさせられている」のではないかという疑惑も生じてくる。「アメリカの裏切り」という言葉さえ浮かんでくる現実がここにある。
日本企業が「中国とのデカップリング近づく」という見方に恐れおののいて中国ビジネスの展開を躊躇しているうちにアメリカや台湾の企業にビジネスチャンスをさらわれているのではないだろうか。だが、幸か不幸かまだ中国は経済制裁の対象とはなっておらず、中国ビジネスを諦めざるを得ないような場面ではない。デカップリングせざるをえなくなる局面を想定しておく必要はあるだろうが、必要もないのにデカップリングして自らの首を絞めることは避けたいものだ。
執筆者プロフィール
丸川 知雄 (まるかわ ともお)
東京大学 社会科学研究所 教授
東京大学経済学部卒、アジア経済研究所を経て、2001年4月より東京大学社会科学研究所勤務。専門は中国経済・産業経済。
著書:『現代中国経済・新版』(有斐閣、2021年)、『タバコ産業の政治経済学』(共著、昭和堂、2021年)、『中国・新興国ネクサス』(共編著、東京大学出版会、2018年)、『チャイニーズ・ドリーム』(筑摩書房、2013年)、『携帯電話産業の進化プロセス』(共編著、有斐閣、2010年)、『現代中国の産業』(中央公論新社、2007年)他。

