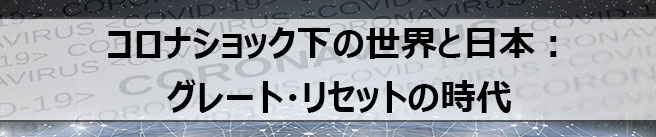
(21) 日本企業のサプライチェーン見直しの現状について考える

掲載日:2021年10月19日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 チーフエコノミスト
李 智雄
新型コロナウイルス禍で見直しの議論が進んだサプライチェーン
新型コロナウイルスのみならず、貿易摩擦や、震災などが、なぜ日本をはじめとした様々な国のグローバルサプライチェーンに決定的な変化を与えていないのか、に関して考えてみたい。
新型コロナウイルスが世界経済に大きな影響を与える以前より、グローバルサプライチェーンを巡る各国の問題意識は高まっていた。ジャーナリストのトーマス・フリードマンが2005年に用いた「フラット化する世界(The World is Flat)」という言葉が、実際に世界が「フラット化」したかどうかの議論はさておき、世界中の企業、投資家に対して世界がグローバル化している、という印象を説得的に与えたことは記憶に新しい。
しかしグローバリゼーションに対する期待の時代は長続きしなかった。二つの象徴的なデータがある。一つは世界経済成長率である。2008年のグローバル金融危機前までの10年間(1998~2007年)、世界の実質GDP成長率は年平均4.2%増であった。だが、2007年の5.5%増をピークにその後は、同成長率を上回る伸び率は確認できていない。具体的にはグローバル金融危機を経た(よって金融危機中の2008~2009年の成長率は除く)世界の経済成長率は2010~19年までで年平均3.7%増へと低下している(図表1)。
もう一つはWTOにおけるアンチ・ダンピング関税措置の新規調査開始件数である。グローバリゼーションの進展を受け、2001年の372件から徐々に低下してきたが、2007年に165件とボトムとなったあと、その後は振れを伴いつつも上昇傾向が続き、2020年は349件まで上昇した(図表2)。
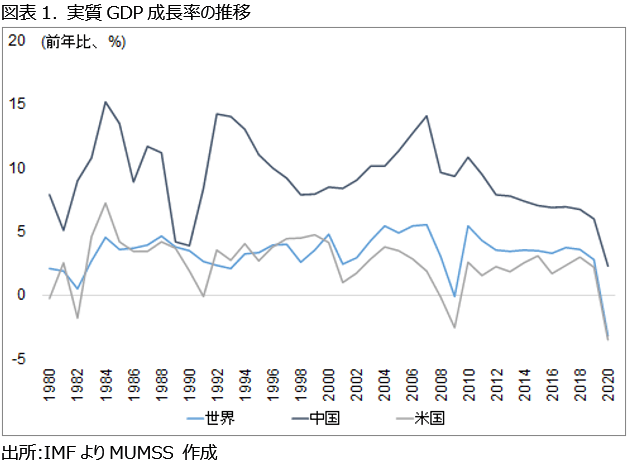
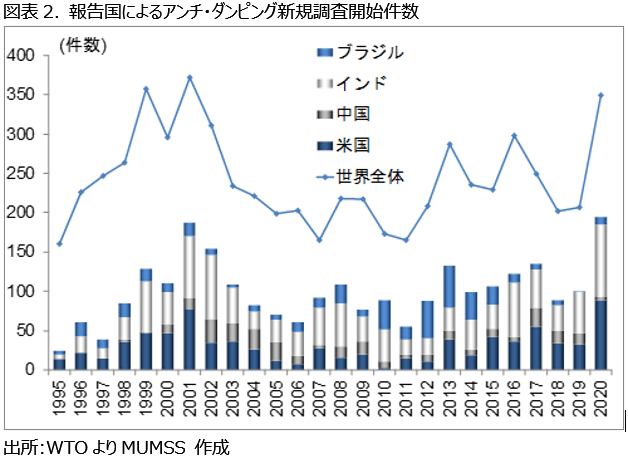
何が起こっているのか。背景には、経済成長率低下に伴う保護主義の復活がある。象徴的には、米中の貿易摩擦やBREXIT(2017年3月29日に通知された英国のEU離脱)が挙げられよう。
特に米中の対立は、関税のみならず、様々な分野の貿易に関する規制にまで及んでおり、両国ともに1、2位の貿易相手国となっている日本は勿論のこと、様々な国に対して、サプライチェーンの在り方の再考を迫ってきた。
そこに発生したのが新型コロナウイルスの問題である。新型コロナ禍によるサプライチェーンの分断は、身近な医療用品を含め、各国政府に対応を促す大きな契機となった。
例えば日本政府は2020年4月に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、国内回帰や多元化を通じた強固なサプライチェーンの構築を支援することを決定している(1次採択で3,060億円、2次採択で2,108億円の予算)。
サプライチェーン見直しの議論は実際のアクションにつながっているのか
それでは、同対策の国内回帰等への補助によって、国内への生産回帰は進んできたのだろうか。
国際協力銀行による「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告(2020年度海外直接投資アンケート調査結果(第32回))」によれば、新型コロナウイルスを受けた「海外投資計画の見直し」について聞かれた企業のうち、56.3%が「変更はない」と答えている。「製品・事業別の配分を見直す」(15.8%)、「投資計画を一時凍結する」(14.3%)などとある一方で、「国内投資に切り替える」はわずか2.0%に過ぎない(図表3)。
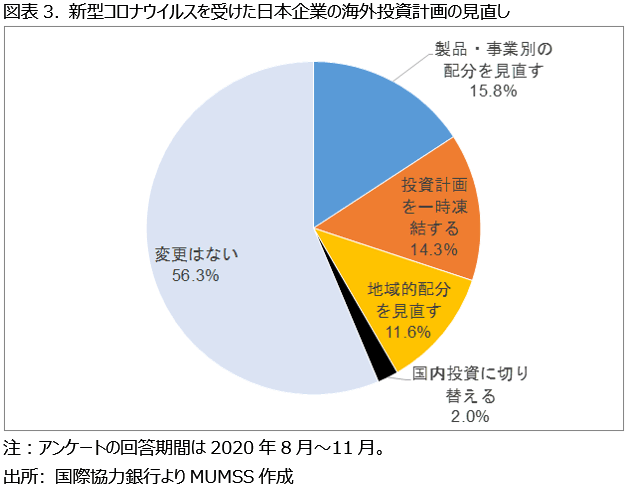
同時に、新型コロナウイルスを受け、海外投資計画の「地域的配分を見直す」という会社の割合は11.6%と一定割合存在する。
結果、中国からの生産拠点の移動が一部生じることは間違いなさそうだ。これまでも、中国からの生産拠点の移転の必要性は何度も話題になってきた。2010年前後の中国国内における過剰労働力の枯渇による賃金の上昇(いわゆる「ルイスの転換点(期間)」)の議論に加え、2016年前後の環境規制強化(それ以前から環境規制はあったが、2015年10月中国国務院弁公庁は「環境保護監査法案(試行)」を公布、その後処罰件数が大幅増加)、2018年以降の米中関税引き上げなど、その度に安価な「世界の工場」としての中国の地位は疑問視されてきた(図表4)。
また、日本政策投資銀行(DBJ)の「全国設備投資計画調査(2021年6月調査)」のうち、「企業行動に関する意識調査」を見てみると、「サプライチェーン見直しの契機(全産業、大企業)」は、「新型コロナウイルス」が58%とトップだが、「自社固有の事情などその他」23%を除けば、次に「米中対立の激化」が23%、「人件費の高騰」が16%と続くことから、新型コロナウイルスだけがサプライチェーン見直しの議論の背景にあったわけではないことがわかる。うち、「米中対立の激化」や「人件費の高騰」の影響を受けたのが中国であることは想像に難くない(図表5)。
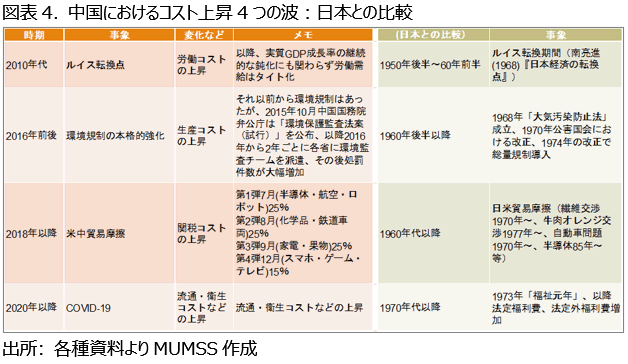
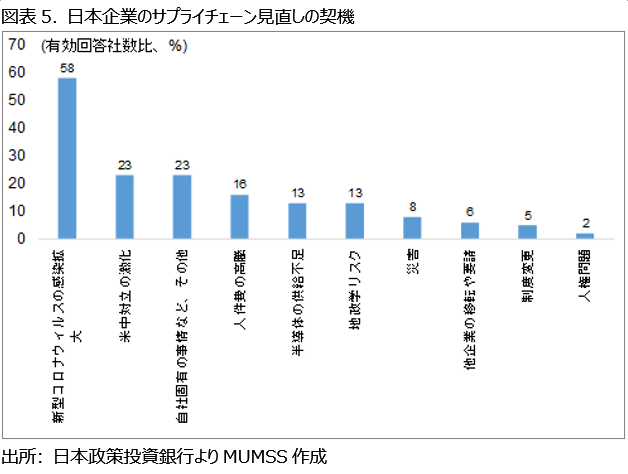
その結果、実際に日本企業の海外現地法人数のうち、中国の占める割合は2012年度の33.0%をピークに低下してきた(経済産業省、海外事業活動基本調査)。一方でASEANの比率は、2019年度まで拡大してきた。なお2020年度は新型コロナウイルスの早期収束に成功した中国の割合が再び拡大していることは注記しておこう(図表6)。
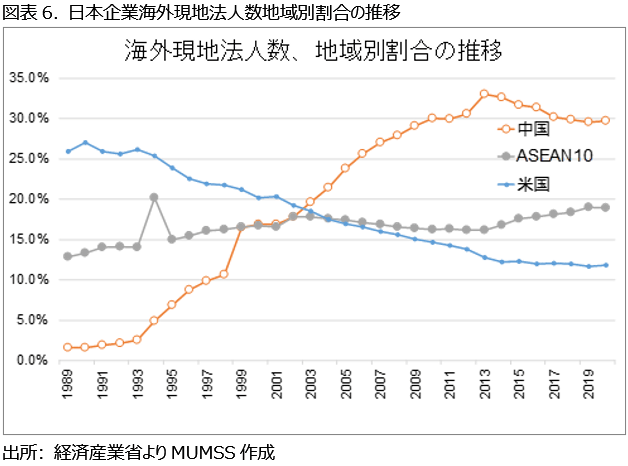
これを受けて、中国の製造業の空洞化は進み、弱体化していく、そう結論づけて良いのだろうか。そうではないと考えている。
中国から生産拠点を移動している企業の多くは、中国におけるコスト上昇(賃金や環境コスト、関税など)に耐えきれなくなったため、よりコストが低いASEAN諸国を選ばざるを得なくなった企業であろう。
日本から海外への生産拠点進出が進んだ1970年代を振り返る
ここで少し遠回りをして日本の経験を振り返ってみよう。1970年代の日本経済は、2010年代以降の中国経済に次の四つの点で類似している。
まず、(1)経済成長率の低下傾向(1960年代の年平均9.1%増から、1970年代は4.6%増へと鈍化)、次に(2)米国との対立激化(日米繊維交渉開始は1970年、第二次鉄鋼自主輸出規制は1972年より)、それから(3)賃金(労働コスト)の上昇(日本のルイスの転換点は1950年代後半から1960年代前半、南亮進(1968年))、そして(4)各種生産コストの上昇(環境規制強化、社会保障強化。例えば、1973年を田中角栄内閣は「福祉元年」と宣言)である(前掲図表4)。
これらは企業にとって、市場の魅力度の低下や企業活動に関わるコストの上昇となって意識されたはずだ。そのような日本で、製造業はどのような変遷を遂げたのか。
日本企業が海外への進出を積極化したことに加えて(経済産業省の海外事業活動基本調査の調査開始年は1971年である)、サービスを含めた非製造業の比率が上昇したことは周知の通りである。それではその結果、日本の製造業が空洞化し、弱体化したかと言えば、そうではなかった(図表7~8)。
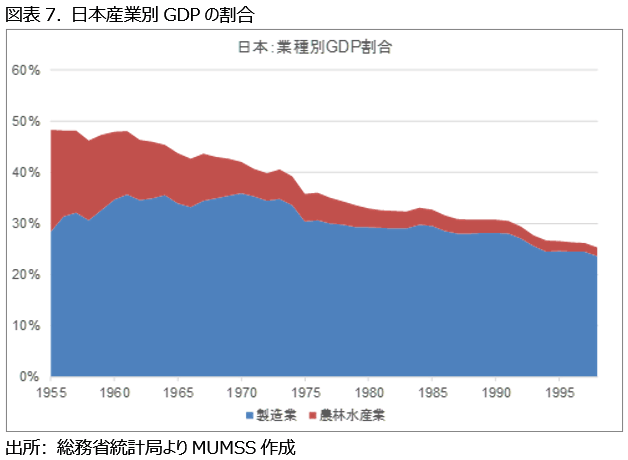
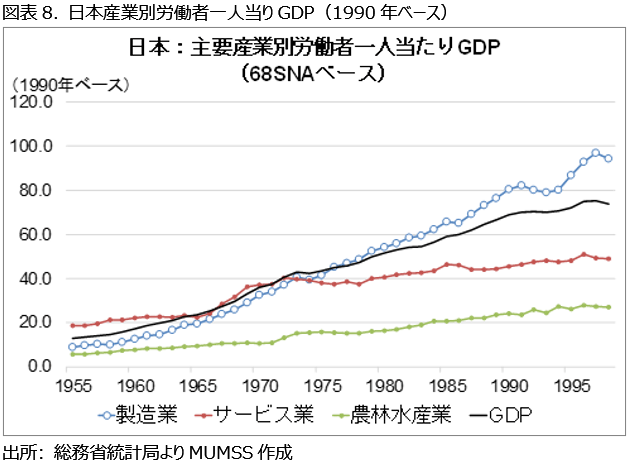
製造業のGDPに占める割合は低下しつつも、製造業従業者一人当たりGDPで計測した生産性は上昇を続けたのである。いわば、日本経済にとって製造業は「スリム化」すると同時に、「筋肉質化」したと言えよう。それを支えたのは、産業用ロボットや制御機器などによるFA化(ファクトリーオートメーション)や、高品質化、差別化などの戦略であった。
中国の製造業は「空洞化」というより「スリム化」「筋肉質化」
それを踏まえて考えると興味深いのは、筆者に聞こえてくる、中国に進出している日本企業の次のような声である。一部の企業は、資本装備比率を引き上げていることに加えて中国の労働者の質も上がっていることから、一人当たりの生産性が、足元で上昇している様々なコスト以上に、上がっているため、中国での生産をより強化しているということだ。特に自動車関連や情報通信関連、医療機器関連企業がそうであるように見える。
つまり中国において、それは中国国内企業であろうと、海外からの進出企業であろうと、足元で直面している様々な困難を乗り越えようとしている企業が存在する。結局のところ、中国の製造業も「スリム化」し「筋肉質化」する可能性が高いのではないだろうか。
今回の日本政府の政策を考えてみると、同政策によって、一部の企業が国内回帰や、中国以外の国での生産設備の多元化を行う可能性は十分にあるものの、それは、その企業の生産だけで比較的成り立ってしまう、あるいは高付加価値化された産業集積地を必要としない産業の企業である可能性が高いのではないか。言い換えれば、一社だけが生産拠点を移動することが有利に働かない状態は、生産拠点移動はゲーム理論のいう「ナッシュ均衡」ではないため、移動することが最適解にはならない。
さらにいえば、前述の「海外事業活動基本調査」にもあるように、海外現地法人の投資決定のポイントのトップは「現地の製品需要が旺盛又は今後の需要が見込まれる」であり2017年度は68.6%と、2位の「進出先近隣三国で製品需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」の25.9%とは大きくかけ離れている。コストにかかわる「良質で安価な労働力が期待できる」や「税制、融資などの優遇措置がある」などのコストに関わるポイントはそれぞれ16.0%、8.0%と低くはないが、1位の需要要因と比べれば小さい(図表9)。結局は需要が重要なのだ。所得上昇が着実に進んでおり、それに伴った更なる高付加価値の需要増を見込む企業は、中国を選ばざるを得ない。
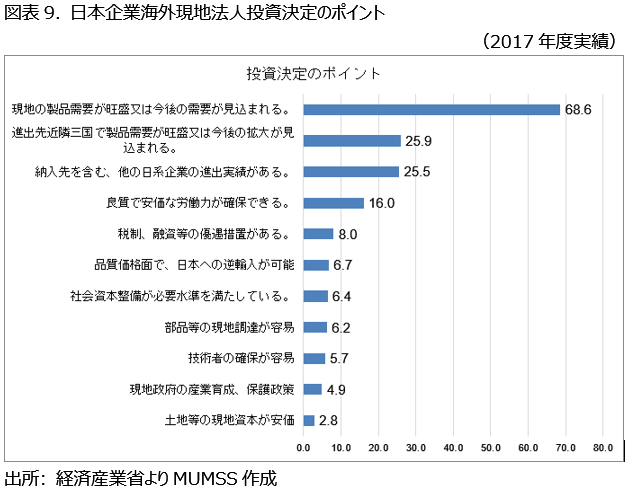
その意味で、前述DBJの調査にある「海外における設備投資動向(連結ベース)」のデータは興味深い。2020年度は、新型コロナウイルスを比較的早期に抑え込んだ中国への伸び率が全地域で唯一プラス(前年比10.8%増、全体同14.4%減)であったが、2021年度の計画は全体が前年比17.2%増と伸びる中、中国向けは25.6%増とさらに加速している(図表10)。
さらに前述の国際協力銀行の調査によれば、今後3年程度の有望な事業展開先国は、中国がインドを抜き再び首位に返り咲いている。新型コロナウイルスの感染拡大の抑制の程度が大きく影響した可能性は高いものの、中国の有望理由のトップが「現地マーケットの現状規模」であることは変わっていない(図表11)。
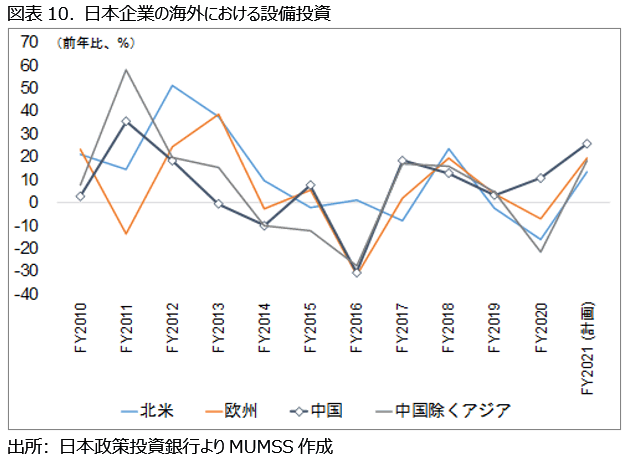
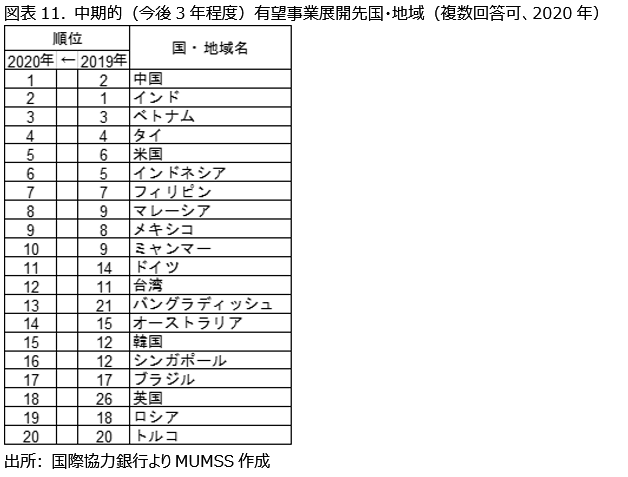
より大きな流れとしての保護主義も、中国での生産拠点の残留・強化に拍車をかけている。保護主義の下では、国境を超えた取引は一層難しくなるため、地産地消型の生産拠点の確保が必要となる。よって、中国国内の需要増が継続するという見通しのもとでは、中国を離れることができない。
結果どうなるのか。中国国内で所得増による需要増を見越した企業・産業は、自動化や生産合理化、差別化などの戦略を用いてコスト上昇以上の生産性上昇を目指す。一方で、産業集積に依存せず、低コスト構造、生産地以外の需要に依存するような企業・産業は、中国を離れ、ASEANなどへと生産拠点を移動させることになるだろう。
その結果、中国国内においては、経済活動に占める製造業の割合は持続的に低下する一方、中国国内で生産を続ける企業の生産性は上がっていく(図表12~13)。いや、上げることができる企業しか生き残れなくなっていく、という表現の方が正しいだろう。
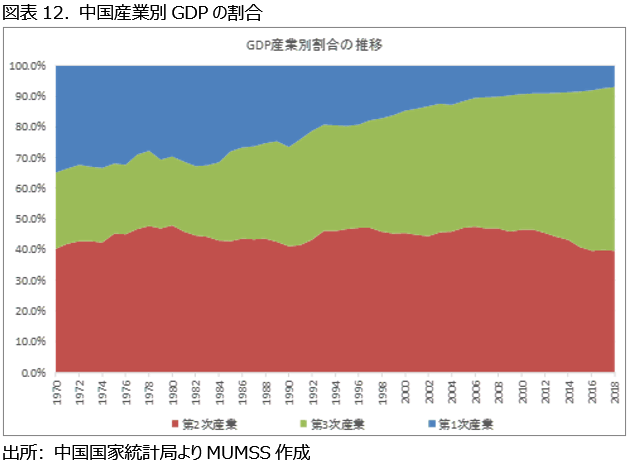
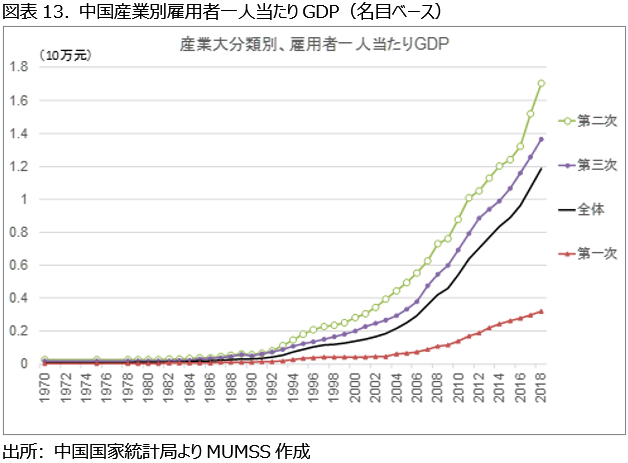
備えておくべきリスク
もちろん、企業によっては中国経済の不動産バブル崩壊や政治リスクなどを織り込む形で、移転を考える企業もあるだろう。更に言えば、米中の「技術覇権」争いが激化すれば、高付加価値な技術を中国で生み出しているということを理由に、米国市場へのアクセスを制限される可能性もある。これまでの米中摩擦の激化を考えれば、十分に想定しておく必要のあるリスクであろう。
だが逆に過去の日本の例から、もう一つ備えておかなければならないリスクもある。それは中国という巨大市場にあると想定していた需要が、競合相手である中国企業などによって、その多くを奪われてしまうことである。家電や一般機械をはじめ、建設機械など様々な面で、中国企業の台頭は進みつつある。過去に米国の代表的な産業が、日本企業によって追いやられたようなことが、日本企業に起きないとは限らない。
企業間の競争が公平であるならば、それは市場による淘汰に過ぎない。だがそこに、万が一知的財産の保護や人権問題など、保護主義を含めた何らかの問題が関わっているのであるならば、官民が課題ごとに協力するのみならず、同盟国との協力関係の下、公平なルール作りが一層必要となろう。
新型コロナウイルスによりデジタルなコミュニケーションがより容易になった現在、多国間のコミュニケーションを緊密に行い、公平な競争環境を構築することで、自由貿易主義の後退を止めることが必要である。これまで常にそうであったように、グローバリゼーションの危機は、同時に「グレートリセット」の好機でもある。
執筆者プロフィール
李智雄(り・ちうん)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 チーフエコノミスト
2003年から2006年まで韓国陸軍士官学校にて陸軍中尉及び経済学科専任講師。2006年から2014年までゴールドマンサックス東京及びソウルオフィスにて、日本経済エコノミスト、韓国経済エコノミスト兼韓国ストラテジストを歴任。2011年度東京大学大学院総合文化研究科にて客員准教授。地域文化研究講義を担当。2011年10月~3月経済産業省「グローバル化と国際分業の中での産業構造に関する研究会」委員。2013年~2016年新潟国際大学講師。Financial Markets and Globalization担当。2014年三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社、2018年よりチーフエコノミスト。2021年米国国務省インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム(IVLP)参加。著書『故事成語で読み解く中国経済』(日経BP社)2016年。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 チーフエコノミスト
李 智雄
新型コロナウイルス禍で見直しの議論が進んだサプライチェーン
新型コロナウイルスのみならず、貿易摩擦や、震災などが、なぜ日本をはじめとした様々な国のグローバルサプライチェーンに決定的な変化を与えていないのか、に関して考えてみたい。
新型コロナウイルスが世界経済に大きな影響を与える以前より、グローバルサプライチェーンを巡る各国の問題意識は高まっていた。ジャーナリストのトーマス・フリードマンが2005年に用いた「フラット化する世界(The World is Flat)」という言葉が、実際に世界が「フラット化」したかどうかの議論はさておき、世界中の企業、投資家に対して世界がグローバル化している、という印象を説得的に与えたことは記憶に新しい。
しかしグローバリゼーションに対する期待の時代は長続きしなかった。二つの象徴的なデータがある。一つは世界経済成長率である。2008年のグローバル金融危機前までの10年間(1998~2007年)、世界の実質GDP成長率は年平均4.2%増であった。だが、2007年の5.5%増をピークにその後は、同成長率を上回る伸び率は確認できていない。具体的にはグローバル金融危機を経た(よって金融危機中の2008~2009年の成長率は除く)世界の経済成長率は2010~19年までで年平均3.7%増へと低下している(図表1)。
もう一つはWTOにおけるアンチ・ダンピング関税措置の新規調査開始件数である。グローバリゼーションの進展を受け、2001年の372件から徐々に低下してきたが、2007年に165件とボトムとなったあと、その後は振れを伴いつつも上昇傾向が続き、2020年は349件まで上昇した(図表2)。
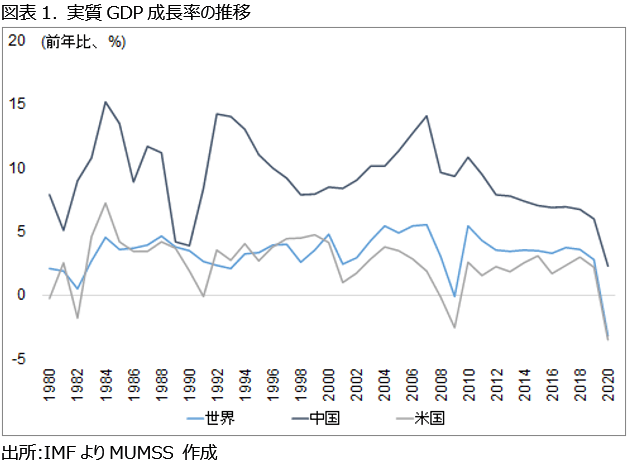
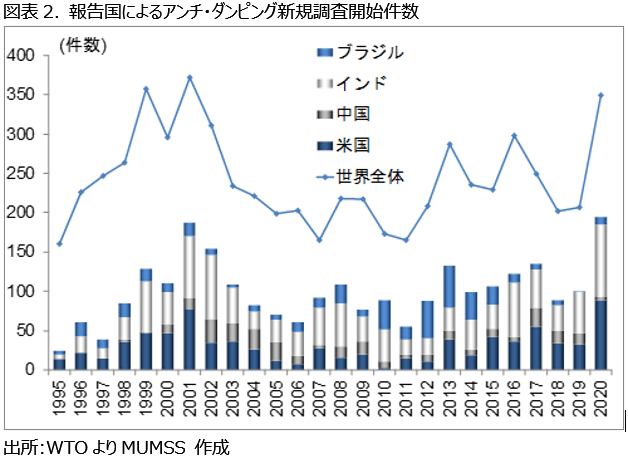
何が起こっているのか。背景には、経済成長率低下に伴う保護主義の復活がある。象徴的には、米中の貿易摩擦やBREXIT(2017年3月29日に通知された英国のEU離脱)が挙げられよう。
特に米中の対立は、関税のみならず、様々な分野の貿易に関する規制にまで及んでおり、両国ともに1、2位の貿易相手国となっている日本は勿論のこと、様々な国に対して、サプライチェーンの在り方の再考を迫ってきた。
そこに発生したのが新型コロナウイルスの問題である。新型コロナ禍によるサプライチェーンの分断は、身近な医療用品を含め、各国政府に対応を促す大きな契機となった。
例えば日本政府は2020年4月に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、国内回帰や多元化を通じた強固なサプライチェーンの構築を支援することを決定している(1次採択で3,060億円、2次採択で2,108億円の予算)。
サプライチェーン見直しの議論は実際のアクションにつながっているのか
それでは、同対策の国内回帰等への補助によって、国内への生産回帰は進んできたのだろうか。
国際協力銀行による「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告(2020年度海外直接投資アンケート調査結果(第32回))」によれば、新型コロナウイルスを受けた「海外投資計画の見直し」について聞かれた企業のうち、56.3%が「変更はない」と答えている。「製品・事業別の配分を見直す」(15.8%)、「投資計画を一時凍結する」(14.3%)などとある一方で、「国内投資に切り替える」はわずか2.0%に過ぎない(図表3)。
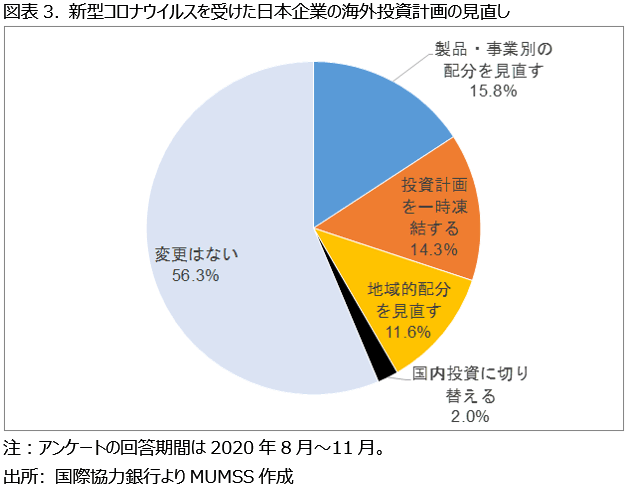
同時に、新型コロナウイルスを受け、海外投資計画の「地域的配分を見直す」という会社の割合は11.6%と一定割合存在する。
結果、中国からの生産拠点の移動が一部生じることは間違いなさそうだ。これまでも、中国からの生産拠点の移転の必要性は何度も話題になってきた。2010年前後の中国国内における過剰労働力の枯渇による賃金の上昇(いわゆる「ルイスの転換点(期間)」)の議論に加え、2016年前後の環境規制強化(それ以前から環境規制はあったが、2015年10月中国国務院弁公庁は「環境保護監査法案(試行)」を公布、その後処罰件数が大幅増加)、2018年以降の米中関税引き上げなど、その度に安価な「世界の工場」としての中国の地位は疑問視されてきた(図表4)。
また、日本政策投資銀行(DBJ)の「全国設備投資計画調査(2021年6月調査)」のうち、「企業行動に関する意識調査」を見てみると、「サプライチェーン見直しの契機(全産業、大企業)」は、「新型コロナウイルス」が58%とトップだが、「自社固有の事情などその他」23%を除けば、次に「米中対立の激化」が23%、「人件費の高騰」が16%と続くことから、新型コロナウイルスだけがサプライチェーン見直しの議論の背景にあったわけではないことがわかる。うち、「米中対立の激化」や「人件費の高騰」の影響を受けたのが中国であることは想像に難くない(図表5)。
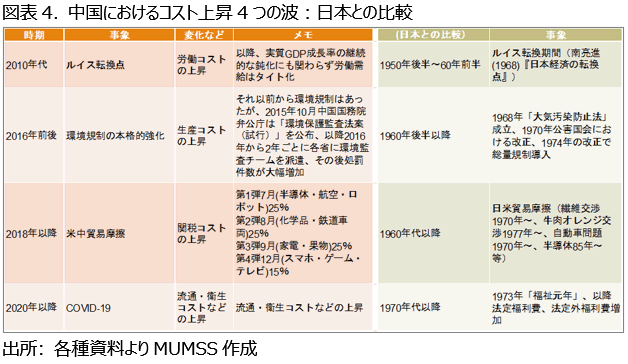
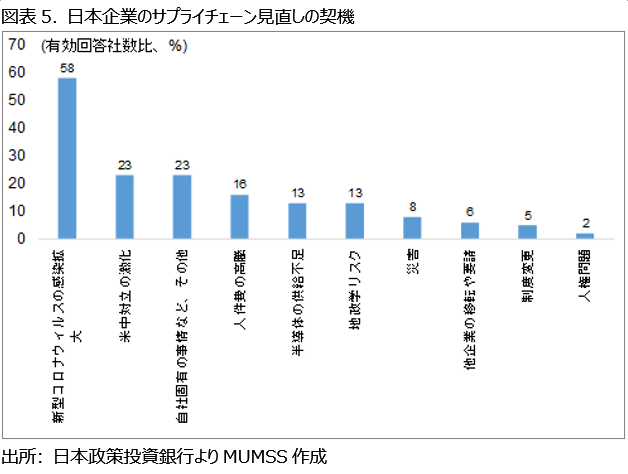
その結果、実際に日本企業の海外現地法人数のうち、中国の占める割合は2012年度の33.0%をピークに低下してきた(経済産業省、海外事業活動基本調査)。一方でASEANの比率は、2019年度まで拡大してきた。なお2020年度は新型コロナウイルスの早期収束に成功した中国の割合が再び拡大していることは注記しておこう(図表6)。
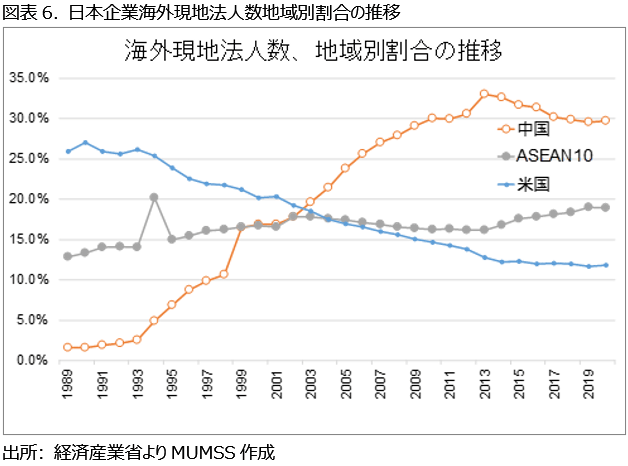
これを受けて、中国の製造業の空洞化は進み、弱体化していく、そう結論づけて良いのだろうか。そうではないと考えている。
中国から生産拠点を移動している企業の多くは、中国におけるコスト上昇(賃金や環境コスト、関税など)に耐えきれなくなったため、よりコストが低いASEAN諸国を選ばざるを得なくなった企業であろう。
日本から海外への生産拠点進出が進んだ1970年代を振り返る
ここで少し遠回りをして日本の経験を振り返ってみよう。1970年代の日本経済は、2010年代以降の中国経済に次の四つの点で類似している。
まず、(1)経済成長率の低下傾向(1960年代の年平均9.1%増から、1970年代は4.6%増へと鈍化)、次に(2)米国との対立激化(日米繊維交渉開始は1970年、第二次鉄鋼自主輸出規制は1972年より)、それから(3)賃金(労働コスト)の上昇(日本のルイスの転換点は1950年代後半から1960年代前半、南亮進(1968年))、そして(4)各種生産コストの上昇(環境規制強化、社会保障強化。例えば、1973年を田中角栄内閣は「福祉元年」と宣言)である(前掲図表4)。
これらは企業にとって、市場の魅力度の低下や企業活動に関わるコストの上昇となって意識されたはずだ。そのような日本で、製造業はどのような変遷を遂げたのか。
日本企業が海外への進出を積極化したことに加えて(経済産業省の海外事業活動基本調査の調査開始年は1971年である)、サービスを含めた非製造業の比率が上昇したことは周知の通りである。それではその結果、日本の製造業が空洞化し、弱体化したかと言えば、そうではなかった(図表7~8)。
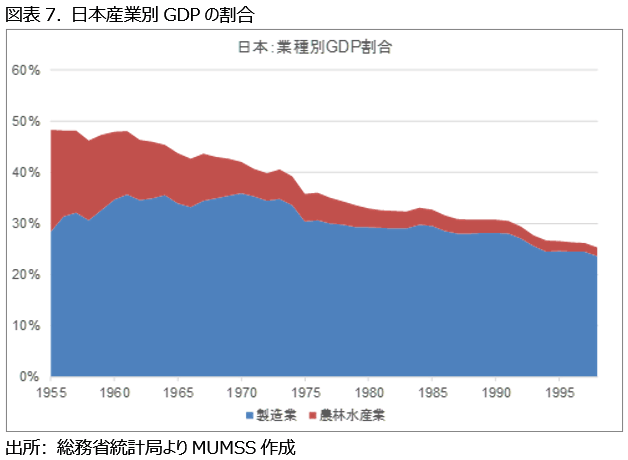
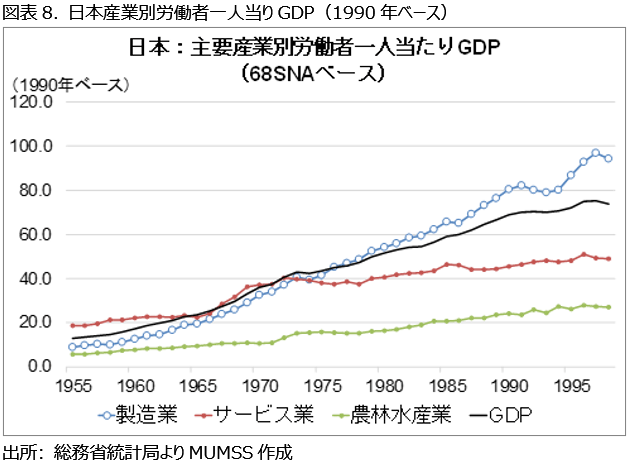
製造業のGDPに占める割合は低下しつつも、製造業従業者一人当たりGDPで計測した生産性は上昇を続けたのである。いわば、日本経済にとって製造業は「スリム化」すると同時に、「筋肉質化」したと言えよう。それを支えたのは、産業用ロボットや制御機器などによるFA化(ファクトリーオートメーション)や、高品質化、差別化などの戦略であった。
中国の製造業は「空洞化」というより「スリム化」「筋肉質化」
それを踏まえて考えると興味深いのは、筆者に聞こえてくる、中国に進出している日本企業の次のような声である。一部の企業は、資本装備比率を引き上げていることに加えて中国の労働者の質も上がっていることから、一人当たりの生産性が、足元で上昇している様々なコスト以上に、上がっているため、中国での生産をより強化しているということだ。特に自動車関連や情報通信関連、医療機器関連企業がそうであるように見える。
つまり中国において、それは中国国内企業であろうと、海外からの進出企業であろうと、足元で直面している様々な困難を乗り越えようとしている企業が存在する。結局のところ、中国の製造業も「スリム化」し「筋肉質化」する可能性が高いのではないだろうか。
今回の日本政府の政策を考えてみると、同政策によって、一部の企業が国内回帰や、中国以外の国での生産設備の多元化を行う可能性は十分にあるものの、それは、その企業の生産だけで比較的成り立ってしまう、あるいは高付加価値化された産業集積地を必要としない産業の企業である可能性が高いのではないか。言い換えれば、一社だけが生産拠点を移動することが有利に働かない状態は、生産拠点移動はゲーム理論のいう「ナッシュ均衡」ではないため、移動することが最適解にはならない。
さらにいえば、前述の「海外事業活動基本調査」にもあるように、海外現地法人の投資決定のポイントのトップは「現地の製品需要が旺盛又は今後の需要が見込まれる」であり2017年度は68.6%と、2位の「進出先近隣三国で製品需要が旺盛又は今後の拡大が見込まれる」の25.9%とは大きくかけ離れている。コストにかかわる「良質で安価な労働力が期待できる」や「税制、融資などの優遇措置がある」などのコストに関わるポイントはそれぞれ16.0%、8.0%と低くはないが、1位の需要要因と比べれば小さい(図表9)。結局は需要が重要なのだ。所得上昇が着実に進んでおり、それに伴った更なる高付加価値の需要増を見込む企業は、中国を選ばざるを得ない。
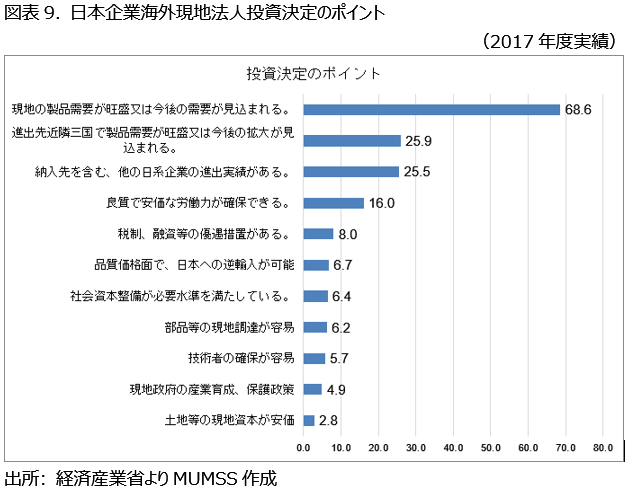
その意味で、前述DBJの調査にある「海外における設備投資動向(連結ベース)」のデータは興味深い。2020年度は、新型コロナウイルスを比較的早期に抑え込んだ中国への伸び率が全地域で唯一プラス(前年比10.8%増、全体同14.4%減)であったが、2021年度の計画は全体が前年比17.2%増と伸びる中、中国向けは25.6%増とさらに加速している(図表10)。
さらに前述の国際協力銀行の調査によれば、今後3年程度の有望な事業展開先国は、中国がインドを抜き再び首位に返り咲いている。新型コロナウイルスの感染拡大の抑制の程度が大きく影響した可能性は高いものの、中国の有望理由のトップが「現地マーケットの現状規模」であることは変わっていない(図表11)。
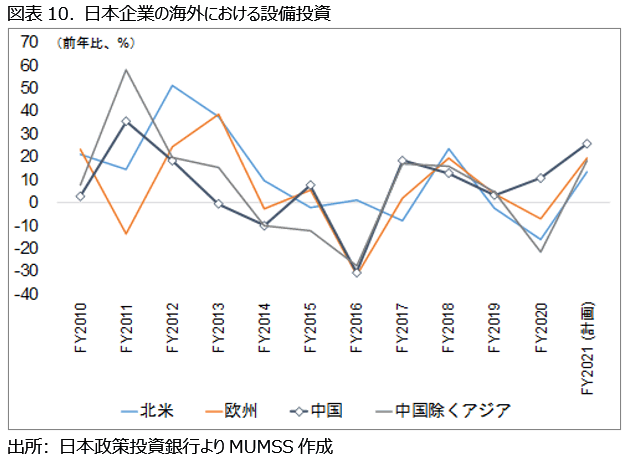
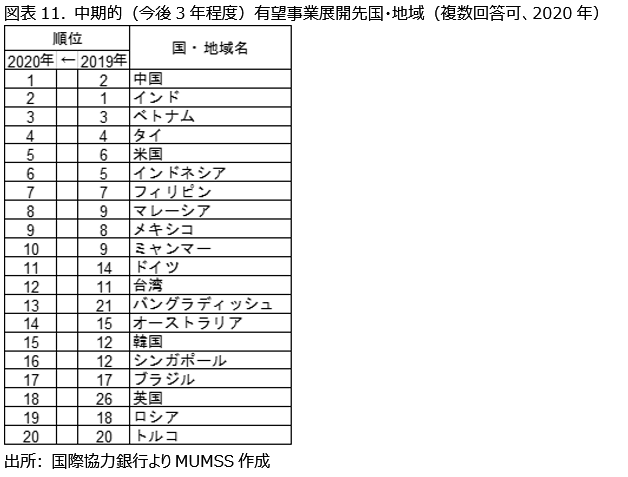
より大きな流れとしての保護主義も、中国での生産拠点の残留・強化に拍車をかけている。保護主義の下では、国境を超えた取引は一層難しくなるため、地産地消型の生産拠点の確保が必要となる。よって、中国国内の需要増が継続するという見通しのもとでは、中国を離れることができない。
結果どうなるのか。中国国内で所得増による需要増を見越した企業・産業は、自動化や生産合理化、差別化などの戦略を用いてコスト上昇以上の生産性上昇を目指す。一方で、産業集積に依存せず、低コスト構造、生産地以外の需要に依存するような企業・産業は、中国を離れ、ASEANなどへと生産拠点を移動させることになるだろう。
その結果、中国国内においては、経済活動に占める製造業の割合は持続的に低下する一方、中国国内で生産を続ける企業の生産性は上がっていく(図表12~13)。いや、上げることができる企業しか生き残れなくなっていく、という表現の方が正しいだろう。
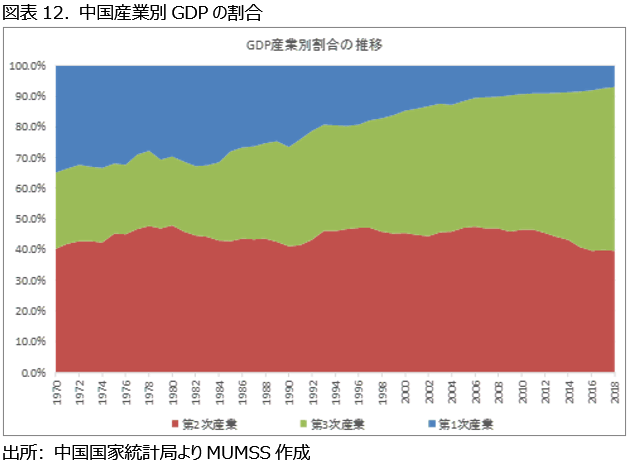
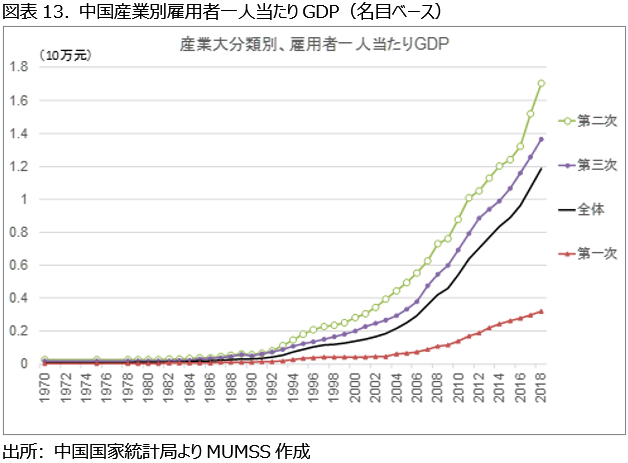
備えておくべきリスク
もちろん、企業によっては中国経済の不動産バブル崩壊や政治リスクなどを織り込む形で、移転を考える企業もあるだろう。更に言えば、米中の「技術覇権」争いが激化すれば、高付加価値な技術を中国で生み出しているということを理由に、米国市場へのアクセスを制限される可能性もある。これまでの米中摩擦の激化を考えれば、十分に想定しておく必要のあるリスクであろう。
だが逆に過去の日本の例から、もう一つ備えておかなければならないリスクもある。それは中国という巨大市場にあると想定していた需要が、競合相手である中国企業などによって、その多くを奪われてしまうことである。家電や一般機械をはじめ、建設機械など様々な面で、中国企業の台頭は進みつつある。過去に米国の代表的な産業が、日本企業によって追いやられたようなことが、日本企業に起きないとは限らない。
企業間の競争が公平であるならば、それは市場による淘汰に過ぎない。だがそこに、万が一知的財産の保護や人権問題など、保護主義を含めた何らかの問題が関わっているのであるならば、官民が課題ごとに協力するのみならず、同盟国との協力関係の下、公平なルール作りが一層必要となろう。
新型コロナウイルスによりデジタルなコミュニケーションがより容易になった現在、多国間のコミュニケーションを緊密に行い、公平な競争環境を構築することで、自由貿易主義の後退を止めることが必要である。これまで常にそうであったように、グローバリゼーションの危機は、同時に「グレートリセット」の好機でもある。
執筆者プロフィール
李智雄(り・ちうん)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 チーフエコノミスト
2003年から2006年まで韓国陸軍士官学校にて陸軍中尉及び経済学科専任講師。2006年から2014年までゴールドマンサックス東京及びソウルオフィスにて、日本経済エコノミスト、韓国経済エコノミスト兼韓国ストラテジストを歴任。2011年度東京大学大学院総合文化研究科にて客員准教授。地域文化研究講義を担当。2011年10月~3月経済産業省「グローバル化と国際分業の中での産業構造に関する研究会」委員。2013年~2016年新潟国際大学講師。Financial Markets and Globalization担当。2014年三菱UFJモルガン・スタンレー証券入社、2018年よりチーフエコノミスト。2021年米国国務省インターナショナル・ビジター・リーダーシップ・プログラム(IVLP)参加。著書『故事成語で読み解く中国経済』(日経BP社)2016年。

