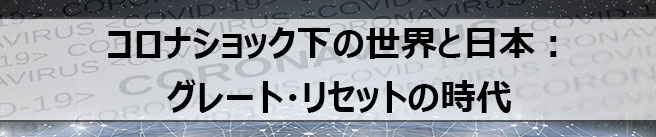
(5) コロナ禍に立ち向かう民主主義と専制政治の違い

掲載日:2021年6月11日
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
柯 隆
1990年代初頭、ソ連が崩壊し冷戦は終結した。歴史の終焉と表現されている冷戦の終結は専制政治と計画経済の失敗によるものだった。民主主義陣営は全面的な勝利を収め、市場経済は計画経済よりも優れていると認識されている。その後、旧ソ連や東欧諸国は民主化し、経済も市場経済化した。そのなかで中国は冷戦が終結する10年前、具体的に1978年から「改革・開放」をはじめ、計画経済に市場経済の要素、すなわち、市場メカニズムを取り入れた。今の中国経済は市場経済でもなく、計画経済でもない、両者を組み合わせた中国の特色のある社会主義市場経済と定義されている。これまでの30年間、中国経済は奇跡的な高成長を実現した。
民主主義はベストな制度ではなく、ベターな制度とよくいわれる。その指摘が正しければ、専制政治はどんな制度なのだろうか。毛沢東が定義した中国の専制政治は民主集中制だった。要するに、広く民主的に意見を聞き取り、最後に政治的にそれを集約して意思決定するというプロセスのことである。しかし、ガバナンス機能が用意されていない専制政治では、政治の意思決定において民主的な意見を取り入れる保証はない。毛時代の27年間(1949-76年)、民主的に意見を聞き取ることは単なる政治的パフォーマンスでしかなかった。政治の意思決定は一貫して独裁的に行われていた。
むろん、現在の中国社会は毛時代と比較して決定的に異なる点として、市場開放によってプロパガンダのマインドコントロールはかつてほど機能しなくなった。中国では、厳しい情報統制が続いているが、いったん自由を味わった人民から再び自由を奪おうとしても必ずや激しく抵抗される。とくに、海外に定住しているビジネスマンや留学生などは、その親族や友人に海外の情報をインターネットを通じて伝えているため、毛時代のプロパガンダはマインドコントロールの効果が予想以上に低下している。
そこで、コロナ禍は中国社会に思わぬ影を落としている。まず、コロナ感染の水際作戦として堂々と門戸が閉ざされた。そして、同じコロナ感染の抑制策として人民に対する監視体制が強化されている。さらに、中国は世界主要国のなかで唯一コロナ感染抑制に成功した国であり、専制政治の中国は民主主義よりも優れていると主張している。
確かに2020年、世界主要国の経済は軒並みマイナス成長を喫したが、中国経済だけは2.3%とプラス成長を実現した。2021年第1四半期、中国経済はさらに18.3%も成長した。その背景には、コロナ感染抑制に成功し、経済活動が再開したことがある。李克強首相は全人代(日本の国会に相当)で行った政府活動報告において「内循環経済モデル」を繰り返して強調した。しかし、グローバル化されている中国経済は「内循環経済モデル」、すなわち、内需に依存するだけで成長を持続していけるのだろうか。
ポストコロナ禍の世界経済と中国経済の展望
コロナ禍による世界経済への最大のダメージは各国が人流を抑制して有効需要が弱まったことである。そもそも2008年のリーマンショックをきっかけに世界主要国の中央銀行は弱まった景気を押し上げるために、低金利政策に加え、大規模な量的緩和を実施してきた。コロナ禍に立ち向かうために、各国政府は金融緩和政策に加え、大規模な財政出動を行っている。世界中の人々はワクチンの効果に期待を寄せているが、しかし、ウィルスの変異が続いており、コロナ禍との闘いは短期的に終わりそうにない。このままいけば、国家のバランスシートが壊れる可能性が高くなる。
世界の景気が減速するなるなか、一番心配されるのは雇用の悪化である。減速する景気を押し上げるのに躍起となっている各国の中央銀行による異次元の金融緩和政策と大規模な財政出動は株高をもたらし資産バブルを引き起こしている。ハーバード大学元学長のローレンス・サマーズ教授は米紙ワシントン・ポストのコラムに寄稿し「コロナ禍によるデフレを心配するよりも、インフレーションへの対処に備えるべき」と警鐘を鳴らしている。しかし、世界主要国の中央銀行は金融政策を転換する姿勢をみせていない。結果的に、所得格差と資産格差が拡大し、二極化を示すK字経済が鮮明になっている。
もっとも、コロナ禍において中国経済はプラス成長を実現しているとはいえ、独り勝ちにはならない。短期的には長年、高い貯蓄率が維持されてきたため、富裕層の家庭を中心に多額の金融資産を保有しており、内需依存の経済成長が当面続くと予想される。ただし、諸外国と同じように中国の雇用情勢も深刻化している。外国人ビジネスマンが宿泊するホテルや海外旅行を企画する旅行会社など外需依存サービス産業は内需向けに経営方針を転換しているが、経営方針の転換だけでは経営を立て直しすることができない。とくに、輸出製造業の下請けの中小企業の一部は存亡の危機に直面している。中国の輸出製造業にとってコロナ禍だけでなく、米中対立の激化も輸出拡大の妨げになっている。
繰り返しになるが、習政権はコロナ禍をきっかけに中国社会に対する監視と統制を強化している。習政権が進める統制経済は近代経済学に重要な挑戦を突き付けている。というのは、アダムスミス以降の古典派経済学では、市場メカニズムこそ資源配分を効率化することができるといわれているからである。政府の役割を強調するケインズ経済学でも、政府の役割は市場メカニズムを補完するものと位置付けている。しかし、習政権は経済統制を強化して成長を維持しようとしている。毛時代に逆戻りしようとする習政権の統制経済でも資源配分を効率化できるのだろうか。
近代経済学の常識では、政府主導の資源配分は効率化しないとしているが、強権政治において政府はあらゆる資源を動員して、短期的な高成長を成し遂げることができる。1950年代初期の旧ソ連の経済成長はその典型例といえる。それに対して、1980年代以降の中国の経済成長は政府主導のものというよりも、部分的に市場メカニズムを取り入れ、それによる資源配分が効率化したから、経済成長を実現できた。
中国の経済学者は「改革・開放」以降の経済システムを「双軌制」(dual track systems)と定義している。「双軌制」とは計画経済の統制価格と市場経済の市場価格が併存するシステムのことである。たとえば、中国では、石油や電力といった公共財の価格が政府によって統制されている。それに対して、日用品や食品などの価格が市場メカニズムによって調整され決まるようになっている。本来ならば、中国がこの「双軌制」を徐々に撤廃し、市場価格に一本化すれば、中国経済はもっと高い成長を成し遂げることができたはずである。習政権は経済統制を強化しているため、市場メカニズムによる資源配分は非効率化する可能性が高い。したがって、中国経済が持続的に成長していけるかどうかはわからなくなっている。
ポストコロナ禍のグローバル覇権のあり方
戦後、アメリカは名実ともに世界の覇権国家だった。旧ソ連と対峙する必要性からアメリカは西ヨーロッパの国々と連携を強化し、民主主義陣営を結成した。その間、中国は社会主義陣営に属しながら、ソ連との関係がぎくしゃくしていた。中国は独自の路線を歩み、東南アジアの小国とアフリカの一部の国と密接な関係を維持していた。中国は一貫して途上国の代表としての自らの足場を固めている。
1974年鄧小平副首相(当時)は国連特別会議で「中国は今も将来も超大国にはならない。超大国とは他国を侵略、干渉、コントロール、転覆、世界覇権を狙う帝国主義国家のことである。(中略)もし、ある日、中国が超大国に変わり、世界で覇権国家になろうとするとすれば、もしいたるところで他国を侵略し、他国を搾取するとすれば、世界の人民は中国に社会帝国主義の帽子を被せ、それを暴き、それに反対してほしい。しかも、(世界の人民は)中国人民と一緒にそれを打倒してほしい」との談話を発表した。
鄧小平政治思想の神髄は「韜光養晦」(とうこうようかい)というものである。それは自らの実力が十分に強くなるまで、それを隠しておくことである。それは鄧小平の人生観そのものといえる。鄧小平は毛時代において繰り返し、毛によって追放されたが、毛との正面衝突を避けながら、その都度、再起を果たすことができた。しかし、韜光養晦は鄧小平だからこそそれを成功裏に生かして権力闘争に勝ち抜くことができた。習近平政権になってから、中国の経済規模は急拡大した。それを受けて、中国はそろそろ世界のリーダーになれるのではないかと思われるようになった。習政権には鄧小平の韜光養晦のDNAは含まれていないといわざるを得ない。
むろん、習政権は中国が世界で覇権を求めていると認めていない。習主席は中華民族の偉大なる復興を目指している。これは中国の夢であると表明されている。しかし、中華民族の偉大なる復興とはいつのことを意味するのだろうか。数千年の中国の歴史において秦の始皇帝は中国を統一したが、短命な王朝(27年間)だった。中国の文化の土台を作ったのは漢だった。もっとも輝かしい王朝はいうまでもなく唐だった。しかし、中国の文化が一番栄えたのは宋だった。中国の近代が宋から始まったと主張する歴史家すらいる。
中国の経済規模(GDP)は遅くとも2030年までにアメリカを超えるとみられている。英国誌「エコノミスト」は速ければ、中国のGDPは2028年にもアメリカを超えると予測している。習政権は中国の経済規模がアメリカを超えることを中華民族の偉大なる復興とみているのだろうか。明らかに問題はそれほど単純ではない。
覇権という言葉は中国でネガティブなイメージが強いため、あまり使わないが、習政権が目指すのは世界のリーダーになることではなかろうか。リーダーとは世界のルールを決める役割のことである。それゆえ、覇権国家のアメリカと激しく対立してしまうのである。
中国にとっての強国復権の条件
中国からみると、単なる可能性だが、コロナ禍により先進国の国力が大きく低下する可能性がある。少なくとも現在の中国の経済力からいかなる国も中国を封じ込めることができないのは明白である。だからこそバイデン政権は中国のことを敵とみなしておらず、競争相手と位置付けている。
バイデン政権の外交戦略をトランプ政権のそれと比較すると、最大の違いは同盟国を重視する点ではなかろうか。アメリカ単独で中国に対峙しても勝てる可能性は低いが、同盟国との連携で中国に挑もうとしているのがバイデン政権の外交戦略である。
一方、中国はかつてないほど自信を持っている。習政権は強国復権に向けてまっしぐらである。2018年、貿易不均衡を理由にトランプ政権に制裁関税を課されるなど喧嘩を売られたとき、習政権は「我々は喧嘩を売らないが、売られた喧嘩は必ず買う。我々の文化は目には目、歯には歯である」とどんな代償を払ってでも絶対屈服しないと決意をあらわにした。
問題は中国はほんとうに世界のリーダーになれるのだろうか。これにはいくつかの条件がある。少なくとも世界に恐れられる国は世界のリーダーになれない。世界に尊敬される国にならないといけない。
では、中国にとって強国復権の条件とはどんなものだろうか。
まず、強い経済力が必要である。強い経済力とは、単に経済規模が大きくなるだけでなく、イノベーションなど強い科学力と技術力が求められる。中国のGDPは2010年、日本を追い抜いて世界二番目の規模になった。しかし、科学のノーベル賞受賞者は一人だけである。製造業にとってもっとも重要な技術の一つは工作機械の製造技術だが、中国のハイテク工作機械の国産化率はわずか6%程度である。
そして、二番目の条件は軍事力である。素人的な見方を紹介すれば、軍事力は強国がとことんまで強化したほうがいいように思われがちだが、自国の経済力がそれを支えきれなくなれば、その結末は旧ソ連の轍を踏むことになる。したがって、軍事力はとことんまで強化するのではなくて、自国防衛の必要性に応じて強化する、いわゆる最適化でなければならない。とくに、中国のような財政ガバナンスのない国では、必要以上に軍備を増強しようとしがちである。適切にブレーキを踏まなければ、経済力が軍事力の増強を支えきれなくなる可能性がある。
最後にもっとも重要な条件だが、それは強国にとって必ず必要なのは文化力である。歴史を振り返るまでもないことだが、唐の王朝に文化力がなかったら、日本から遣唐使は長安(現在の西安)へ行かなかったはずである。問題は今の中国は文化力が予想以上に弱くなっている点である。文化が芽生える条件は自由が不可欠である。経済統制、言論統制、情報統制などを強化していることは自国の文化力を弱めることである。経済力があり、軍事力が強くて、文化力のない国が他国に尊敬されるのだろうか。結論的にいえば、このままでは、中国は強国復権を実現することが難しいと思われる。
最後に、コロナ禍は世界を大きく変える可能性がある。重要な点は、目に見えないウィルスに立ち向かうために、世界は結束を強化しようとしている。その過程で、価値観の共有はこれまで以上に重要視されるようになるということである。
執筆者プロフィール
柯 隆(か・りゅう) Long Ke
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年、同大卒業。94年、名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。長銀総合研究所国際調査部研究員(98年まで)。98~2006年、富士通総研経済研究所主任研究員、06年より同主席研究員を経て、現職。 兼職:静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授、研究分野・主な関心領域:開発経済、中国のマクロ経済
著書:『「ネオ・チャイナリスク」研究:ヘゲモニーなき世界の支配構造』(慶應義塾大学出版会、2021)、『中国「強国復権」の条件』(慶應義塾大学出版会、2018。第13回 樫山純三賞)ほか。
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
柯 隆
1990年代初頭、ソ連が崩壊し冷戦は終結した。歴史の終焉と表現されている冷戦の終結は専制政治と計画経済の失敗によるものだった。民主主義陣営は全面的な勝利を収め、市場経済は計画経済よりも優れていると認識されている。その後、旧ソ連や東欧諸国は民主化し、経済も市場経済化した。そのなかで中国は冷戦が終結する10年前、具体的に1978年から「改革・開放」をはじめ、計画経済に市場経済の要素、すなわち、市場メカニズムを取り入れた。今の中国経済は市場経済でもなく、計画経済でもない、両者を組み合わせた中国の特色のある社会主義市場経済と定義されている。これまでの30年間、中国経済は奇跡的な高成長を実現した。
民主主義はベストな制度ではなく、ベターな制度とよくいわれる。その指摘が正しければ、専制政治はどんな制度なのだろうか。毛沢東が定義した中国の専制政治は民主集中制だった。要するに、広く民主的に意見を聞き取り、最後に政治的にそれを集約して意思決定するというプロセスのことである。しかし、ガバナンス機能が用意されていない専制政治では、政治の意思決定において民主的な意見を取り入れる保証はない。毛時代の27年間(1949-76年)、民主的に意見を聞き取ることは単なる政治的パフォーマンスでしかなかった。政治の意思決定は一貫して独裁的に行われていた。
むろん、現在の中国社会は毛時代と比較して決定的に異なる点として、市場開放によってプロパガンダのマインドコントロールはかつてほど機能しなくなった。中国では、厳しい情報統制が続いているが、いったん自由を味わった人民から再び自由を奪おうとしても必ずや激しく抵抗される。とくに、海外に定住しているビジネスマンや留学生などは、その親族や友人に海外の情報をインターネットを通じて伝えているため、毛時代のプロパガンダはマインドコントロールの効果が予想以上に低下している。
そこで、コロナ禍は中国社会に思わぬ影を落としている。まず、コロナ感染の水際作戦として堂々と門戸が閉ざされた。そして、同じコロナ感染の抑制策として人民に対する監視体制が強化されている。さらに、中国は世界主要国のなかで唯一コロナ感染抑制に成功した国であり、専制政治の中国は民主主義よりも優れていると主張している。
確かに2020年、世界主要国の経済は軒並みマイナス成長を喫したが、中国経済だけは2.3%とプラス成長を実現した。2021年第1四半期、中国経済はさらに18.3%も成長した。その背景には、コロナ感染抑制に成功し、経済活動が再開したことがある。李克強首相は全人代(日本の国会に相当)で行った政府活動報告において「内循環経済モデル」を繰り返して強調した。しかし、グローバル化されている中国経済は「内循環経済モデル」、すなわち、内需に依存するだけで成長を持続していけるのだろうか。
ポストコロナ禍の世界経済と中国経済の展望
コロナ禍による世界経済への最大のダメージは各国が人流を抑制して有効需要が弱まったことである。そもそも2008年のリーマンショックをきっかけに世界主要国の中央銀行は弱まった景気を押し上げるために、低金利政策に加え、大規模な量的緩和を実施してきた。コロナ禍に立ち向かうために、各国政府は金融緩和政策に加え、大規模な財政出動を行っている。世界中の人々はワクチンの効果に期待を寄せているが、しかし、ウィルスの変異が続いており、コロナ禍との闘いは短期的に終わりそうにない。このままいけば、国家のバランスシートが壊れる可能性が高くなる。
世界の景気が減速するなるなか、一番心配されるのは雇用の悪化である。減速する景気を押し上げるのに躍起となっている各国の中央銀行による異次元の金融緩和政策と大規模な財政出動は株高をもたらし資産バブルを引き起こしている。ハーバード大学元学長のローレンス・サマーズ教授は米紙ワシントン・ポストのコラムに寄稿し「コロナ禍によるデフレを心配するよりも、インフレーションへの対処に備えるべき」と警鐘を鳴らしている。しかし、世界主要国の中央銀行は金融政策を転換する姿勢をみせていない。結果的に、所得格差と資産格差が拡大し、二極化を示すK字経済が鮮明になっている。
もっとも、コロナ禍において中国経済はプラス成長を実現しているとはいえ、独り勝ちにはならない。短期的には長年、高い貯蓄率が維持されてきたため、富裕層の家庭を中心に多額の金融資産を保有しており、内需依存の経済成長が当面続くと予想される。ただし、諸外国と同じように中国の雇用情勢も深刻化している。外国人ビジネスマンが宿泊するホテルや海外旅行を企画する旅行会社など外需依存サービス産業は内需向けに経営方針を転換しているが、経営方針の転換だけでは経営を立て直しすることができない。とくに、輸出製造業の下請けの中小企業の一部は存亡の危機に直面している。中国の輸出製造業にとってコロナ禍だけでなく、米中対立の激化も輸出拡大の妨げになっている。
繰り返しになるが、習政権はコロナ禍をきっかけに中国社会に対する監視と統制を強化している。習政権が進める統制経済は近代経済学に重要な挑戦を突き付けている。というのは、アダムスミス以降の古典派経済学では、市場メカニズムこそ資源配分を効率化することができるといわれているからである。政府の役割を強調するケインズ経済学でも、政府の役割は市場メカニズムを補完するものと位置付けている。しかし、習政権は経済統制を強化して成長を維持しようとしている。毛時代に逆戻りしようとする習政権の統制経済でも資源配分を効率化できるのだろうか。
近代経済学の常識では、政府主導の資源配分は効率化しないとしているが、強権政治において政府はあらゆる資源を動員して、短期的な高成長を成し遂げることができる。1950年代初期の旧ソ連の経済成長はその典型例といえる。それに対して、1980年代以降の中国の経済成長は政府主導のものというよりも、部分的に市場メカニズムを取り入れ、それによる資源配分が効率化したから、経済成長を実現できた。
中国の経済学者は「改革・開放」以降の経済システムを「双軌制」(dual track systems)と定義している。「双軌制」とは計画経済の統制価格と市場経済の市場価格が併存するシステムのことである。たとえば、中国では、石油や電力といった公共財の価格が政府によって統制されている。それに対して、日用品や食品などの価格が市場メカニズムによって調整され決まるようになっている。本来ならば、中国がこの「双軌制」を徐々に撤廃し、市場価格に一本化すれば、中国経済はもっと高い成長を成し遂げることができたはずである。習政権は経済統制を強化しているため、市場メカニズムによる資源配分は非効率化する可能性が高い。したがって、中国経済が持続的に成長していけるかどうかはわからなくなっている。
ポストコロナ禍のグローバル覇権のあり方
戦後、アメリカは名実ともに世界の覇権国家だった。旧ソ連と対峙する必要性からアメリカは西ヨーロッパの国々と連携を強化し、民主主義陣営を結成した。その間、中国は社会主義陣営に属しながら、ソ連との関係がぎくしゃくしていた。中国は独自の路線を歩み、東南アジアの小国とアフリカの一部の国と密接な関係を維持していた。中国は一貫して途上国の代表としての自らの足場を固めている。
1974年鄧小平副首相(当時)は国連特別会議で「中国は今も将来も超大国にはならない。超大国とは他国を侵略、干渉、コントロール、転覆、世界覇権を狙う帝国主義国家のことである。(中略)もし、ある日、中国が超大国に変わり、世界で覇権国家になろうとするとすれば、もしいたるところで他国を侵略し、他国を搾取するとすれば、世界の人民は中国に社会帝国主義の帽子を被せ、それを暴き、それに反対してほしい。しかも、(世界の人民は)中国人民と一緒にそれを打倒してほしい」との談話を発表した。
鄧小平政治思想の神髄は「韜光養晦」(とうこうようかい)というものである。それは自らの実力が十分に強くなるまで、それを隠しておくことである。それは鄧小平の人生観そのものといえる。鄧小平は毛時代において繰り返し、毛によって追放されたが、毛との正面衝突を避けながら、その都度、再起を果たすことができた。しかし、韜光養晦は鄧小平だからこそそれを成功裏に生かして権力闘争に勝ち抜くことができた。習近平政権になってから、中国の経済規模は急拡大した。それを受けて、中国はそろそろ世界のリーダーになれるのではないかと思われるようになった。習政権には鄧小平の韜光養晦のDNAは含まれていないといわざるを得ない。
むろん、習政権は中国が世界で覇権を求めていると認めていない。習主席は中華民族の偉大なる復興を目指している。これは中国の夢であると表明されている。しかし、中華民族の偉大なる復興とはいつのことを意味するのだろうか。数千年の中国の歴史において秦の始皇帝は中国を統一したが、短命な王朝(27年間)だった。中国の文化の土台を作ったのは漢だった。もっとも輝かしい王朝はいうまでもなく唐だった。しかし、中国の文化が一番栄えたのは宋だった。中国の近代が宋から始まったと主張する歴史家すらいる。
中国の経済規模(GDP)は遅くとも2030年までにアメリカを超えるとみられている。英国誌「エコノミスト」は速ければ、中国のGDPは2028年にもアメリカを超えると予測している。習政権は中国の経済規模がアメリカを超えることを中華民族の偉大なる復興とみているのだろうか。明らかに問題はそれほど単純ではない。
覇権という言葉は中国でネガティブなイメージが強いため、あまり使わないが、習政権が目指すのは世界のリーダーになることではなかろうか。リーダーとは世界のルールを決める役割のことである。それゆえ、覇権国家のアメリカと激しく対立してしまうのである。
中国にとっての強国復権の条件
中国からみると、単なる可能性だが、コロナ禍により先進国の国力が大きく低下する可能性がある。少なくとも現在の中国の経済力からいかなる国も中国を封じ込めることができないのは明白である。だからこそバイデン政権は中国のことを敵とみなしておらず、競争相手と位置付けている。
バイデン政権の外交戦略をトランプ政権のそれと比較すると、最大の違いは同盟国を重視する点ではなかろうか。アメリカ単独で中国に対峙しても勝てる可能性は低いが、同盟国との連携で中国に挑もうとしているのがバイデン政権の外交戦略である。
一方、中国はかつてないほど自信を持っている。習政権は強国復権に向けてまっしぐらである。2018年、貿易不均衡を理由にトランプ政権に制裁関税を課されるなど喧嘩を売られたとき、習政権は「我々は喧嘩を売らないが、売られた喧嘩は必ず買う。我々の文化は目には目、歯には歯である」とどんな代償を払ってでも絶対屈服しないと決意をあらわにした。
問題は中国はほんとうに世界のリーダーになれるのだろうか。これにはいくつかの条件がある。少なくとも世界に恐れられる国は世界のリーダーになれない。世界に尊敬される国にならないといけない。
では、中国にとって強国復権の条件とはどんなものだろうか。
まず、強い経済力が必要である。強い経済力とは、単に経済規模が大きくなるだけでなく、イノベーションなど強い科学力と技術力が求められる。中国のGDPは2010年、日本を追い抜いて世界二番目の規模になった。しかし、科学のノーベル賞受賞者は一人だけである。製造業にとってもっとも重要な技術の一つは工作機械の製造技術だが、中国のハイテク工作機械の国産化率はわずか6%程度である。
そして、二番目の条件は軍事力である。素人的な見方を紹介すれば、軍事力は強国がとことんまで強化したほうがいいように思われがちだが、自国の経済力がそれを支えきれなくなれば、その結末は旧ソ連の轍を踏むことになる。したがって、軍事力はとことんまで強化するのではなくて、自国防衛の必要性に応じて強化する、いわゆる最適化でなければならない。とくに、中国のような財政ガバナンスのない国では、必要以上に軍備を増強しようとしがちである。適切にブレーキを踏まなければ、経済力が軍事力の増強を支えきれなくなる可能性がある。
最後にもっとも重要な条件だが、それは強国にとって必ず必要なのは文化力である。歴史を振り返るまでもないことだが、唐の王朝に文化力がなかったら、日本から遣唐使は長安(現在の西安)へ行かなかったはずである。問題は今の中国は文化力が予想以上に弱くなっている点である。文化が芽生える条件は自由が不可欠である。経済統制、言論統制、情報統制などを強化していることは自国の文化力を弱めることである。経済力があり、軍事力が強くて、文化力のない国が他国に尊敬されるのだろうか。結論的にいえば、このままでは、中国は強国復権を実現することが難しいと思われる。
最後に、コロナ禍は世界を大きく変える可能性がある。重要な点は、目に見えないウィルスに立ち向かうために、世界は結束を強化しようとしている。その過程で、価値観の共有はこれまで以上に重要視されるようになるということである。
執筆者プロフィール
柯 隆(か・りゅう) Long Ke
公益財団法人 東京財団政策研究所 主席研究員
1963年、中華人民共和国・江蘇省南京市生まれ。88年来日、愛知大学法経学部入学。92年、同大卒業。94年、名古屋大学大学院修士課程修了(経済学修士号取得)。長銀総合研究所国際調査部研究員(98年まで)。98~2006年、富士通総研経済研究所主任研究員、06年より同主席研究員を経て、現職。 兼職:静岡県立大学グローバル地域センター特任教授、多摩大学大学院客員教授、研究分野・主な関心領域:開発経済、中国のマクロ経済
著書:『「ネオ・チャイナリスク」研究:ヘゲモニーなき世界の支配構造』(慶應義塾大学出版会、2021)、『中国「強国復権」の条件』(慶應義塾大学出版会、2018。第13回 樫山純三賞)ほか。

