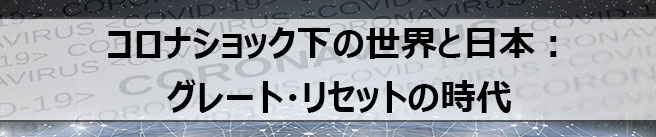
コロナショック下の世界と日本:グレート・リセットの時代

掲載日:2021年5月24日
一般財団法人 国際経済連携推進センター 理事長
政策研究大学院大学理事・客員教授
日本経済研究センター参与
JETRO運営審議会委員
小島 明
中国湖北省武漢で新型ウイルスが検出されたのは2019年12月末。翌2020年1月には日本国内での感染者が確認されたのをはじめ、感染は急激な勢いで各国に波及し、深刻なパンデミックとなった。世界経済はIMF(国際通貨基金)が『グレート・ロックダウン』と呼ぶ中、各国間、業種間、各種階層間などで様々な「格差」を生みながら、1930年代の大恐慌以来という大不況に陥った。2020年の世界経済の成長率はマイナス3.3%まで落ち込んだ。様々な分野での格差拡大は、経済・社会がK字型、つまり上昇・拡大する分野と下降・低下する分野とに二極化しながら展開し始めていることに注目する向きもある。コロナショックは一過性のものではなく、経済・社会の構造を大きく転換させ始めた。
IMFは2021年4月の世界経済見通し(WEO)で、2021年には6.0%、2022年は4.4%のプラス成長を世界経済に見込んでいる。これは前回2020年10月の見通しと比べ、それぞれ0.8%、0.2%の上方修正であり、さらなる悪化を阻止できるとの見通しになっている。しかし、このプラス成長は(1)米国はじめ主要国におけるかつてない規模での財政拡大策と金融緩和に支えられた(2)有効なワクチン接種が順調に進む―といった要素・前提に基づくものであり、IMF自体、ワクチン接種効果への期待を示しながらも、経済活動の正常化が進むまでのつなぎとなる政策支援の有効性など、予測を取り巻く「不確実性」が極めて大きいと警告している。また、(1)の財政拡大は、すでに警戒水準まで膨らんでいる各国の政府債務を一段と膨らませるもので、これも不確実性を増幅している。
現在のパンデミックは世界中を巻き込んだ「戦争」だとも言える。感染が拡大するなかで多くの国、都市が封鎖され、人、モノの移動が抑制され、そのため経済活動が顕著に縮小した。それでも世界全体の感染者は2021年4月末時点で約1億4650万人、死者は310万人に達している。
日本は強制的な都市封鎖、ロックダウンはせず、自粛要請の形で対応してきた。しかし感染者は波状的に増え、2020年4月、21年1月次いで21年4月に政府が「緊急事態宣言」を発した。感染者は2021年4月末で57万人弱、死者は1万人を超えてしまった。日本の問題は、ワクチン接種が極端に遅れていることにある。
日本経済新聞と英フィナンシャル・タイムズの共同集計によると、世界全体のコロナワクチン接種は2021年4月末時点で10億回を超え、1回以上接種した人はイスラエルで約6割、英国で5割に達し、両国の経済、社会活動が段階的に正常化に向かいつつあるという。
イスラエルの場合、最近の新規感染者は80人程度まで減少している。対照的なのが日本であり、ワクチン接種が始まったのは2月17日からで、4月末時点で1回目のワクチン接種を終えたのは180万人ほどであり、普及率は1%超でしかない。これはアジア全体の接種率4%と比べてもひどく見劣りがする。
当面のコロナ対応そのものは大問題だが、それとは別に今回のコロナ禍で露呈された様々の構造問題がある。第1はパンデミックに対する世界の備えが脆弱であることである。その脆弱さゆえに、感染が拡大するなかで本来必要な多国間の協力体制が強化されるどころか、各国が自国中心となり、必要とされるマスク、体温計をはじめとする個人用、医療用の製品、人工呼吸器等の医療関連物資の輸出制限措置がとられた。マスクは多くの国が中国に供給を大きく依存していたため、さながらグローバルな中国製マスクの争奪戦となった。これに乗じて中国は外交的な影響力を強め、友好国・協力国を増やそうと意図した「マスク外交」を展開した。
日本は自国でワクチンを製造できない状態にあり、医療品も輸入依存である。ちなみに医療品の世界輸出総額は1兆ドル近い規模であり、輸出上位10カ国はドイツ、米国、スイス、オランダ、ベルギー、アイルランド、中国、フランス、イタリア、英国の順である。
2021年4月半ばに開かれたバイデン大統領と菅首相による日米首脳会談で採択された共同声明はコロナウイルスに関して次のように言及している。
「新型コロナウイルス感染症は、日米両国および世界に対して、我々が生物学的な大惨事への備えができていないことを示した。この目的のため、日米両国はまた、健康安全保障(ヘルスセキュリティ)の推進、将来の公衆衛生危機への対応およびグローバルヘルスの構築のための協力を強化する」。
声明はさらに「パンデミックを終わらせるため、グローバルな新型ウイルス・ワクチンの供給および製造のニーズに関して協力する」とも指摘したが、残念ながら日本は自国のワクチン確保もままならない状況であり、そうした協力が出来る余地は限られている。
露呈された第2の問題は、日本のデジタル技術の利活用の遅れである。菅政権は2021年9月に行政のIT化、国全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進を目的としたデジタル庁を設置する予定である。デジタル改革担当大臣の平井卓也氏は都内の会合での挨拶で「コロナ禍はデジタル活用において、日本がいかに遅れているかを痛感させた」と言い、「人口減少・超高齢化社会の中で、デジタルの力を使い、持続的に成長できるモデルの構築が求められている」と述べている。
コロナ禍のもとで在宅勤務、大学等でのリモート講義、リモート会議、Eコマースが増加し、働き方、生活様式、経営モデルなどに大きな変化が見られる。ただ、いわゆるデジタル化は、コロナ禍で一気に加速はしているが、コロナ禍以前から進行しており、とうに経済・社会のパラダイム転換をもたらしつつある。「数年分のデジタル化が数カ月で起こった」との指摘も耳にする。その通りではある。しかし、日本より先行していた国々も、コロナ危機をきっかけにデジタル化をさらに加速させている。日本が相対的に劣後している状況は変わらないというべきだろう。
新しいデジタル庁は、おそらくいくつものKPI(目的・ゴールの達成度を測るための指標)を掲げるだろう。しかし、日本のデジタル化が遅れている現実を客観的に直視、かつ遅れてしまった原因を追究することなしにはKPIへ向けた前進は難しい。現に、これまでの政権は、日本が上位のデジタル先進国になることを目指したが、現実には日本のこの分野での国際ランキングは下がってしまった。IMD世界デジタル競争力指数によると、2020年のランキングは27位で、2015年から4つ順位が落ちている。アジアにおいてもシンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシアより低く、7位にとどまる。
在日アメリカ商工会議所(ACCJ)が2021年2月にまとめた報告書『2030日本デジタル改革』は、「世界は過去に例を見ないほどの改革的なデジタル時代に突入した」と前置きしながら「日本は規制改革や体制整備の面が他国に遅れをとっている。日本が推進すべきは大規模改革である。漸進主義では競争力の差を埋めることはできない」と強調している。報告は日本がデジタル化で劣後したいくつもの原因を指摘している。他国へのアドバイスとしての報告のため、そうした原因については「日本には改革の余地があり、前進の余地がある」と、婉曲かつ前向きな表現で「可能性」を指摘している。しかし、指摘された原因を取り除かなければ、いかなるKPIを掲げても無意味だろう。
DXという言葉は、日本でいま、はやり言葉となっている。しかし、スウェーデンの情報学者、E.ストルターマンがDXを提唱したのは2004年で、20年近くも前のことである。デジタル時代はデータ、特許など無形資産が戦略的にも重要になるが、日本は20世紀に成果をあげたモノづくり、有形資産の発想にとらわれすぎてはいないだろうか。
米国のアナリストの予想によると、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)にマイクロソフトを加えた米国のIT5社(GAFAM)による合計の研究開発投資は2022年には1641億ドル(約17兆9000億円)となり、2018年の日本の民間部門全部の研究開発投資額を上回る。
行政のデジタル化の遅れもひどく、2021年初めの一人10万円の現金給付に際してのもたつきにもそれが現れた。だから大きな政府が必要というわけではない。必要なのは、民間部門の創意工夫の努力を妨げないよう、規制改革をすることだろう。日本の政府による規制は「規制の玉ねぎ」(グレン・S・フクシマ氏の指摘)であり、剥いても剥いても次の規制が顔をだす。例えば、法令には法律、政令、省令、通達、規制、内規、行政指導と7つの層がある。規制の類型も許可、認可、免許、承認、指定、承諾、認定、確認、認証、届出、提出、報告、申告など20もあるという。それぞれの定義が明確でなく、行政の担当者が裁量的に解釈している。この不透明、裁量性は、データが駆動力となるデジタル時代の阻害要因であることは明らかである。
「いつの間に後進国になったか」と題する日本経済新聞の「大機小機」コラム(2021年4月9日付)は、日本がワクチン後進国、デジタル後進国、「化石賞」を受けた環境後進国、世界120位のジェンダー後進国、人権後進国、さらに公的債務残高が年間GDP(国内総生産)の2.7倍に膨れ上がった財政後進国だと嘆いている(無垢氏)。
日本はいくつもの独自の難しい構造問題を抱えている。それらの多くは、コロナ禍以前から存在し、対応が先送りされてきたものである。日本の現在の諸困難を新型コロナのせいにしてはならない。だが、現実の政策はコロナ対応に追われ、そうした構造的な課題への対応が生ぬるいものになっているようだ。
例えば、潜在成長率の低下。先進国の潜在成長率を「直近の5年間平均でみると、米国が2.0%、ユーロ圏が1.3%なのに対し、日本は0.6%でしかない。労働人口の減少も影響しているが、総合的な生産性であるTFP(全要素生産性)が低い。超高齢社会になって求められている社会保障制度改革もなかなか進まない。
また、コロナショックで所得、消費が落ちるなか、10万円給付の効果に期待があったが、給付のほとんどが貯蓄に回ったという。コロナ禍以前から「賃金デフレ」が続き、人々は将来不安から消費を抑制した。しかも、賃金が減ったのに貯蓄が増え、いわゆる消費性向が2014年の75%から2020年には61%にまで落ちるという、各国にも、日本の近年の歴史においても見られなかった現象が生まれている。
コロナ禍以前から問題となっていた地球温暖化問題が、さらに重要視されている。それは、近年、世界各地においてスーパー台風、洪水、森林火災など自然災害が過酷化、多発化していることへの危機意識を背景としている。世界各地、とりわけ欧州各国では「地球非常事態宣言」が発せられている。株主利益最優先を改めようとする動きが米国でも生まれ、「ステークホルダー資本主義」論が「情報・データ資本主義」論とならんで議論されている。「最大のステークホルダーは地球ではないか」という見方も浮上している。「地球安全保障」論の発想も生まれている(地球産業文化研究所報告)。
気候変動対策の国際的な枠組みとして190カ国・地域が批准したパリ協定が、2016年11月に発効した。米国のトランプ前政権は2017年に同協定から離脱したが、バイデン新政権になって2021年2月に復帰した。米国はいまや環境政策の旗振り役になろうとしている。象徴的なのは、菅・バイデン会談後の共同声明である。声明はこううたっている。
「気候危機は世界にとって生存に関わる脅威であると認識し、日米両国はこの危機と闘うための世界の取り組みを主導し、重要な役割を果たす。2050年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的な形で、2030年までに確固たる行動をとる。この責任を認識し、菅総理とバイデン大統領は『日米気候パートナーシップ』を立ち上げた」。
パリ協定合意と同じ2015年の国連サミットにおいて全会一致で合意したSDGs(持続可能な開発目標)がパリ協定理念と合流する格好で、気候変動、地球環境問題への各国の取り組みが加速している。
SDGsは17の目標を掲げているが、それを3つのグループに分類し、3つ重ねのウェディングケーキに見立てる発想が興味深い。一番下の層は地球環境がらみのもので、その他の目標を支えるという構図である。
パリ協定とSDGsはこうして合流した。それへの積極的な挑戦が成長・発展の制約ではなく新しい形の成長・発展につながるとの認識も強まり、グリーン成長戦略を打ち出す国が増えている。日本も化石賞を返上すべく、遅ればせながらではあるが菅政権が2020年10月に「温暖化ガス2050年ゼロ」目標を表明し、日米首脳会談の直後には、2030年までに温暖化ガスの排出を2013年度比で46%削減するとの目標を打ち出した。
その目標達成には政策対応、産業構造、経営モデルからライフスタイルに及ぶ、グレート・リセットと称される大きな変革が必要になる。デジタル化もそうした変革を支える上で不可欠な戦略でもある。
ただ、デジタル化、情報化に関しては副作用の抑制も必要になろう。プライバシー保護をどう扱うかという問題も重要である。民主主義の在り方をめぐる議論も活発になっている。この点に関してはデジタル時代の情報リテラシーの問題にも目を向けなければならない。パンデミックをもじったインフォデミックが注目されだした。真偽が不明な情報の氾濫・拡散の危険のことである。
インターネットを通じた情報の多くは匿名で、かつ個人でも既存の巨大メディアを超えるような伝播力を持つことがある。また、フェイクニュースが新型コロナウイルスの情報に関しても増え、社会の混乱を招いてもいる。
間違った情報には、単純な誤情報であるmis-information、意図的な偽情報であるdis-information、さらに悪意のある攻撃mal-informationがある。
Post Truthの時代だともいわれる。自分が共感できる情報、得になる情報が真実だと意識する傾向も台頭しつつある。インターネット検索サイトがユーザーを識別しユーザーの欲しいと思われる情報を推定し、見たくなさそうな情報を遮断する(フィルタリング)という現象もある。健全な民主主義、市場経済を確保するために、こうした問題をどう処理するか。デジタル時代の情報リテラシーは重大な問題である。
当面のコロナ危機はいずれ収束するだろうが、その時期はワクチンの普及に大きく依存する。順調な普及ができず、危機が長期化するリスクもある。ウィズコロナの長期化である。
さらに、環境破壊が続く限り感染爆発は繰り返されるとする見方も生まれている。自然の生態系が破壊され、ウイルス感染が起きやすいようにウイルスが「解放される」ためだという説である。
いずれにしても今回のコロナ危機はデジタル化を一気に加速し、地球環境問題への危機意識を醸成し、それにより、経済・社会に大きな変革と転換をもたらしつつある。あるいは、それを必要としている。100年以上も続いたエンジン車の文明もデジタル技術と環境重視が重なって推進されだしたEV(電気自動車)の挑戦を受けている。
いろいろな面において、今回のコロナ危機は従来からの政策、制度、経営、生活様式、さらには国際関係にまで影響を及ぼしつつある。グレート・トランスフォーメーション(大転換)、グレート・リセットの時代なのだろう。
リセットが求められる分野は多方面にわたっている。まず、国際関係において、多国間主義、自由貿易主義が脅かされていることを真剣に受け止めなければならない。近年、国際関係において、いくつもの「分断」が生じている。急速に台頭し、自らも大国指向の中国に対して米国が警戒心を高め、地政学的な変動を背景とした米中”新冷戦“が懸念されている。両国は貿易制限、報復を繰りかえしている。
そうした状況にコロナ禍が上乗せされ、国際関係は一層ぎくしゃくしだした。貿易面では輸入制限だけでなく安全保障を大義名分として輸出管理(規制)、投資規制の動きも強まっている。
世界が直面する問題には地球環境、感染症、テロ対策など一国だけでは対処できず、対立ではなくむしろ一層の協調、協力が不可欠な分野がある。
民主主義のリセットも必要である。米国の2020年の大統領選挙では、トランプ前大統領が「選挙に不正があった」とし、選挙結果を受け入れようとせず、多くのトランプ支持者が連邦議会に乱入するという事態にまで発展した。民主主義の基本が揺らいでいる。それには前述のインフォデミックも関連している。
さらに格差をめぐる問題も深刻である。それは、資本主義の在り方にまで絡む議論を生んでいる。資本主義は1970年代までは「調和的成長の時代」をもたらした。それはイノベーションを生み、成長と生活水準の向上を実現した。豊かさの格差はあっても富める者から富がしたたり落ちるように貧しい者にも自然と浸透していくという、いわゆるトリクルダウン論があった。しかし80年代以降、格差の拡大こそが問題となり、90年代から21世紀にはいってからは中間層の崩壊、それによる社会の分断が米国はじめ、多くの国で注目されるようになった。コロナ禍は格差問題を増幅した。経済回復のパターンとしてV字型とか、L字型とかがあるが、現在問題となっているのは格差拡大、二極化を示すK字型である。富める者はますます富み、貧しいものはますます貧しくなる現象である。これには同じ国のなかでの産業間、職業間、地域間、階層間の格差拡大に加えて国と国の間の格差の拡大がある。そうした格差の拡大が資本主義の在り方に問題を投げかけている。
2008年の米国投資会社、リーマン・ブラザーズ社の経営破綻をきっかけとした世界金融危機の際には、金融資本主義の暴走が問題となり、格差拡大に憤った人々が米国資本主義のシンボルであるウォール街を取り巻くデモを起こした。資本主義の在り方をめぐる議論が高まる中で、米国の主要企業が名を連ねる財界ロビーグループであるビジネス・ラウンドテーブルが2019年8月に声明を発表した。その内容は、米国経営の原則とされた株主資本主義、利益優先企業経営を自ら批判し、「ステークホルダー資本主義」への転換を宣言したものだった。それは現在加速しているESG(環境、社会的責任、不祥事を防ぐ企業統治)重視の経営・投資態度と重なるもので、従来の資本主義、企業経営の在り方が問われている。
またコロナ禍のなかでIT技術、デジタル技術が威力を発揮しているが、これもK字型経済を加速させている。IT企業の収益はコロナ禍の中で一段と増大した。株式市場でもK字型が見られ、米国の巨大IT5社GAFAMの株式時価総額が日本の東証1部約2170社の時価総額合計を上回った。これらIT5社の独占的な状況も懸念され、さらにその税負担率が米企業平均、各国企業平均より低いことも問題となっている。
巨大IT企業の一段の拡大が資本主義の在り方の論議に新しい課題を提示している。ここでも格差が、国と国の間、同じ国における業種間、個人間で問題となっている。さらにIT企業は自動車産業などと比べ、雇用の創出が少ないことも注目される。資本主義が急速の無形資産をもとにした利益に依存する形になっており、有形資本中心だったこれまでの資本主義における税制の在り方も、問い直されつつある。
スイスに本部を置くWEF(ワールド・エコノミック・フォーラム)は毎年、「ダボス会議」でグローバルなアジェンダ・セッティングをしており、今年は「グレート・リセット」をテーマとしてコロナ後の世界の在り方をめぐる討議を予定していた。だが、コロナ禍で、例年、1月に開く総会はネット会議になり、延期し5月に予定したシンガポール総会も中止となってしまった。パンデミックの深刻さを象徴する顛末だといえよう。しかし、これから様々なレベルにおいて、また各国でグレート・リセットが議論され、試みられると思われる。
当面のコロナ危機はワクチンが普及すれば山をこえるだろうが、その影響は永続しよう。コロナ後の世界がコロナ以前に戻ることはない。すでに過去の延長線上にはない新しい時代が生まれつつある。
世界経済における債務の状況も、コロナ前のトレンドとは断絶した格好で膨張している。IIF(国際金融協会)によると、世界が抱える債務は2020年に24兆ドル膨らんだ。世界全体のGDPの3.5倍を上回る。その後のコロナ対策で債務は一段と増大している。コロナ後にこれをどう処理するのか。政府が抱える公的債務も急膨張している。各国政策当局にも危機意識が生まれている。法人税率の引き下げ競争をやめようとする議論が始まったのはこのためである。
”ウィズコロナ”の状態が長期化しそうである。米国の調査会社であるユーラシア・グループは2021年始め発表した今年の世界10大リスクで、「新型コロナの長期化による影響」を2番目にあげた。そこでもコロナ禍の遺産としての巨額な公的債務に注目している。また、雇用喪失を背景に政府への信頼の喪失、社会分断の危険性を指摘、社会不安が高まることを警戒している。
”ウィズコロナ”の状態がすでに予想されたより長引いている。さらに長期化しそうである。ポストコロナ、アフターコロナを迎える前に取り組むべき課題は多い。従来からの在り方を根本的に問い直す、グレート・リセットの発想が欠かせない。
執筆者プロフィール
小島 明(こじま あきら)
一般財団法人 国際経済連携推進センター 理事長
ジャーナリスト、国際経済学者。日本経済新聞社ニューヨーク支局長、編集委員、論説委員、常務取締役論説主幹、専務取締役論説担当、公益社団法人・日本経済研究センター会長。政策研究大学院大学理事、客員教授。公益財団法人・本田財団理事、公益財団法人・イオンワンパーセントクラブ理事。2019年より国際経済連携推進センター理事長。
ボーン・上田記念国際記者賞、日本記者クラブ賞受賞。
主な著作に『「日本経済」どこへ行くのか(上)(下)』平凡社(2013年)など。
一般財団法人 国際経済連携推進センター 理事長
政策研究大学院大学理事・客員教授
日本経済研究センター参与
JETRO運営審議会委員
小島 明
中国湖北省武漢で新型ウイルスが検出されたのは2019年12月末。翌2020年1月には日本国内での感染者が確認されたのをはじめ、感染は急激な勢いで各国に波及し、深刻なパンデミックとなった。世界経済はIMF(国際通貨基金)が『グレート・ロックダウン』と呼ぶ中、各国間、業種間、各種階層間などで様々な「格差」を生みながら、1930年代の大恐慌以来という大不況に陥った。2020年の世界経済の成長率はマイナス3.3%まで落ち込んだ。様々な分野での格差拡大は、経済・社会がK字型、つまり上昇・拡大する分野と下降・低下する分野とに二極化しながら展開し始めていることに注目する向きもある。コロナショックは一過性のものではなく、経済・社会の構造を大きく転換させ始めた。
IMFは2021年4月の世界経済見通し(WEO)で、2021年には6.0%、2022年は4.4%のプラス成長を世界経済に見込んでいる。これは前回2020年10月の見通しと比べ、それぞれ0.8%、0.2%の上方修正であり、さらなる悪化を阻止できるとの見通しになっている。しかし、このプラス成長は(1)米国はじめ主要国におけるかつてない規模での財政拡大策と金融緩和に支えられた(2)有効なワクチン接種が順調に進む―といった要素・前提に基づくものであり、IMF自体、ワクチン接種効果への期待を示しながらも、経済活動の正常化が進むまでのつなぎとなる政策支援の有効性など、予測を取り巻く「不確実性」が極めて大きいと警告している。また、(1)の財政拡大は、すでに警戒水準まで膨らんでいる各国の政府債務を一段と膨らませるもので、これも不確実性を増幅している。
現在のパンデミックは世界中を巻き込んだ「戦争」だとも言える。感染が拡大するなかで多くの国、都市が封鎖され、人、モノの移動が抑制され、そのため経済活動が顕著に縮小した。それでも世界全体の感染者は2021年4月末時点で約1億4650万人、死者は310万人に達している。
日本は強制的な都市封鎖、ロックダウンはせず、自粛要請の形で対応してきた。しかし感染者は波状的に増え、2020年4月、21年1月次いで21年4月に政府が「緊急事態宣言」を発した。感染者は2021年4月末で57万人弱、死者は1万人を超えてしまった。日本の問題は、ワクチン接種が極端に遅れていることにある。
日本経済新聞と英フィナンシャル・タイムズの共同集計によると、世界全体のコロナワクチン接種は2021年4月末時点で10億回を超え、1回以上接種した人はイスラエルで約6割、英国で5割に達し、両国の経済、社会活動が段階的に正常化に向かいつつあるという。
イスラエルの場合、最近の新規感染者は80人程度まで減少している。対照的なのが日本であり、ワクチン接種が始まったのは2月17日からで、4月末時点で1回目のワクチン接種を終えたのは180万人ほどであり、普及率は1%超でしかない。これはアジア全体の接種率4%と比べてもひどく見劣りがする。
当面のコロナ対応そのものは大問題だが、それとは別に今回のコロナ禍で露呈された様々の構造問題がある。第1はパンデミックに対する世界の備えが脆弱であることである。その脆弱さゆえに、感染が拡大するなかで本来必要な多国間の協力体制が強化されるどころか、各国が自国中心となり、必要とされるマスク、体温計をはじめとする個人用、医療用の製品、人工呼吸器等の医療関連物資の輸出制限措置がとられた。マスクは多くの国が中国に供給を大きく依存していたため、さながらグローバルな中国製マスクの争奪戦となった。これに乗じて中国は外交的な影響力を強め、友好国・協力国を増やそうと意図した「マスク外交」を展開した。
日本は自国でワクチンを製造できない状態にあり、医療品も輸入依存である。ちなみに医療品の世界輸出総額は1兆ドル近い規模であり、輸出上位10カ国はドイツ、米国、スイス、オランダ、ベルギー、アイルランド、中国、フランス、イタリア、英国の順である。
2021年4月半ばに開かれたバイデン大統領と菅首相による日米首脳会談で採択された共同声明はコロナウイルスに関して次のように言及している。
「新型コロナウイルス感染症は、日米両国および世界に対して、我々が生物学的な大惨事への備えができていないことを示した。この目的のため、日米両国はまた、健康安全保障(ヘルスセキュリティ)の推進、将来の公衆衛生危機への対応およびグローバルヘルスの構築のための協力を強化する」。
声明はさらに「パンデミックを終わらせるため、グローバルな新型ウイルス・ワクチンの供給および製造のニーズに関して協力する」とも指摘したが、残念ながら日本は自国のワクチン確保もままならない状況であり、そうした協力が出来る余地は限られている。
露呈された第2の問題は、日本のデジタル技術の利活用の遅れである。菅政権は2021年9月に行政のIT化、国全体のDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進を目的としたデジタル庁を設置する予定である。デジタル改革担当大臣の平井卓也氏は都内の会合での挨拶で「コロナ禍はデジタル活用において、日本がいかに遅れているかを痛感させた」と言い、「人口減少・超高齢化社会の中で、デジタルの力を使い、持続的に成長できるモデルの構築が求められている」と述べている。
コロナ禍のもとで在宅勤務、大学等でのリモート講義、リモート会議、Eコマースが増加し、働き方、生活様式、経営モデルなどに大きな変化が見られる。ただ、いわゆるデジタル化は、コロナ禍で一気に加速はしているが、コロナ禍以前から進行しており、とうに経済・社会のパラダイム転換をもたらしつつある。「数年分のデジタル化が数カ月で起こった」との指摘も耳にする。その通りではある。しかし、日本より先行していた国々も、コロナ危機をきっかけにデジタル化をさらに加速させている。日本が相対的に劣後している状況は変わらないというべきだろう。
新しいデジタル庁は、おそらくいくつものKPI(目的・ゴールの達成度を測るための指標)を掲げるだろう。しかし、日本のデジタル化が遅れている現実を客観的に直視、かつ遅れてしまった原因を追究することなしにはKPIへ向けた前進は難しい。現に、これまでの政権は、日本が上位のデジタル先進国になることを目指したが、現実には日本のこの分野での国際ランキングは下がってしまった。IMD世界デジタル競争力指数によると、2020年のランキングは27位で、2015年から4つ順位が落ちている。アジアにおいてもシンガポール、香港、韓国、台湾、中国、マレーシアより低く、7位にとどまる。
在日アメリカ商工会議所(ACCJ)が2021年2月にまとめた報告書『2030日本デジタル改革』は、「世界は過去に例を見ないほどの改革的なデジタル時代に突入した」と前置きしながら「日本は規制改革や体制整備の面が他国に遅れをとっている。日本が推進すべきは大規模改革である。漸進主義では競争力の差を埋めることはできない」と強調している。報告は日本がデジタル化で劣後したいくつもの原因を指摘している。他国へのアドバイスとしての報告のため、そうした原因については「日本には改革の余地があり、前進の余地がある」と、婉曲かつ前向きな表現で「可能性」を指摘している。しかし、指摘された原因を取り除かなければ、いかなるKPIを掲げても無意味だろう。
DXという言葉は、日本でいま、はやり言葉となっている。しかし、スウェーデンの情報学者、E.ストルターマンがDXを提唱したのは2004年で、20年近くも前のことである。デジタル時代はデータ、特許など無形資産が戦略的にも重要になるが、日本は20世紀に成果をあげたモノづくり、有形資産の発想にとらわれすぎてはいないだろうか。
米国のアナリストの予想によると、GAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)にマイクロソフトを加えた米国のIT5社(GAFAM)による合計の研究開発投資は2022年には1641億ドル(約17兆9000億円)となり、2018年の日本の民間部門全部の研究開発投資額を上回る。
行政のデジタル化の遅れもひどく、2021年初めの一人10万円の現金給付に際してのもたつきにもそれが現れた。だから大きな政府が必要というわけではない。必要なのは、民間部門の創意工夫の努力を妨げないよう、規制改革をすることだろう。日本の政府による規制は「規制の玉ねぎ」(グレン・S・フクシマ氏の指摘)であり、剥いても剥いても次の規制が顔をだす。例えば、法令には法律、政令、省令、通達、規制、内規、行政指導と7つの層がある。規制の類型も許可、認可、免許、承認、指定、承諾、認定、確認、認証、届出、提出、報告、申告など20もあるという。それぞれの定義が明確でなく、行政の担当者が裁量的に解釈している。この不透明、裁量性は、データが駆動力となるデジタル時代の阻害要因であることは明らかである。
「いつの間に後進国になったか」と題する日本経済新聞の「大機小機」コラム(2021年4月9日付)は、日本がワクチン後進国、デジタル後進国、「化石賞」を受けた環境後進国、世界120位のジェンダー後進国、人権後進国、さらに公的債務残高が年間GDP(国内総生産)の2.7倍に膨れ上がった財政後進国だと嘆いている(無垢氏)。
日本はいくつもの独自の難しい構造問題を抱えている。それらの多くは、コロナ禍以前から存在し、対応が先送りされてきたものである。日本の現在の諸困難を新型コロナのせいにしてはならない。だが、現実の政策はコロナ対応に追われ、そうした構造的な課題への対応が生ぬるいものになっているようだ。
例えば、潜在成長率の低下。先進国の潜在成長率を「直近の5年間平均でみると、米国が2.0%、ユーロ圏が1.3%なのに対し、日本は0.6%でしかない。労働人口の減少も影響しているが、総合的な生産性であるTFP(全要素生産性)が低い。超高齢社会になって求められている社会保障制度改革もなかなか進まない。
また、コロナショックで所得、消費が落ちるなか、10万円給付の効果に期待があったが、給付のほとんどが貯蓄に回ったという。コロナ禍以前から「賃金デフレ」が続き、人々は将来不安から消費を抑制した。しかも、賃金が減ったのに貯蓄が増え、いわゆる消費性向が2014年の75%から2020年には61%にまで落ちるという、各国にも、日本の近年の歴史においても見られなかった現象が生まれている。
コロナ禍以前から問題となっていた地球温暖化問題が、さらに重要視されている。それは、近年、世界各地においてスーパー台風、洪水、森林火災など自然災害が過酷化、多発化していることへの危機意識を背景としている。世界各地、とりわけ欧州各国では「地球非常事態宣言」が発せられている。株主利益最優先を改めようとする動きが米国でも生まれ、「ステークホルダー資本主義」論が「情報・データ資本主義」論とならんで議論されている。「最大のステークホルダーは地球ではないか」という見方も浮上している。「地球安全保障」論の発想も生まれている(地球産業文化研究所報告)。
気候変動対策の国際的な枠組みとして190カ国・地域が批准したパリ協定が、2016年11月に発効した。米国のトランプ前政権は2017年に同協定から離脱したが、バイデン新政権になって2021年2月に復帰した。米国はいまや環境政策の旗振り役になろうとしている。象徴的なのは、菅・バイデン会談後の共同声明である。声明はこううたっている。
「気候危機は世界にとって生存に関わる脅威であると認識し、日米両国はこの危機と闘うための世界の取り組みを主導し、重要な役割を果たす。2050年温室効果ガス排出実質ゼロ目標と整合的な形で、2030年までに確固たる行動をとる。この責任を認識し、菅総理とバイデン大統領は『日米気候パートナーシップ』を立ち上げた」。
パリ協定合意と同じ2015年の国連サミットにおいて全会一致で合意したSDGs(持続可能な開発目標)がパリ協定理念と合流する格好で、気候変動、地球環境問題への各国の取り組みが加速している。
SDGsは17の目標を掲げているが、それを3つのグループに分類し、3つ重ねのウェディングケーキに見立てる発想が興味深い。一番下の層は地球環境がらみのもので、その他の目標を支えるという構図である。
パリ協定とSDGsはこうして合流した。それへの積極的な挑戦が成長・発展の制約ではなく新しい形の成長・発展につながるとの認識も強まり、グリーン成長戦略を打ち出す国が増えている。日本も化石賞を返上すべく、遅ればせながらではあるが菅政権が2020年10月に「温暖化ガス2050年ゼロ」目標を表明し、日米首脳会談の直後には、2030年までに温暖化ガスの排出を2013年度比で46%削減するとの目標を打ち出した。
その目標達成には政策対応、産業構造、経営モデルからライフスタイルに及ぶ、グレート・リセットと称される大きな変革が必要になる。デジタル化もそうした変革を支える上で不可欠な戦略でもある。
ただ、デジタル化、情報化に関しては副作用の抑制も必要になろう。プライバシー保護をどう扱うかという問題も重要である。民主主義の在り方をめぐる議論も活発になっている。この点に関してはデジタル時代の情報リテラシーの問題にも目を向けなければならない。パンデミックをもじったインフォデミックが注目されだした。真偽が不明な情報の氾濫・拡散の危険のことである。
インターネットを通じた情報の多くは匿名で、かつ個人でも既存の巨大メディアを超えるような伝播力を持つことがある。また、フェイクニュースが新型コロナウイルスの情報に関しても増え、社会の混乱を招いてもいる。
間違った情報には、単純な誤情報であるmis-information、意図的な偽情報であるdis-information、さらに悪意のある攻撃mal-informationがある。
Post Truthの時代だともいわれる。自分が共感できる情報、得になる情報が真実だと意識する傾向も台頭しつつある。インターネット検索サイトがユーザーを識別しユーザーの欲しいと思われる情報を推定し、見たくなさそうな情報を遮断する(フィルタリング)という現象もある。健全な民主主義、市場経済を確保するために、こうした問題をどう処理するか。デジタル時代の情報リテラシーは重大な問題である。
当面のコロナ危機はいずれ収束するだろうが、その時期はワクチンの普及に大きく依存する。順調な普及ができず、危機が長期化するリスクもある。ウィズコロナの長期化である。
さらに、環境破壊が続く限り感染爆発は繰り返されるとする見方も生まれている。自然の生態系が破壊され、ウイルス感染が起きやすいようにウイルスが「解放される」ためだという説である。
いずれにしても今回のコロナ危機はデジタル化を一気に加速し、地球環境問題への危機意識を醸成し、それにより、経済・社会に大きな変革と転換をもたらしつつある。あるいは、それを必要としている。100年以上も続いたエンジン車の文明もデジタル技術と環境重視が重なって推進されだしたEV(電気自動車)の挑戦を受けている。
いろいろな面において、今回のコロナ危機は従来からの政策、制度、経営、生活様式、さらには国際関係にまで影響を及ぼしつつある。グレート・トランスフォーメーション(大転換)、グレート・リセットの時代なのだろう。
リセットが求められる分野は多方面にわたっている。まず、国際関係において、多国間主義、自由貿易主義が脅かされていることを真剣に受け止めなければならない。近年、国際関係において、いくつもの「分断」が生じている。急速に台頭し、自らも大国指向の中国に対して米国が警戒心を高め、地政学的な変動を背景とした米中”新冷戦“が懸念されている。両国は貿易制限、報復を繰りかえしている。
そうした状況にコロナ禍が上乗せされ、国際関係は一層ぎくしゃくしだした。貿易面では輸入制限だけでなく安全保障を大義名分として輸出管理(規制)、投資規制の動きも強まっている。
世界が直面する問題には地球環境、感染症、テロ対策など一国だけでは対処できず、対立ではなくむしろ一層の協調、協力が不可欠な分野がある。
民主主義のリセットも必要である。米国の2020年の大統領選挙では、トランプ前大統領が「選挙に不正があった」とし、選挙結果を受け入れようとせず、多くのトランプ支持者が連邦議会に乱入するという事態にまで発展した。民主主義の基本が揺らいでいる。それには前述のインフォデミックも関連している。
さらに格差をめぐる問題も深刻である。それは、資本主義の在り方にまで絡む議論を生んでいる。資本主義は1970年代までは「調和的成長の時代」をもたらした。それはイノベーションを生み、成長と生活水準の向上を実現した。豊かさの格差はあっても富める者から富がしたたり落ちるように貧しい者にも自然と浸透していくという、いわゆるトリクルダウン論があった。しかし80年代以降、格差の拡大こそが問題となり、90年代から21世紀にはいってからは中間層の崩壊、それによる社会の分断が米国はじめ、多くの国で注目されるようになった。コロナ禍は格差問題を増幅した。経済回復のパターンとしてV字型とか、L字型とかがあるが、現在問題となっているのは格差拡大、二極化を示すK字型である。富める者はますます富み、貧しいものはますます貧しくなる現象である。これには同じ国のなかでの産業間、職業間、地域間、階層間の格差拡大に加えて国と国の間の格差の拡大がある。そうした格差の拡大が資本主義の在り方に問題を投げかけている。
2008年の米国投資会社、リーマン・ブラザーズ社の経営破綻をきっかけとした世界金融危機の際には、金融資本主義の暴走が問題となり、格差拡大に憤った人々が米国資本主義のシンボルであるウォール街を取り巻くデモを起こした。資本主義の在り方をめぐる議論が高まる中で、米国の主要企業が名を連ねる財界ロビーグループであるビジネス・ラウンドテーブルが2019年8月に声明を発表した。その内容は、米国経営の原則とされた株主資本主義、利益優先企業経営を自ら批判し、「ステークホルダー資本主義」への転換を宣言したものだった。それは現在加速しているESG(環境、社会的責任、不祥事を防ぐ企業統治)重視の経営・投資態度と重なるもので、従来の資本主義、企業経営の在り方が問われている。
またコロナ禍のなかでIT技術、デジタル技術が威力を発揮しているが、これもK字型経済を加速させている。IT企業の収益はコロナ禍の中で一段と増大した。株式市場でもK字型が見られ、米国の巨大IT5社GAFAMの株式時価総額が日本の東証1部約2170社の時価総額合計を上回った。これらIT5社の独占的な状況も懸念され、さらにその税負担率が米企業平均、各国企業平均より低いことも問題となっている。
巨大IT企業の一段の拡大が資本主義の在り方の論議に新しい課題を提示している。ここでも格差が、国と国の間、同じ国における業種間、個人間で問題となっている。さらにIT企業は自動車産業などと比べ、雇用の創出が少ないことも注目される。資本主義が急速の無形資産をもとにした利益に依存する形になっており、有形資本中心だったこれまでの資本主義における税制の在り方も、問い直されつつある。
スイスに本部を置くWEF(ワールド・エコノミック・フォーラム)は毎年、「ダボス会議」でグローバルなアジェンダ・セッティングをしており、今年は「グレート・リセット」をテーマとしてコロナ後の世界の在り方をめぐる討議を予定していた。だが、コロナ禍で、例年、1月に開く総会はネット会議になり、延期し5月に予定したシンガポール総会も中止となってしまった。パンデミックの深刻さを象徴する顛末だといえよう。しかし、これから様々なレベルにおいて、また各国でグレート・リセットが議論され、試みられると思われる。
当面のコロナ危機はワクチンが普及すれば山をこえるだろうが、その影響は永続しよう。コロナ後の世界がコロナ以前に戻ることはない。すでに過去の延長線上にはない新しい時代が生まれつつある。
世界経済における債務の状況も、コロナ前のトレンドとは断絶した格好で膨張している。IIF(国際金融協会)によると、世界が抱える債務は2020年に24兆ドル膨らんだ。世界全体のGDPの3.5倍を上回る。その後のコロナ対策で債務は一段と増大している。コロナ後にこれをどう処理するのか。政府が抱える公的債務も急膨張している。各国政策当局にも危機意識が生まれている。法人税率の引き下げ競争をやめようとする議論が始まったのはこのためである。
”ウィズコロナ”の状態が長期化しそうである。米国の調査会社であるユーラシア・グループは2021年始め発表した今年の世界10大リスクで、「新型コロナの長期化による影響」を2番目にあげた。そこでもコロナ禍の遺産としての巨額な公的債務に注目している。また、雇用喪失を背景に政府への信頼の喪失、社会分断の危険性を指摘、社会不安が高まることを警戒している。
”ウィズコロナ”の状態がすでに予想されたより長引いている。さらに長期化しそうである。ポストコロナ、アフターコロナを迎える前に取り組むべき課題は多い。従来からの在り方を根本的に問い直す、グレート・リセットの発想が欠かせない。
執筆者プロフィール
小島 明(こじま あきら)
一般財団法人 国際経済連携推進センター 理事長
ジャーナリスト、国際経済学者。日本経済新聞社ニューヨーク支局長、編集委員、論説委員、常務取締役論説主幹、専務取締役論説担当、公益社団法人・日本経済研究センター会長。政策研究大学院大学理事、客員教授。公益財団法人・本田財団理事、公益財団法人・イオンワンパーセントクラブ理事。2019年より国際経済連携推進センター理事長。
ボーン・上田記念国際記者賞、日本記者クラブ賞受賞。
主な著作に『「日本経済」どこへ行くのか(上)(下)』平凡社(2013年)など。

