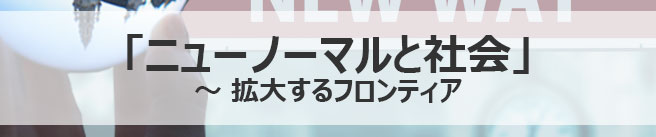
(3) DXの時代にこそじっくりと本質的問題を

掲載日:2020年11月6日
青山学院大学 名誉教授
新潟県立大学 名誉教授
袴田 茂樹
はじめに
今日の日本が陥っている状況を過去と比較しながら概観し、その後で、何故このような事態になったのか、今後日本はどんな道を進むべきかなどについて考えてみたい。
まず、ショッキングな以下の2つの情報を基に、長期の歴史的視点から、われわれの生活や文化の根本問題を考えたい。
1) 現在、わが国はデジタル人材が大きく不足しているという。スイスのローザンヌに拠点を置く、世界のトップクラスのビジネススクールIMD(International Institute for Management Development)が、デジタル競争力の世界ランキングを公表した。それによると、日本のデジタル関連のスキルを示す指標は、63カ国・地域の中で、何と62位に沈んでいるという(日本経済新聞 2020.10.9)。
2) もう一つの衝撃的な事件は、これは周知のことだが、今年10月1日に東京証券取引所でシステム障害が生じて、その日は終日、全銘柄の取引が停止となった。翌日には復旧したが、上場会社数は3,700余りなので、その日はわが国における金融界の頭脳あるいは心臓が停止したとも言える。現代国家としては、あるまじきことが生じたのだ。
しかもその原因が、防御が難しい巧妙な新型サイバー攻撃を受けたのではなく、システム障害だったこと、またそのような障害が生じた際には自動的に機能するはずのバックアップ(Failover)システムが、機能しなかったからだと伝えられた。この報道が正しいとすれば、私のようなアナログ世代から見ても、そのお粗末さは何をか言わんや、である。
(ちなみに、このシステムを担った富士通が理研と共同開発したスーパーコンピュータ「富岳」は、2020年6月には性能ランキングで世界最速を記録しており、富士通の問題と言うつもりはない。)
わが国の経済・社会の基礎が、技術や人材面から見て、またその教育面から見てお粗末な砂上の楼閣ではなかったのかという危惧の念を抱かざるを得ない。さらに、後述のようにこの問題への文科省の性急な対応策は、長期的に見てわが国に禍根を残すことになるのではないか、との懸念も抱く。
「日本は21世紀の国」
1)と2)の2つの事例によって国際政治の専門家として私が深刻に考えるのは、1970-80年代の「輝ける先進国日本」と、1990年代以後の「失われた20年、30年」として各国から「反面教師」と見られるようになった2つのわが国の大きなイメージギャップである。
以下は、90年代半ばに3年半にわたり月刊誌『フォーサイト』に連載し、その後単行本『沈みゆく大国――日本とロシアの世紀末から』(新潮選書 1996)として出版された拙著の一部の要約である。これは筆者が1960年代半ばから70年代初めまでソ連に5年留学し、その後もロシア人の友人、知人たちとの交流を続けた経験を背景に書いたものである。
つい数年前には、21世紀は「日本の世紀」だと浮かれていた日本人も、バブルがはじけてみると、日本の繁栄の底の浅さをみせつけられ、今はシュンとした気持ちになっている。
1960年代中ごろ、初めて私がソ連に行った頃は、一般のソ連人は、社会主義体制の優越性を素直に信じていた。そして、戦勝国でスプートニクや宇宙飛行士を世界で最初に打ち上げたソ連と比べ、敗戦国日本は貧しい後れた二流国家と見ていた。私が「ソ連の店より日本のデパートやスーパーの方がずっと豊かですよ」と言っても、見え透いた嘘を言う者と軽蔑されたものである。
しかし、1960年代末から70年代初めにかけて、日本イメージが急変した。西ドイツや日本の奇跡的発展について諸情報が伝わって来たからだ。そして実生活においても、ソニーやパナソニックに接する機会も生まれ、ソ連の工業製品との品質格差に愕然とし、エレクトロニクスだけでなくトヨタ、コマツなど日本製品は最高品質の代名詞として一般国民にも知られるようになった。
1970年代、80年代の日本の発展は、社会主義体制の優位を信じていた、また豊かな資源や大きな領土を有する国こそが大国だと思っていたソ連人に強烈な衝撃を与えた。彼らの物差しや価値観から見ると、どの点から見ても劣っているアジアの小国かつ敗戦国が、ソ連を追い抜いて米国と一、二位を競う経済大国、科学技術大国になったのだから。当時のソ連のアネクドート(小話)に次のようなものがある。
何故、日本とソ連にエイズが少ないのか。その理由は、エイズは20世紀の病気だが、日本はすでに21世紀の国であり、ソ連はまだ19世紀の国だから。
こうして、1980年代のペレストロイカ(改革)時代のソ連知識人の間では「日本を見ずして改革を語るなかれ」という空気さえ生まれ、誰でも国外に行けるわけではないので、オピニオンリーダーの間では「日本詣で」が憧れとなった。1970-80年代には、筆者もソ連の有識者を日本に招いてシンポジウムなどを組織していたが、どんな重鎮でも、声を掛けると二つ返事で来日したものである。彼らは、日本のデパートやスーパーを見ると、「嗚呼、これこそが本来の共産主義だ」と言ったものだ。モスクワ大学のある女性教授は、講義の時に「日本に2回行ったことがある」と述べただけで、学生は無条件に彼女の権威を認めたと言う。
「ゆとり教育」と日本は戦略的失敗
しかし、私の知人でこのような日本観を最初にはっきり否定したのは、改革派のリーダーであったガブリエル・ポポフ元モスクワ市長だ。すでに1993年に彼は私に、「日本は戦略的な失敗を犯しつつある。ハイテク分野でも、これから日本は米国に大きく水を開けられるだろう」と、断言した。
ポポフ氏は日本に招かれて、政治・経済分野だけでなく、教育分野もしっかり視察し研究していた。現在から振り返ってみると、彼の93年の予測は驚くほどズバリと的中していたのだが、彼がそう判断した理由は何だろうか。
実は、その時彼がその理由をどう説明したか、私ははっきりとは覚えていないのだが、彼は元モスクワ大学教授として(私は同大学の大学院生として、1970年頃に彼と知り合った)、1980年代、90年代の日本の教育に目を向け、疑問を持ったのはほぼ間違いないと考える。
1980年代から90年代にかけて、わが国では所謂「ゆとり教育」が浸透しつつあった。彼はその教育の実態を見て、20年、30年先の日本を推察したと考えられる。わが国が今日の状況に陥った原因は複雑な要因が絡んでおり単純化しては言えないが、文科省(文部省)と日教組が組んで推進した「ゆとり教育」も、間違いなくその重要な要因と私は考える。
「ゆとり教育」は、ある教育状況に対する反動として生じた。皮肉なことに、その教育状況とは1957年10月のスプートニク・ショックによって生まれたものだ。ソ連が世界で最初にスプートニクを打ち上げ、欧米や日本は強い衝撃を受けて、1960-70年代は理数系の科目が重視されるようになった。そして70年代には、わが国の小学、中学、高校でも集合論やベクトル・行列が導入された。
こうして数学だけでなく、学校で教える理科も大変詳しく難しくなり、やがて「落ちこぼれ」が問題化した。そこで、多くの知識の「詰め込み教育」が批判されるようになって、その結果「ゆとり教育」に行き着いた。その際のスローガンは、受け身の「記憶力」ではなく、主体的な「思考力」や「自発性」「創造性」を養う、だった。学校の教科書は薄くなり、2002年には学校の週5日制が導入された。生徒の為と言うよりも、日教組が自らのために主導したのではないか。
しかしこれら「ゆとり教育」の結果は、生徒や学生の理数系離れであり、また様々な国際的調査でも明らかなように、過去20-30年間のわが国の生徒(学生)の学力の大幅低下である。主体性や創造性の育成にも、見るべき結果はほとんどなかった。国語や漢字の能力も低下し、数学などの読解力も落ちた。
こういう状況になったので、意欲や能力と親に財力のある生徒は、公立学校ではなく私立学校を選び、また塾が学校以上の役割を担うようにもなった。この「ゆとり教育」の結果に対する危機意識が強まり、教育の軌道修正がなされたのは、第1次安倍政権下の2007、2008年であった。「脱ゆとり教育」によって再び、学校の教科書は少しずつ厚くなった。
文科省の性急な対応策
ここで懸念されるのは、「ゆとり教育」の惨憺たる結果に対する文科省や教育界の性急なリアクションである。「ゆとり教育」の失敗が今日のわが国が陥った状況と密接に結びついていることは、当然認めるべきだと考える。しかし私が問題としたいのは、DX、イノベーションの活用、DXとビジネスモデルの変革などを基礎とした「ニューノーマルの社会」に向かっての文科省の視野狭窄的とも言える性急な対応だ。
2015年3月に、文科省は「理工系人材育成戦略」を発表し、同年6月には「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」を発表した。後者には、次のような文言があって文科系の大学学部などから強い反発を受けた。
「特に、教育養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。」
ここで問題とされたのは、理系の充実が、あるいは工業部門の発展が国家の繁栄に寄与する、との狭い発想であり、文科系学部の軽視と理解された。
幸い、わが国の経団連が直ちに、経済界や社会が求める人材育成に関連して、狭い意味での理系重視、すなわち工業生産のための数学や物理や応用技術のみの重視に否定的な見解を示し、新時代に求められるのは深い教養を背景に真の創造力を備えた人材だと公表した。その後2018年6月に経団連は「今後のわが国の大学教育の在り方に関する提言」を発表し、そこでは、文系学生だけでなく理系学生に対しても、「多様で幅広い知識と教養、リベラルアーツを身につけ、それらを基礎として自ら深く考え抜き、自らの言葉で解決策を提示することのできる人材が求められる」としたのである。これを経団連は「イノベーション人材」とも称している。
実は、真の創造力の土台となる教養とかリベラルアーツの貧困さは、「ゆとり教育」以前からの、つまりわが国の戦後教育を通じての問題であった。日本が世界に輝いた1970年代、80年代までは、現在よりもGDPに占める工業生産の割合がはるかに高く、国の発展のためには、精巧で高品質の工業製品生産が第一課題であった。70年代、80年代の「輝ける日本」は、それによって生み出された。しかし社会や経済が複雑化した今日以後は、そのような対応だけでは日本の行き詰まりを脱却できない。DXの時代には、高品質の工業製品の生産者や技術者だけでなく、もっと幅広く深みのある創造的な人材が強く求められている。
文科省の性急な対応策には、その辺の認識が欠けているのではないかと私は強い懸念を抱き、「人文系組織の廃止と社会的要請の高い分野への転換」が打ち出された当時、メディアにもその懸念を表明した。冒頭に述べたDXとビジネスモデルの変革とか「ニューノーマル」に求められているのは、単に理科系教育の重視で済まされる問題ではなく、まさに「リベラルアーツを基礎に創造的に自らの言葉で解決策を提示できる人材」である。今日のわが国に、真の意味で「自らの言葉」で語れる人間、すなわち創造的な人間がどれだけ少ないか、これは私が常に問題にしていることでもある。
むすび
最後に、1996年に出版した前述の拙著『沈みゆく大国』の中の文言を、結びの言葉に代えたい。二十数年前の言葉であるが、今日にもそのまま通用すると私は確信している。
現在のパソコンやインターネットへの我々の関心の持ち方も、新技術導入に夢中になった明治以来の日本人の強迫観念を一歩も出ていない。情報、情報と騒いで、世界の情報革命に遅れないようにと危機意識を募らせているが、自ら語るべき言葉や文化に関しては、あるいは文化の創造性やその発信に関しては、ほとんど無関心である。私は、むしろこちらの方にはるかに深刻な危機を感じる。今日のように政治や社会の原理的な問題が問われている時代には、最新の情報や論文に数多く目を通すよりも、古典をじっくり読んで深く考えることの方が、よほど有益である。
執筆者プロフィール
袴田 茂樹(はかまだ しげき)
青山学院大学名誉教授、新潟県立大学名誉教授
国際経済連携推進センター(CFIEC)評議員、CFIEC・中央ユーラシア調査会座長。
1967年東京大学文学部哲学科卒、モスクワ大学大学院修了、東京大学大学院国際関係論博士課程単位取得退学。プリンストン大学客員研究員、東京大学大学院客員教授を歴任。ロシア東欧学会元代表理事、安全保障問題研究会会長。サントリー学芸賞選考委員。
主な著書に『深層の社会主義』(サントリー学芸賞受賞)ほか。
青山学院大学 名誉教授
新潟県立大学 名誉教授
袴田 茂樹
はじめに
今日の日本が陥っている状況を過去と比較しながら概観し、その後で、何故このような事態になったのか、今後日本はどんな道を進むべきかなどについて考えてみたい。
まず、ショッキングな以下の2つの情報を基に、長期の歴史的視点から、われわれの生活や文化の根本問題を考えたい。
1) 現在、わが国はデジタル人材が大きく不足しているという。スイスのローザンヌに拠点を置く、世界のトップクラスのビジネススクールIMD(International Institute for Management Development)が、デジタル競争力の世界ランキングを公表した。それによると、日本のデジタル関連のスキルを示す指標は、63カ国・地域の中で、何と62位に沈んでいるという(日本経済新聞 2020.10.9)。
2) もう一つの衝撃的な事件は、これは周知のことだが、今年10月1日に東京証券取引所でシステム障害が生じて、その日は終日、全銘柄の取引が停止となった。翌日には復旧したが、上場会社数は3,700余りなので、その日はわが国における金融界の頭脳あるいは心臓が停止したとも言える。現代国家としては、あるまじきことが生じたのだ。
しかもその原因が、防御が難しい巧妙な新型サイバー攻撃を受けたのではなく、システム障害だったこと、またそのような障害が生じた際には自動的に機能するはずのバックアップ(Failover)システムが、機能しなかったからだと伝えられた。この報道が正しいとすれば、私のようなアナログ世代から見ても、そのお粗末さは何をか言わんや、である。
(ちなみに、このシステムを担った富士通が理研と共同開発したスーパーコンピュータ「富岳」は、2020年6月には性能ランキングで世界最速を記録しており、富士通の問題と言うつもりはない。)
わが国の経済・社会の基礎が、技術や人材面から見て、またその教育面から見てお粗末な砂上の楼閣ではなかったのかという危惧の念を抱かざるを得ない。さらに、後述のようにこの問題への文科省の性急な対応策は、長期的に見てわが国に禍根を残すことになるのではないか、との懸念も抱く。
「日本は21世紀の国」
1)と2)の2つの事例によって国際政治の専門家として私が深刻に考えるのは、1970-80年代の「輝ける先進国日本」と、1990年代以後の「失われた20年、30年」として各国から「反面教師」と見られるようになった2つのわが国の大きなイメージギャップである。
以下は、90年代半ばに3年半にわたり月刊誌『フォーサイト』に連載し、その後単行本『沈みゆく大国――日本とロシアの世紀末から』(新潮選書 1996)として出版された拙著の一部の要約である。これは筆者が1960年代半ばから70年代初めまでソ連に5年留学し、その後もロシア人の友人、知人たちとの交流を続けた経験を背景に書いたものである。
つい数年前には、21世紀は「日本の世紀」だと浮かれていた日本人も、バブルがはじけてみると、日本の繁栄の底の浅さをみせつけられ、今はシュンとした気持ちになっている。
1960年代中ごろ、初めて私がソ連に行った頃は、一般のソ連人は、社会主義体制の優越性を素直に信じていた。そして、戦勝国でスプートニクや宇宙飛行士を世界で最初に打ち上げたソ連と比べ、敗戦国日本は貧しい後れた二流国家と見ていた。私が「ソ連の店より日本のデパートやスーパーの方がずっと豊かですよ」と言っても、見え透いた嘘を言う者と軽蔑されたものである。
しかし、1960年代末から70年代初めにかけて、日本イメージが急変した。西ドイツや日本の奇跡的発展について諸情報が伝わって来たからだ。そして実生活においても、ソニーやパナソニックに接する機会も生まれ、ソ連の工業製品との品質格差に愕然とし、エレクトロニクスだけでなくトヨタ、コマツなど日本製品は最高品質の代名詞として一般国民にも知られるようになった。
1970年代、80年代の日本の発展は、社会主義体制の優位を信じていた、また豊かな資源や大きな領土を有する国こそが大国だと思っていたソ連人に強烈な衝撃を与えた。彼らの物差しや価値観から見ると、どの点から見ても劣っているアジアの小国かつ敗戦国が、ソ連を追い抜いて米国と一、二位を競う経済大国、科学技術大国になったのだから。当時のソ連のアネクドート(小話)に次のようなものがある。
何故、日本とソ連にエイズが少ないのか。その理由は、エイズは20世紀の病気だが、日本はすでに21世紀の国であり、ソ連はまだ19世紀の国だから。
こうして、1980年代のペレストロイカ(改革)時代のソ連知識人の間では「日本を見ずして改革を語るなかれ」という空気さえ生まれ、誰でも国外に行けるわけではないので、オピニオンリーダーの間では「日本詣で」が憧れとなった。1970-80年代には、筆者もソ連の有識者を日本に招いてシンポジウムなどを組織していたが、どんな重鎮でも、声を掛けると二つ返事で来日したものである。彼らは、日本のデパートやスーパーを見ると、「嗚呼、これこそが本来の共産主義だ」と言ったものだ。モスクワ大学のある女性教授は、講義の時に「日本に2回行ったことがある」と述べただけで、学生は無条件に彼女の権威を認めたと言う。
「ゆとり教育」と日本は戦略的失敗
しかし、私の知人でこのような日本観を最初にはっきり否定したのは、改革派のリーダーであったガブリエル・ポポフ元モスクワ市長だ。すでに1993年に彼は私に、「日本は戦略的な失敗を犯しつつある。ハイテク分野でも、これから日本は米国に大きく水を開けられるだろう」と、断言した。
ポポフ氏は日本に招かれて、政治・経済分野だけでなく、教育分野もしっかり視察し研究していた。現在から振り返ってみると、彼の93年の予測は驚くほどズバリと的中していたのだが、彼がそう判断した理由は何だろうか。
実は、その時彼がその理由をどう説明したか、私ははっきりとは覚えていないのだが、彼は元モスクワ大学教授として(私は同大学の大学院生として、1970年頃に彼と知り合った)、1980年代、90年代の日本の教育に目を向け、疑問を持ったのはほぼ間違いないと考える。
1980年代から90年代にかけて、わが国では所謂「ゆとり教育」が浸透しつつあった。彼はその教育の実態を見て、20年、30年先の日本を推察したと考えられる。わが国が今日の状況に陥った原因は複雑な要因が絡んでおり単純化しては言えないが、文科省(文部省)と日教組が組んで推進した「ゆとり教育」も、間違いなくその重要な要因と私は考える。
「ゆとり教育」は、ある教育状況に対する反動として生じた。皮肉なことに、その教育状況とは1957年10月のスプートニク・ショックによって生まれたものだ。ソ連が世界で最初にスプートニクを打ち上げ、欧米や日本は強い衝撃を受けて、1960-70年代は理数系の科目が重視されるようになった。そして70年代には、わが国の小学、中学、高校でも集合論やベクトル・行列が導入された。
こうして数学だけでなく、学校で教える理科も大変詳しく難しくなり、やがて「落ちこぼれ」が問題化した。そこで、多くの知識の「詰め込み教育」が批判されるようになって、その結果「ゆとり教育」に行き着いた。その際のスローガンは、受け身の「記憶力」ではなく、主体的な「思考力」や「自発性」「創造性」を養う、だった。学校の教科書は薄くなり、2002年には学校の週5日制が導入された。生徒の為と言うよりも、日教組が自らのために主導したのではないか。
しかしこれら「ゆとり教育」の結果は、生徒や学生の理数系離れであり、また様々な国際的調査でも明らかなように、過去20-30年間のわが国の生徒(学生)の学力の大幅低下である。主体性や創造性の育成にも、見るべき結果はほとんどなかった。国語や漢字の能力も低下し、数学などの読解力も落ちた。
こういう状況になったので、意欲や能力と親に財力のある生徒は、公立学校ではなく私立学校を選び、また塾が学校以上の役割を担うようにもなった。この「ゆとり教育」の結果に対する危機意識が強まり、教育の軌道修正がなされたのは、第1次安倍政権下の2007、2008年であった。「脱ゆとり教育」によって再び、学校の教科書は少しずつ厚くなった。
文科省の性急な対応策
ここで懸念されるのは、「ゆとり教育」の惨憺たる結果に対する文科省や教育界の性急なリアクションである。「ゆとり教育」の失敗が今日のわが国が陥った状況と密接に結びついていることは、当然認めるべきだと考える。しかし私が問題としたいのは、DX、イノベーションの活用、DXとビジネスモデルの変革などを基礎とした「ニューノーマルの社会」に向かっての文科省の視野狭窄的とも言える性急な対応だ。
2015年3月に、文科省は「理工系人材育成戦略」を発表し、同年6月には「国立大学法人等の組織及び業務全般の見直しについて」を発表した。後者には、次のような文言があって文科系の大学学部などから強い反発を受けた。
「特に、教育養成系学部・大学院、人文社会科学系学部・大学院については、18歳人口の減少や人材需要、教育研究水準の確保、国立大学としての役割等を踏まえた組織見直し計画を策定し、組織の廃止や社会的要請の高い分野への転換に積極的に取り組むよう努めることとする。」
ここで問題とされたのは、理系の充実が、あるいは工業部門の発展が国家の繁栄に寄与する、との狭い発想であり、文科系学部の軽視と理解された。
幸い、わが国の経団連が直ちに、経済界や社会が求める人材育成に関連して、狭い意味での理系重視、すなわち工業生産のための数学や物理や応用技術のみの重視に否定的な見解を示し、新時代に求められるのは深い教養を背景に真の創造力を備えた人材だと公表した。その後2018年6月に経団連は「今後のわが国の大学教育の在り方に関する提言」を発表し、そこでは、文系学生だけでなく理系学生に対しても、「多様で幅広い知識と教養、リベラルアーツを身につけ、それらを基礎として自ら深く考え抜き、自らの言葉で解決策を提示することのできる人材が求められる」としたのである。これを経団連は「イノベーション人材」とも称している。
実は、真の創造力の土台となる教養とかリベラルアーツの貧困さは、「ゆとり教育」以前からの、つまりわが国の戦後教育を通じての問題であった。日本が世界に輝いた1970年代、80年代までは、現在よりもGDPに占める工業生産の割合がはるかに高く、国の発展のためには、精巧で高品質の工業製品生産が第一課題であった。70年代、80年代の「輝ける日本」は、それによって生み出された。しかし社会や経済が複雑化した今日以後は、そのような対応だけでは日本の行き詰まりを脱却できない。DXの時代には、高品質の工業製品の生産者や技術者だけでなく、もっと幅広く深みのある創造的な人材が強く求められている。
文科省の性急な対応策には、その辺の認識が欠けているのではないかと私は強い懸念を抱き、「人文系組織の廃止と社会的要請の高い分野への転換」が打ち出された当時、メディアにもその懸念を表明した。冒頭に述べたDXとビジネスモデルの変革とか「ニューノーマル」に求められているのは、単に理科系教育の重視で済まされる問題ではなく、まさに「リベラルアーツを基礎に創造的に自らの言葉で解決策を提示できる人材」である。今日のわが国に、真の意味で「自らの言葉」で語れる人間、すなわち創造的な人間がどれだけ少ないか、これは私が常に問題にしていることでもある。
むすび
最後に、1996年に出版した前述の拙著『沈みゆく大国』の中の文言を、結びの言葉に代えたい。二十数年前の言葉であるが、今日にもそのまま通用すると私は確信している。
現在のパソコンやインターネットへの我々の関心の持ち方も、新技術導入に夢中になった明治以来の日本人の強迫観念を一歩も出ていない。情報、情報と騒いで、世界の情報革命に遅れないようにと危機意識を募らせているが、自ら語るべき言葉や文化に関しては、あるいは文化の創造性やその発信に関しては、ほとんど無関心である。私は、むしろこちらの方にはるかに深刻な危機を感じる。今日のように政治や社会の原理的な問題が問われている時代には、最新の情報や論文に数多く目を通すよりも、古典をじっくり読んで深く考えることの方が、よほど有益である。
執筆者プロフィール
袴田 茂樹(はかまだ しげき)
青山学院大学名誉教授、新潟県立大学名誉教授
国際経済連携推進センター(CFIEC)評議員、CFIEC・中央ユーラシア調査会座長。
1967年東京大学文学部哲学科卒、モスクワ大学大学院修了、東京大学大学院国際関係論博士課程単位取得退学。プリンストン大学客員研究員、東京大学大学院客員教授を歴任。ロシア東欧学会元代表理事、安全保障問題研究会会長。サントリー学芸賞選考委員。
主な著書に『深層の社会主義』(サントリー学芸賞受賞)ほか。

